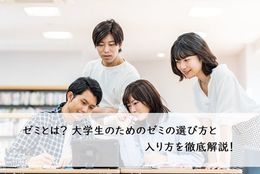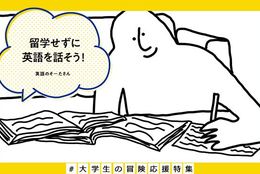レポートの参考文献の書き方は? 電子書籍やネット記事を参考にする場合のルールも解説
本記事ではレポートの参考文献の書き方について解説します。 大学に入るとレポート課題がたくさん出ますね。今回は記載例を何点かご紹介するほか、電子書籍やネット記事を参考文献とする方法についても解説します。是非参考にしてみてください。
▼目次
1.参考文献とは何?
2.なぜレポートで参考文献を記載するのか
3.参考文献で記載する項目は?
4.参考文献の書き方例を紹介!
5.参考文献を書く上で気を付けたいポイント
6.電子書籍を参考にした場合はどうなる?
7.参考文献以外にも知っておきたい、レポートの書き方
▼こちらもチェック!
レポートの書き方まとめ! 基本の書式・構成や高評価をもらえるまとめ方とは?
参考文献とは何?
参考文献とは、レポートや論文を書くにあたって、よそから引用したり内容を参考にしたりした文献のことを指します。文献には書籍や雑誌中の論文、電子ジャーナルのほかWebサイト記事なども含まれます。
参考文献は、レポートの末尾に全てまとめて出典を明示しなければなりません。
1.表紙
2.レポートの本文
3.References(参考文献)
4.Appendix(補遺・付表・追記など)
上記3の「References(参考文献)」のところですね。本文が終わった後に参考文献をまとめて記載することになります。
なぜレポートで参考文献を記載するのか
なぜ参考文献を記載するのか、その理由と目的は次のとおりです。
2.自分の見解部分を明らかにするため
3.先行研究者の業績に対して敬意を払うため
4.読み手へ情報提供するため
これらを順番に解説します。
出典を明示しないと著作権法違反となる
著作権法では、誰かの著作物の一部分を自分の文章で利用するためには、出典を明示しなければならないと定められています(著作権法第48条(出所の明示))。出典を明らかにしておかないのは著作権法違反となってしまいます。
他人の著作での主張を、あたかも自分の主張であるかのように記載するのは「盗用」「剽窃(ひょうせつ)」にあたり、許されることではありません。
自分の見解部分を明らかにするため
参考文献を正しく記載することで、「レポート内のどの点が作成者のオリジナルな見解なのか」を明らかにすることができます。どこまでが先人の研究結果で、どこが自分独自の考えなのか、区別しやすくなるということです。
先行研究者の業績に対して敬意を払うため
「この部分は先行研究者Aが述べている」と示すことで、先人の業績に対して敬意を払うことにもつながります。
読み手へ情報提供するため
参考文献が明示されていることで、読む人が、レポート内に登場する各種データ、引用の原典に当たることが可能になります。原典が怪しい、また現在では否定されているような実験や主張を参照したレポートであれば、そこから論拠があいまいだと評価できます。このような確認ができるのも参考文献が明示されていればこそです。
参考文献で記載する項目は?

参考文献を挙げる場合には、大きく分けて以下の4項目を表記しなければなりません。
・書名,雑誌名,論文標題
・版表示,出版社,出版年,ページなど
・媒体表示,参照日付など
※ページ数が単数の場合は「p」を、複数の場合は「pp」を使い、「p.4」「pp.124-130」と表記する方法があります。
参考文献の書き方にはある程度の定型フォーマットがありますが、順番や区切り方などの詳細は色々な書き方が存在しています。大学のマニュアルや教員の指導によって異なることもあります。
もしも「このように書いてください」とマニュアルなどで明確に指定されていればそれを第一に優先すべきでしょう。もし明確な指定がない場合、定型フォーマットを「これ」と決めてレポート内で統一しておけば問題ありません。フォーマットについては次からご紹介する記載例を是非参考にしてみてください。
参考文献の書き方例を紹介!
参考文献の記載例として、今回は科学技術振興機構(JST)の科学技術情報流通技術基準(SIST)のひとつ、SIST 02で紹介された参照文献の書き方をメインにご紹介していきます。
SIST 02の基本ルールとして、先ほど4つに分けた項目間の区切りはピリオドを使い、項目内の各要素の区切りはコンマを使います。ただし論文標題・誌名・書名の末尾はピリオドです。
雑誌論文の場合
出版年は西暦で書くのが基本です。例を見てみましょう。
小池靖子,田中裕二.コロナ禍における健康維持の取り組み.日本医学会雑誌.2021,58巻,1号,p.13-23.
ピリオドとコンマが少しややこしいですが、注意深く記載していきましょう。
ページ表記については先ほど触れたとおり、複数ページの場合「pp」を使い「pp.13-23」と表記する方法もあります。ですがSIST 02での書き方によれば「p.13-23」とpひとつで良いことになっています。
ネット上の電子ジャーナル中の論文の場合
※(媒体表示)は省略可
電子ジャーナルの論文も、先ほどの雑誌論文と途中まで同じ。ピンクの色分けのところが追加される形です。
小池靖子,田中裕二.コロナ禍における健康維持の取り組み.日本医学会雑誌.2021,58巻,1号,p.13-23.http://123/456,(参照2022-06-10).
このように、入手先URLや入手日付、つまり参照した日付を記載します。
単行本の場合
※出版地,(シリーズ名,シリーズ番号),ISBNは省略可
※版表示は初版の場合は省略できます。
野尻哲史.貯蓄ゼロから始める安心投資で安定生活.明治書院,2015,352p.
352p.と「p.」がページ数の後にくるのは総ページ数であることを意味しています。
また、SIST 02以外のフォーマットとして、カッコ書きを使った例もあります。
野尻哲史『貯蓄ゼロから始める安心投資で安定生活』(2015年)明治書院,352p.
この場合は、書籍名を『 』、発行年を()でくくり、各要素の間を,(コンマ)で区切っています。
ウェブサイト中の記事の場合
※更新日付は省略可
ネット上にあるウェブサイト記事の場合のポイントは、入手先としてサイトURLを貼ること、そして入手日付(参照した日)を書くことです。ネットの記事は書き換えたり差し替えたりすることが容易ですし、場合によっては削除されることもあり得ます。そのため、「いつアクセスして情報を取得したのか」を記載するようになっています。
厚生労働省.“新型コロナワクチンの有効性・安全性について”.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yuukousei_anzensei.html,(参照2022-10-17).
官公庁ホームページのように著作者の人名が不明な場合は、著作権者&Webサイト名でもある「厚生労働省」と記載します。更新日付は省略しても構いませんが、参照日だけはしっかり書くようにしましょう。
参考文献を書く上で気を付けたいポイント
改めて、参考文献を書く上で気をつけたいポイントを2点ご紹介します。
レポート内でフォーマットを統一する
今回ご紹介した書き方に限らず、実際にはさまざまな参考文献の書き方が存在します。『』や()を使ったり、また順番もいろいろです。大切なのは、レポート内ではフォーマットを統一すること。項目の順番も一貫性を持たせるようにします。
文献の順番を整える
参考文献の記載順については、本文での参照箇所の書き方によって異なります。
⇒本文で参照するときは小さく番号をふっておき、参考文献欄ではその番号順に記載。
●ハーバード方式
⇒本文で参照するときは(著者名・発行年)を記載。参考文献欄では、著者名の五十音順またはアルファベット順に並べます。同じ著者名の文献が複数ある場合には、古い順に並べます。
どちらの方法にするかは学術分野によって傾向があるようです。ゼミや講義でのレポートの場合も、前例があればそれに従うようにしましょう。
電子書籍を参考にした場合はどうなる?

最近では書籍(単行本)を紙ベースではなく電子版で読む人が増えてきました。ここでは電子書籍を参考文献として挙げる場合のポイントについて解説します。
電子書籍は紙媒体と違って、ページ番号が端末によって変わったり、内容の書き換えをしやすいといった特徴があります。そのため、電子書籍ではなく紙の書籍を参考文献とすることを推奨する教員も多いようです。
それでも何らかの事情で電子書籍を参考文献にしたい場合は、項目の末尾に(Kindle版)などと電子書籍であることが分かるように記載しておくと良いです。
先ほどの記載例の一つに追記してみます。
野尻哲史.貯蓄ゼロから始める安心投資で安定生活.明治書院,2015,352p,Kindle版.
電子書籍は比較的新しい媒体ですので、先生によってその扱い方や見解は異なります(電子書籍は受け付けないなど)。よって電子書籍を利用する場合は、できるだけ事前に先生に相談することをオススメします。
参考文献以外にも知っておきたい、レポートの書き方
レポートは参考文献以外にも知っておきたいコツや書き方のルールがあります。ぜひ一度チェックしてみましょう!
✔レポートで引用を使うときの書き方は?課題提出の際に欠かせない基礎知識
✔レポートの書き出しに悩む大学生必見! 盛り込むべき内容と例文
参考文献の書き方はレポート、論文を書く上で非常に重要な要素です。その記載方法も講義で先生が教えてくれるかもしれませんが、早く覚えてその書式に慣れるようにしましょう。