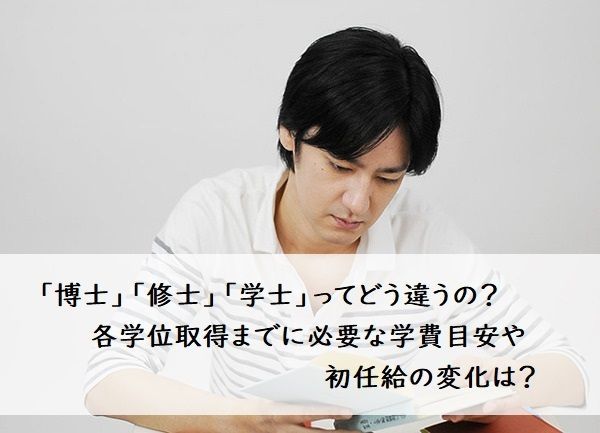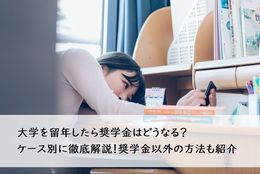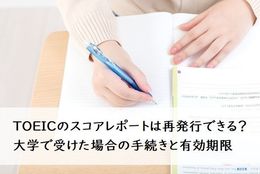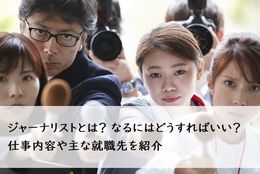「学士」「修士」「博士」とは? 各学位取得までに必要な学費目安や初任給の変化は?
「学士」「修士」「博士」とは?
「マスター」「ドクター」どっちがどっち?
耳にしたことはあっても、実は違いがよく分からないという人もいるのではないでしょうか。
今回はこの「学士」をはじめとした学位についてご紹介します。読み方などの基本事項から、どうすれば取得できるのか、気になる初任給の変化までお伝えしていきます。これからの進路や就職を考える際に参考にしてみてください。
▼目次
1.学位とは?
2.日本の主な学位4つ
3.専門士および高度専門士について
4.各学位取得までに必要な学費目安はどのくらい?
5.学位ごとの初任給の変化は?
6.まとめ
学位とは?
「学位」とは、主に次のような場合に授与される「称号」のことです。
・教育課程を履修、または試験に合格するなどして学業を修める
・学術的価値のある研究を修め、論文などを公刊する
・学術・教育の分野において功績を修める
学位の定義については、文部科学省ホームページからも抜粋してご紹介しておきます。
“学位は、大学の学部又は大学院教育修了相当の知識・能力の証明として、大学又は大学に準じた性格の機関が授与するものである。
(引用:文部科学省「用語の整理に関する参考資料」)”
つまり「学位」とは一般的に大学・短期大学・大学院を卒業あるいは修了した証明として与えられるものということになります。
学位には専攻分野がある
学士を含む学位は、専攻分野を付した上で授与されることになっています。理学や工学・医学・文学など、学部や学科名となっているものを考えるとわかりやすいでしょう。
この専攻分野は多岐にわたっており、例えば学士に付記される専攻分野の例として「現代コミュニケーション」「ファイナンス」「子ども学」といったものも。
授与される際は「学士(法学)」のように専攻分野が付記されることになります。
日本の主な学位4つ

学位は国によってさまざまですが、日本における学位は主に4つです。
いずれも国際的に通用するため、留学を希望する場合は覚えておくと役立ちます。
<日本の主な学位一覧>
| 学位 | 読み方 | 要件 |
| 学士 | がくし | 大学を卒業すると与えられる |
| 修士 |
しゅうし (マスター) |
大学院の修士課程を修めると与えられる |
| 博士 | はくし (ドクター) |
大学院の博士課程を修めると与えられる |
| 短期大学士 | たんきだいがくし | 短期大学を卒業すると与えられる |
このほかに、(専門職)とつく各種学位もあります。
例:「学士(専門職)」「修士(専門職)」など
読み方については、博士はドクター、修士はマスターと呼ぶことも多いです。この流れでいくと学士はバチェラー(bachelor)ですが、耳にすることは少ないかもしれません。
1)学士とは
最も一般的なのが「学士」という学位です。学士は大学に入学し、定められた単位や課程を経て卒業すると与えられるため、大学を卒業すれば学士と認められます。
また、大学を卒業していなくても「独立法人 大学改革支援・学位授与機構」が定める審査に合格したり「通信教育や夜間コースを採用する大学」に入学・卒業すれば、通常の大学卒業者と同等以上の学力があると認められ学士の称号が授与されます。
| 修了要件 | 1)通常の4年制大学を124単位以上で卒業 2)独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構の定める審査に合格 3)通信制や夜間コースを採用する大学に通う ※大学により異なるため必ず確認してください |
| 取得までの 必要期間 |
1)4年が一般的(医学部や薬学部は6年以上など、学部や専門により異なる) 2)3年〜12年 3)4年が一般的 ※大学により異なるため必ず確認してください |
| メリット |
・昇進に期待ができる ・国家試験を受ける際に受験資格が緩和される場合がある |
| 就職への 影響 |
・「大卒以上」の求人に応募でき、選択肢が大幅に広がる ・専門性よりポテンシャルを見られる ・仕事に取り組む姿勢や、新しいことを吸収できるかが大切 |
| 就職先の 傾向 |
・民間企業から公務員まで幅広い ・事務・販売・サービス・技術職など ・学んだ専門と違う職種に就職できることも多い |
2)修士とは
大学院修士とは、大学院の修士課程を修めることで得られる学位です。修士の中には、論文を提出して審査に合格して得られる専門的な「修士」もあるようです。
| 修了要件 | ・大学院の修士課程に2年以上在籍 ・在籍する大学院の修士課程で定める論文または課題の研究成果の審査および試験の合格 ※大学院により異なるため必ず確認してください |
| 取得までの必要期間 | ・2年が一般的(博士課程における前期2年にあたる) |
| メリット | ・高い専門性が身につく ・プレゼンテーション能力が高くなる |
| 就職への 影響 |
・専門職の門戸が広くなる ・初任給が学士よりも高くなる ・企業が求める専門性をアピールできるかが大切 ・年齢がネックになることも |
| 就職先の 傾向 |
・研究開発職やシンクタンク ・事務職や教員など |
専門職学位というものもある
「専門職大学院」で学び、修了した場合に授与されるのが「専門職学位」です。
専門職学位は学位規則で3つに区分されており、
⇒法務博士(専門職)
●教職大学院を修了した者
⇒教職修士(専門職)
●上記以外の専門職大学院を修了した者
⇒修士(専門職)
の学位が与えられます。
なお、修士(専門職)については専攻分野を加えた形で表記されます。
例:「経営学修士(専門職)」「会計修士(専門職)」
3)博士とは
「博士」とは学位の中で最上位の称号です。授与されるのは以下の2つのケースがあります。
・大学院の博士課程を修めた「課程博士」
・大学院に論文を提出し、内容が認められた「論文博士」
ちなみに、博士の通し番号には「課程博士」の場合は「甲」が、「論文博士」の場合は「乙」の文字が付されます。
| 修了要件 | ・5年以上の在学
・30単位以上の修得 ・必要な研究指導を受けた上、 当該大学院の行う博士論文の審査及び試験の合格 ※大学院により異なるため必ず確認してください |
| 取得までの必要期間 | ・5年の一貫的なタイプ ・博士課程の前期2年を修士とみなし、後期3年を博士課程に区分するタイプ |
| メリット | ・高い専門性が身につく ・プレゼンテーション能力が高くなる |
| 就職への 影響 |
・研究職や教授職への就職に有利 ・初任給が学士よりも高い |
| 就職先の 傾向 |
・大学教員が多い ・民間企業なら研究開発職 |
海外で博士や修士を取る人も
「博士」や前述の「修士」といった学位は海外の大学院でも取得することができますが、海外の大学院の博士号は非常に難しいようです。
4)短期大学士とは
「短期大学士」は短期大学を卒業した者に授与される学位であり、「短大士号」と略して表記されることもあります。
「短期大学士」の学位を持っている場合、大学への編入が可能となる場合があるため、短期大学卒業見込みの方は進路選択に活用できるかもしれません。
また、独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構の認定試験により学士への学位変更も可能であるため、何かと有利になりがちです。
| 修了要件 | 1)一般的に62単位以上(3年制の場合は93単位以上) 2)通信制や夜間コースを採用する大学に通う ※大学により異なるため必ず確認してください |
| 取得までの必要期間 | ・2〜3年が一般的(課程や修了要件による) |
| メリット | ・短期間で学位が取得できる ・4年制大学への編入により進路の幅が広がる ・独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構の定める試験で大学卒に値する学士も取得可能 |
| 就職への 影響 |
・専門的な技術や資格が取得しやすいため就職に有利 ・地域に根差した短期大学が多いため地元での進学や就職に有利 ・学士に比べると初任給が低め |
| 就職先の 傾向 |
・保育士・看護師・幼稚園教諭などの専門職 ・公務員や民間企業の事務職など |
専門士および高度専門士について
専門学校を卒業した人に与えられるのが「専門士」で、短期大学を卒業した「短期大学士」と同じ程度の証明になります。短期大学士と同じく大学への編入も可能であるため、学びの幅が広がるでしょう。
一方の「高度専門士」は4年以上の専門学校を卒業した人に与えられる称号で、日本においては大学卒業と同じ程度の証明になります。
ただし、厳密には専門士および高度専門士はあくまで称号であり学位ではありませんので、そこは考慮しなければなりません。
| 修了要件 | ■専門士 1)総授業時数が1,700 時間(62 単位)以上 2)試験等により成績評価を行い、評価に基づいて課程修了の認定を行っていること ■高度専門士 1)総授業時数が3,400 時間(124 単位)以上 2)体系的に教育課程が編成されていること 3)試験等により成績評価を行い、評価に基づいて課程修了の認定を行っていること |
| 取得までの必要期間 | 専門士:2年が一般的(学校による) 高度専門士:4年が一般的(学校による) |
| メリット | ・高度専門士でも大学院への進学が可能 ・専門士は4年制大学への編入により進路の幅が広がる |
| 就職への 影響 |
・専門的な技術や資格が取得しやすいため就職に有利 ・高度専門士は学士と同じくらいの給料がもらえる場合もある |
| 就職先の 傾向 |
・看護師・美容師・自動車整備士などの専門職 ・医療事務・クリエイター・販売職など多彩 |
各学位取得までに必要な学費目安はどのくらい?

学位の取得までにはそれぞれ長い道のりがありますが、費用は学位によってどのくらい差が出るのでしょうか?
学費は学校や学部のタイプにより様々あるだけでなく、私立なのか国立なのか公立なのか、通学か通信制かによっても異なります。
さらに、私立大学・大学院においては学部によって費用も異なるだけでなく、学生生活を実家で過ごすのかひとり暮らしするのかによっても変動します。
今回ご紹介する費用はあくまで目安でのご紹介ですので、進路選択時の参考にしてみてください。
国立大学・公立大学は学費が安いが入学金に違いがある
一般的には国立大学と公立大学は同じくらいの学費だと言われています。
| 国公立大学 | ・入学金および学費の目安:530万円前後 |
(参考:日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果(令和2年度)」
※通勤定期や学用品など、在学中の教育費全般を加味した金額
※学科など分野によっても変動有なのであくまで目安
ただし、国立大学よりも公立大学のほうが入学金がやや高いという声もあるため、あくまで目安として覚えておくと良いでしょう。
私立大学は学部により差が生じる
一方の私立大学は、国立大学や公立大学と比較すると学費が高い傾向にあります。
また、文系学部や理系学部かどうかで大きな差が生じるため一概に言えませんが、目安として以下を想定すると良いかもしれません。
| 私立大学文系 |
・入学金および学費の目安:700万円前後 |
| 私立大学理系 | ・入学金および学費の目安:860万円前後 |
| 私立医学部 | ・入学金および学費の目安:3,000万円以上 |
(参考:日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果(令和2年度)」
※通勤定期や学用品など、在学中の教育費全般を加味した金額
※学科など分野によっても変動有なのであくまで目安
私立大学で6年通う医学部・歯学部などの医療系学部は、学費も突出して高くなることに注意が必要です。
修士・博士課程も幅が広い
修士および博士課程ともなると、それぞれの課程で勉強するために入学金を支払うことがあるということを考慮しなければなりません。
修士・博士課程においても大学院それぞれで変動があるため、一概には言えませんが200万円~350万円が目安とされています。
修士・博士課程では研究がメインとなりますが、研究費は大学側が持ってくれるケースが多いようです。
▼こちらもチェック!
博士課程に進むなら500万円以上は覚悟! 大学院に通う場合っていくらぐらい必要?
短大や専門学校は2年早く社会に出るのが一般的
短期大学の場合は私立の割合が多く、平均学費目安は410万円前後とされています。
| 私立短期大学 | ・入学金および学費の目安:410万円前後 |
(参考:日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果(令和2年度)」
※通勤定期や学用品など、在学中の教育費全般を加味した金額
※学科など分野によっても変動有なのであくまで目安
短期大学や専門学校は大学よりも学費が抑えられるだけでなく、一般的に大学生よりも2年早く社会に出ることから、2年分の収入に差が出るというメリットがあります。
専門学校においては、多くの場合は2年間と短期間になるため大学よりも授業料がおおよそ半分に抑えられる可能性があります。
専門学校で専門士や高度専門士を取得する場合、平均費用目安は240万円〜460万円と幅広です。
| 専門学校 | ・入学金および学費の目安:240万円〜460万円前後 |
(参考:東京都専修学校各種学校協会「令和3年度学生・生徒納付金調査」)
※初年度の納入金に入学金以外を足し2年目以降の学費とした場合
※学科など分野によっても変動有なのであくまで目安
美術系や医療系・CG系といった特に専門性を問われる職種の場合は特殊技術ということだけでなく、通う年数も増えることもあるため幅広い費用目安となるのでしょう。
大学無償化により負担が減る可能性も
2020年4月より、条件を満たせば大学や専門学校では学費が無償化となる制度がスタートしました。
学位を取得するためには膨大な学費がかかるため、諦めてしまう人もいるかもしれません。
以下に当てはまる場合は、文部科学省の公式ホームページより案内を確認し、無償化支援にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
| 高等教育の無償化支援の対象者となる学生 |
| ・世帯収入や資産の要件を満たしていること ・学ぶ意欲がある学生であること ・その学校が支援の対象校であること |
(引用・参考:高等教育の修学支援新制度:文部科学省)
学位ごとの初任給の変化は?

学位ごとに初任給に差が出るだけでなく、年収にも違いがあります。以下に学歴別にみた初任給をまとめました。
| 学歴 | 初任給 |
| 大学院 | 25.3万円 |
| 大学卒 | 22.5万円 |
| 高専・短大卒 | 19.9万円 |
| 専門学校卒 | 20.6万円 |
(参考:厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況」)
数字はあくまで平均なので、もっと多い人もいれば少ない人もいます。それに、勤め先や職種によっては「大卒と専門卒が逆転」といった現象もあり得ます。ですから学位にこだわりすぎず、自分の夢や目標にあった進路を選択していくことがベストでしょう。
まとめ

今回は、日本における「学位」の種類をご紹介しました。
学位によって選択の幅や将来設計も大きく変わることが考えられますが、大切なのはあなたが高校卒業以降で何を学びたいかなのではないでしょうか。
また、今回ご紹介の学位が取得できる教育機関では、必ずしも高校卒業後に選択する必要はなく社会人を経験してから入学し、学位を得ることも可能です。
あなたの学びたいこと・やりたいことをじっくり考え、最適な進路を選択しましょう。