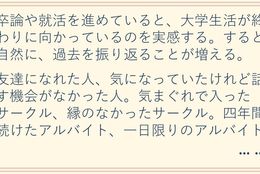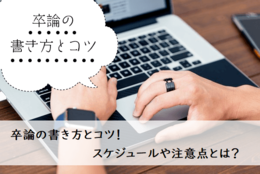卒論のアンケートの集め方・やり方は? 適したテーマ例や必要な人数、依頼文例も解説!
※記事全文を読むには会員登録(無料)が必要となります。

「卒論でアンケート調査をやろうか…でも集め方ってどうやるの?」
アンケート調査をやってみたいと思っても、一般にアンケートを取る機会などほとんどないため、集め方が分からないという方がほとんどでしょう。そこで今回は、卒論でのアンケート調査のイロハを徹底解説。そもそもアンケート調査に向いたテーマとは?必要な人数は?などよくある疑問にもお答えしていきます。
卒論でアンケート調査に向いたテーマとは?
卒論でアンケート調査に向いているのは、どのようなテーマなのでしょうか。
心理学や社会学系などの文系テーマ
アンケート調査は、社会学や心理学系のテーマでよく用いられています。なぜならアンケート調査とは「人」を対象としており、多くの人の価値観や、考え方の傾向について調べるものだからです。心理学は人の心理を扱う学問ですし、社会学も人が重要なカギを握る学問ですから、アンケート調査の出番は多くなります。
もちろん他の分野でもアンケート調査が採用されることはよくあります。例えば文学部は「ことば」を扱いますから、言葉を発する「人」にアンケート調査を行うなどです。教育学もアンケート調査が役立つケースは多いでしょう。理系の学科よりも文系の学科の方が、アンケート調査を行うケースは圧倒的に多くなります。
「一般的な傾向」を分析するテーマ
とはいえ、文系テーマだからといって全てがアンケート調査に向いているとは限りません。アンケート調査は大勢に同じ質問をして回答を得るというスタイルなので、「一般的な傾向」について分析をするテーマに向いています。
例えば卒論のテーマとして「保育士」を扱うとしましょう。
●テーマ例1「保育士の現場から〜現状と課題」
⇒たくさんの保育士の方々にアンケート調査を行うことで、新たな知見を得られる可能性が高いです。つまりアンケート調査が向いている、ということになります。
●テーマ例2「保育士不足への対策・取り組み事例」
⇒この課題に答えられる人は限られているはず。例えば積極的に対策に取り組んでいる行政の担当者や、待遇改善に取り組む保育園の人材担当などになるでしょうか。このようなテーマはアンケート調査(定量調査という)よりも、インタビュー調査(定性調査という)の方が向いています。
このように、アンケート調査はなるべく多くの人に、同じ質問を投げかけられるようなテーマに向いているのです。
卒論のアンケート調査で必要な人数は?
卒論でアンケート調査を行う際、「アンケートの回答人数はどのくらい必要なのか?」が気になる方は多いのではないでしょうか。
結論からいうと、アンケート調査で必要な人数は「最低100人程度から」が目安となります。
アンケート調査にあたっては、回答する人数は多ければ多いほど、データの精度は高くなります。ですが人数が多すぎると、手間やコストがかかりすぎて困ってしまうことに。一方で、人数が少なければ手間やコストの負担は減りますが、データの実態との誤差が大きくなってしまいます。
より精度の高いアンケート結果を得るためには、プロのリサーチ会社に依頼するといった方法もあります。ですがお金もかかることなので、卒論に取り組むみなさんにとってはハードルが高いと感じることもあるでしょう。
そこで、データの「誤差の許容範囲」と「自分たちの作業負担」との兼ね合いで、現実的な落としどころを考えていくことになります。
ここでは大まかな目安の提示となりますが、
| アンケート回答数 | 最大誤差 |
| 100サンプル | およそ10%程度 |
| 200サンプル | およそ7%程度 |
| 400サンプル | およそ5%程度 |
とされています。誤差が10%というとやや大きい印象もありますが、卒論でのアンケート調査という観点では最低100サンプル程度から、というのが現実的と考えられます。あとは指導教員にアドバイスをもらいながら決めてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、当然のことですが卒論アンケートの水増しは許されません。卒論は学生生活の集大成ですから、不正行為のないよう真面目に取り組むようにしましょう。
卒論のアンケートの集め方【依頼文例あり】
ここからは、具体的なアンケートの集め方について解説していきます。
1.目的を明確にし、仮説を立てる
まず、卒論テーマに対して先行研究を調べるなど、自分でできるところはしっかり勉強しておくというのが大前提です。その上で、アンケート調査を行う「目的」を明確にします。目的とは「〜の部分について詳しく探求するため」といったものです。
さらに、目的に加えて「仮説」を立てることが大切。つまり漠然と「〜を知りたい」というだけでなく、仮の答えを考えてみるということです。仮説を立てることで、より効果的な質問を設定できるようになります。
例えば先ほどの保育士の例でいうと、
保育士の現場の実態について探求するため
<仮説>
●楽しいところはどこなのか?
⇒子どもが笑ってくれる・子どもとのふれ合い・成長に立ち会える
●大変なところはどこなのか?
⇒朝が早すぎる・保護者対応・お給料面など?
このように仮説を立てていきます。そして、実際にアンケート調査を行うことで仮説がどうだったのか検証していくわけです。仮説を立てた際には、既に調査済みで公開されているデータや先行研究がないかも確認してからアンケートを取ると良いでしょう。
2.対象者を決める
目的を明確にすれば、おのずと対象者は絞られてくるはずです。先の保育士の例でいえば、全国あるいは特定の地域の「保育士」が対象となります。各保育園に一旦連絡をして了承をもらってから、そこで働く保育士さんに書いてもらうか、QRコード付きの依頼文を郵送するなどの方法が考えられます。
卒論の場合、自分が所属する大学の学生や学部生などを対象とするケースも多いようです。「大学生」というのが対象者として適切ならば、自分の周りの学生を対象にすればとても身近で取り組みやすいですよね。指導教員によっては、授業のタイミングを利用して受講生に声かけができるケースもあります。
・大学キャンパス内で声をかける
・教員の了承のもと、授業やゼミで依頼する
・街頭アンケート
・企業や団体へ協力を依頼する
(例:高齢者施設や公共施設、企業など)
・プロのリサーチ会社に依頼する【有料】
街頭アンケートは大学名の入ったウインドブレーカーを着たり、名札を首からぶら下げるなど、怪しまれないような工夫が必要です。それでもなかなか回答してもらえず凹んでしまうかもしれませんが、場所を変えるなどして根気強く取り組みましょう。
企業や団体への協力依頼では、まず広報や総合受付などを通すことが一般的。断られてしまうことはある意味当たり前ですので、丁寧にお願いしながら許可をもらえるところを探してみましょう。許可をもらえたら、具体的な調査方法については相談の上決めていくことになります。
ツイッターなどのSNSで拡散する方法は?
TwitterやFacebookなどのSNSで、フォロワーや友達にアンケートを依頼すると、趣味や好みが偏ってしまう懸念があります。
あるいは、これらのSNSは拡散力があるのが強みですが、どんどん拡散していくと「一体誰が答えているのか」が分かりづらくなってしまいます。SNSは拡散する力がある一方で匿名性が高いため、街頭アンケートなどと比べても不正行為が起こりやすくなってしまうのです(多重回答など)。
卒論のアンケート調査では「〇〇を対象とする」と対象者を明記することになりますが、SNSではここが曖昧になりやすいため推奨しない、という意見が今のところ主流となっています。
3.調査方法を決める
次に、調査方法を決めます。これは先の「対象者」が誰なのかによって、一番適した方法を考えていかなければなりません。
・対面でその場でタブレット入力してもらう
・対面で案内とQRコードを渡し、好きな時にスマホで回答してもらう
・郵送で依頼し、返送してもらうorスマホやPCで回答してもらう
・メールで依頼し、スマホやPCで回答してもらう
このように方法はさまざま。学内アンケートの場合はその場で書いてもらうのが一番手っ取り早いかもしれません。街頭アンケートも、紙で書いてもらうか、あるいはタブレットに入力してもらう方法もおすすめ。
そして、アンケート調査票のスタイルとしては大きく次の2つに分かれます。
●webで行うアンケート
紙ベースでのアンケートは、その場で一目見て分かり、どの年代にもお願いしやすいのがメリット。WordやExcelを使って作成するのが一般的です。
webで行うアンケートの方は、どちらかと言えば若い年代を対象とする場合におすすめ。調査を実施する側にとっては集計をしやすいのが大きなメリットとなります。ここでは無料で使える便利なアンケートフォームとして「Googleフォーム」をおすすめします。
Googleフォームとは?

Googleフォームとは、Googleが提供している無料フォーム作成ツールです。
Googleアカウントを持っていれば誰でも気軽に使えるため、アンケートのほか出欠確認、キャンペーンへの申し込みフォームなど、幅広く利用されています。卒論アンケートにも使われているケースがとても多く見受けられます。
作成方法はとても簡単!初めてでも直感的に作成できるようになっているので、まず練習がてら1つ作ってみても良いかもしれません。Googleフォームなら分析機能まで付いてくるので、紙ベースのアンケートより格段に集計が楽になるのも魅力です。
4.指導教員に相談する
ここまでの内容について検討し、調査の概要がある程度固まったところで、いったん指導教員に相談するようにします。卒論研究や、卒論に係るアンケート調査はゼミ研究生として行うものですから、指導教員が内容を把握していないのは後々トラブルになることがあります。
必ず教員に相談し、アドバイスをもらい、内容的にOKをもらった上で対外的なアクションを起こすようにしましょう。
5.アンケート依頼文を作る【例文紹介】
指導教員からのOKが出たら、実際のアンケート作成に入っていきましょう。アンケートは「依頼文」と「調査票(アンケート本文)」で構成されます。特に依頼文は1から作るとなると体裁が分からず困ってしまうケースが多いようです。
そこで今回は、アンケート依頼文の例文をご紹介。依頼する際はメールで送付することも多いですが、ここでは最もフォーマルな文書を想定してご紹介します。