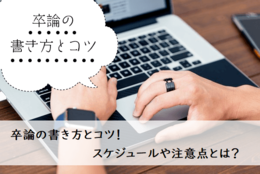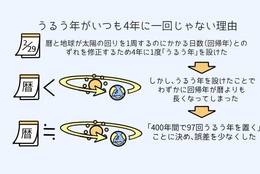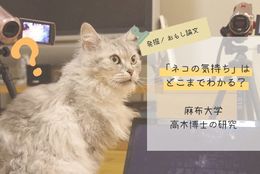卒論の謝辞の書き方とは? 例文つきで解説
※記事全文を読むには会員登録(無料)が必要となります。
卒論や修論の謝辞の書き方について解説します。
「卒業論文(卒論)」や「修士論文(修論)」の最後には「謝辞」がつきもの。ここまで指導をしてくださった教官、協力いただけた人・企業・組織にお礼を述べるところです。
ですがいざ書くとなると、何をどのように書いたら良いのか迷ってしまいますよね。今回は謝辞の例文もご紹介します。

▼目次
1.謝辞って何?
2.卒論・修論の謝辞の書き方 ポイントは?
3.謝辞の例文
4.謝辞は「書かなくていい説」もある
5.まとめ
▼こちらもチェック!
卒論執筆にかけた時間はどれぐらい? 今年卒業する大学生の卒論事情!
謝辞って何?
謝辞とはそもそも何なのでしょうか。ここでは卒論や修論における謝辞について解説します。
謝辞の主旨は、「お礼を述べる」
卒論や修論における謝辞とは、次のような方々に対して感謝の意を述べるためのものです。
1.卒論・修論の指導教官や副指導教官
2.指導教官以外でアドバイス・助言をいただいた先生
3.卒論・修論の研究に協力していただいた人・組織・企業など
論文が完成するまでの間には、指導教官やゼミのメンバー、その他多くの方々の協力があったことでしょう。その方々あるいは団体などにお礼を述べる場が「謝辞」というわけです。
謝辞は論文の最後に入れる
関係者にお礼を述べる「謝辞」は、論文の最後に持ってくるのが基本です。ただしここで注意したいのは、一口に最後といっても「一番最後」なのか、「結論の直後(参考文献の前)」なのか、あるいは「どちらでもOK」なのか大学や研究室によって異なるということ。所属するゼミや研究室で、論文フォーマットについて取り決めたレジュメなどがあれば、必ず確認するようにしましょう。
一例として、論文の全体構成から謝辞の位置を見てみましょう。
| タイトル | |
| 要旨 | 論文の全体をまとめたもの |
| 目次 | |
| 第1章 序論 | 背景や問題提起。「はじめに」など |
| 第2章 本論 | |
| 第○章 | 本論を何章かにわたって記述 |
| 第○章 | |
| 第○章 結論 | 結論をまとめる。「おわりに」など |
| 謝辞 | ←ココ! |
| 参考文献 | ←謝辞と参考文献が逆になることも |
| 付録 |
卒論・修論の謝辞の書き方 ポイントは?

では本題の、謝辞の書き方のポイントについて解説します。ちなみに卒論の謝辞と修論の謝辞との違いですが、「感謝の意を表明する」という意味合いは全く同じ。以下で解説するポイントについても卒論と修論で特に違いはありません。修論を書く方は一度卒論でも謝辞を書いているはずですので、改めておさらいの意味でご覧になってみて下さい。
簡潔に記載する
1つ目のポイントは、長々と書かずに簡潔に記載すること。ただし大勢の人をまとめて簡潔にお礼を述べるのではなく、個別に名前を挙げて記載します。そこで煩雑にならぬよう、箇条書きスタイルにするのがオススメ。
具体的には個別の名前を挙げて(複数名でもOK)、「〜で感謝申し上げます。」「〜でお礼を申し上げます。」などと記載し、一文程度でまとめます。ここで一行あけて、また同じように次の人の名前を挙げて感謝を伝えます。このように行をあけて箇条書きスタイルにすることで、人数が多くなっても見やすさをキープすることができます。
一文一文も長くなりすぎないように心がけます。お世話になったエピソードもそれぞれ1点程度に抑えて、あくまでも簡潔に。謝辞の全体量の目安としてはA4用紙1枚か、多くても2枚で収まるようにまとめましょう。
各個人名の書き方に注意する
各個人を記載する際は、失礼にならないように注意しなければなりません。例えばゼミの先輩を「〇〇君」などとうっかり書いてしまっては大変!個人名に関して注意したいポイントは以下のとおりです。
・感謝を述べる相手は指導教官→その他の先生→その他の順に記載
・肩書、地位の上位の人から先に記載する
・原則として個人名はフルネームを使用する
・教官、先生方の記載は「氏名+肩書(職名)」とする
・先輩を記載する場合には「○○先輩」「○○さん」「○○氏」
・同期を記載する場合には「○○さん」「○○君」「○○氏」
・後輩を記載する場合には「○○さん」「○○君」「○○氏」
・ゼミ、研究室を記載する場合には「正式名称+のみなさん(みなさま)」
・企業を記載する場合には「正式名称(+正式部署名)」
(「株式会社」などを省略しない)
それぞれの人がどのように卒論の研究に関わっていただいたのかを簡潔に付け加えながら謝辞をまとめましょう。
家族のことは書くべき?
家族は論文自体への直接的な関係性は薄いと思われるので、「書くべき」というわけではありません。ですが論文の研究に打ち込むことができたのは家族の応援があってこそ。そこでもし書くのであれば、謝辞の最後に個人名ではなく「〜支えてくれた家族に感謝いたします。」などと家族全体を指しながら記載すると良いでしょう。
恋人を書いてもいい?
「恋人と切磋琢磨しながら論文を仕上げた」という人は大切なパートナーの果たした役割について記述したいかもしれません。ですが恋人とは非常にプライベートな関係性ですので、謝辞への記載はおすすめしません。後々のことを考えても逆に不都合になる(!)可能性もありますので、謝辞に書くのは控えた方が賢明です。恋人へは直接口頭で感謝の気持ちを伝えましょう。