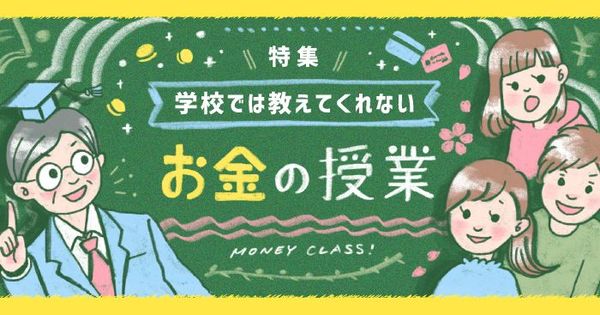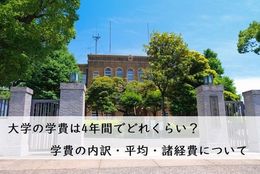20代の今から考えたい『年金』の仕組みと支払いについて |学校では教えてくれない「お金の授業」
20歳になると「国民年金への加入」が始まりますが、年金とはどのような仕組みなのか、理解しきれていない方もいるでしょう。
また、大学生の中には「保険料の支払いができない」という方もいると思いますが、そのままにしておくと将来受け取れる金額も少なくなりますので、きちんと手続きをとる必要があります。
ここでは、年金の仕組みや、支払いができない場合の手続き方法などについて、詳しくご紹介しています。
年金の仕組みとは?
日本の年金制度は、以下のように「3階建て」の構造をとっています。
|
|
年金の種類 |
主な加入者 |
| 1階 |
国民年金(基礎年金) |
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方 |
| 2階 |
厚生年金 |
会社員、公務員など |
| 3階 |
企業年金、個人型確定拠出年金(iDeCo)など |
・企業年金制度のある企業に勤めている方 ・個人型確定拠出年金などに任意加入している方 |
1階部分と2階部分を合わせて「公的年金」、3階部分を「私的年金」といいます。
また、公的年金に加入している方(被保険者)は、職業やライフスタイルによって下の3つに分かれています。
| 被保険者の種類 |
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
第3号被保険者 |
| 職業 |
自営業、学生、無職の方とその配偶者など |
会社員、公務員など |
第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦(夫)) |
| 加入している年金 |
国民年金 |
国民年金と厚生年金 |
国民年金 |
大学生は20歳になると第1号被保険者として国民年金に加入し、その後企業に就職した際には、第2号被保険者として厚生年金に加入することになります。
公的年金
公的年金には、国民年金と厚生年金のふたつがありますので、それぞれの特徴を確認しておきましょう。
国民年金
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の国民すべてが加入する制度で、ほかの年金の土台となっているため「基礎年金」といわれることもあります。 自営業や個人事業主、フリーランス、学生、無職及びその配偶者などは国民年金のみに加入します。
また、第3被保険者(専業主婦(夫))は、配偶者が厚生年金に加入していれば国民年金保険料を納付したことになります。
厚生年金
会社員や公務員などが加入する保険で、国民年金に上乗せ給付される制度です。 厚生年金を納付すれば、国民年金も納付したことになり、年金を受け取る際にも国民年金と厚生年金の両方が支給されます。 厚生年金保険料は収入に応じて異なり、保険料は被保険者と会社が半分ずつ負担します(労使折半といいます)。
私的年金
私的年金は、勤務先で企業年金制度がある場合に加入できるものと、個人型確定拠出年金(iDeCo)のように個人で任意に加入するものがあります。 企業年金には、「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「企業型確定拠出年金」があります。 一方、個人で加入できるものには、「個人型確定拠出年金 (iDeCo)」や「国民年金基金」があります。
国民年金基金は、年金受給額を増やすために第1号被保険者が任意加入できるもので、個人型確定拠出年金 (iDeCo)は2017年から加入対象者の範囲が広くなり、自営業、会社員、公務員、専業主婦(夫)などほとんどの方が加入できます。
年金の支払いはいつから?
保険料の支払い開始のタイミングや、納付金額について確認していきましょう。 国民年金と厚生年金とでは支払開始日や金額が異なりますのでそれぞれご紹介します。
国民年金は「満20歳の誕生月」から支払い開始
国民年金保険料の支払いは、「誕生日の前日が含まれる月」からの納入となります。 そのため、1日生まれの方は注意が必要です。たとえば、5月2日生まれの方は保険料の納付は5月からですが、5月1日生まれの方は誕生日の前日が4月30日なので4月からの納入になります。
保険料は16,520円/月
令和5年度の国民年金保険料は、月額16,520円です。納付方法は、金融機関やコンビニ窓口のほか、口座振替やクレジットカードでも支払うことができます。
厚生年金は就職時から支払い開始
厚生年金は国民年金のように「何歳から支払い開始」と決まっているわけではありません。また、就職した企業が「厚生年金の適用事業所」であるかどうかで異なります。 「厚生年金の適用事業所」について簡単にご説明すると、すべての法人事業所や5人以上の従業員がいる個人事業所は厚生年金に強制加入となり、それ以外の企業も任意加入することができます。 勤務先が厚生年金の適用事業所であれば、就職時に加入することになります。 ただし、パートやアルバイトなどで働く場合は、労働時間や日数によって加入できないこともあります。
保険料は収入によって異なる
厚生年金保険料は収入によって異なります。たとえば標準報酬月額(※)が24万円の場合、保険料は43,920円ですが、労使折半なので自己負担は半額の21,960円になります。保険料は給料から天引きされますので、自分で納める必要はありません。
※標準報酬月額:会社から支給される基本給や役職手当、通勤手当、残業手当などの諸手当を加えた1か月の総支給額
年金の支払いの猶予期間や免除について
国民年金には20歳になると加入することになりますが、「まだ学生だし保険料を払う余裕がないよ!」という方もいると思います。そのような場合には、「学生納付特例制度」を利用しましょう。
学生納付特例制度とは
学生納付特例制度は、在学中の保険料の納付が猶予される制度で、本人所得が一定額以下の学生が対象です。 所得は、「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下であることが条件です(家族の所得は対象外)。
申請先
申込みは、次のいずれかで申請してください。
・住民登録してある市区町村役場の国民年金担当窓口(郵送も可)
・近くの年金事務所
・在学している学校の担当窓口
(学生納付特例の代行事務の許認可を受けている場合)
必要書類
申請用紙は国民年金機構の公式サイトからダウンロードできます。また、「ねんきんネット」の画面上でも学生納付特例申請書を作成できますが、ID登録が必要です。また添付書類として以下の書類が必要です。
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・学生であることまたは学生であったことを証明する書類
(在学証明書(原本)、学生証の写しなど)
ちなみに、退職(失業)した場合に申請するときは、退職(失業)したことを証明できる書類(雇用保険受給者証、被保険者離職票など)が必要です。
【注意】「学生納付特例制度」を利用しても将来の年金額は減る
「学生納付特例制度」を利用して保険料の納付を猶予してもらうと、実際には保険料を納入していないため、将来もらう年金額は減ってしまいます。
猶予はあくまでも猶予であり免除ではないので、後から納付(追納といいます)しなくては満額もらうことができないのです。
卒業後10年以内なら追納できる
納入を猶予してもらった分は、就職して収入が得られるようになったら忘れずに追納してください。卒業後10年以内であればさかのぼって納めることができ、将来の年金も満額もらえるようになります。
もし自分の納付状況がわからないときは、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認してみましょう。
いつ年金がもらえるの?
ここまで年金を納めることについてご紹介してきましたが、もらうことについても知っておきたいですよね。
国民年金と厚生年金は、それぞれいつから受け取れるのか確認していきましょう。
国民年金は原則65歳で「繰上げ」「繰下げ」もできる
国民年金は、保険料納付済期間と免除期間などを合算した「受給資格期間」が10年以上あれば65歳から支給開始され、受給者本人が亡くなるまでもらえます。年金額は、満額の場合で月額66,250円(令和5年)、加入月数が40年(480月)に満たない場合は減額されます。
支給開始年齢は原則65歳からですが、60歳から65歳までにもらえる「繰上げ受給」と、66歳以降からもらう「繰下げ受給」を選ぶこともできます。繰上げ受給をすると繰り上げた月数に応じて最大30%減額されてしまいます。
一方、繰下げ受給を選ぶと最大42%も増額できます。この減額と増額は一生変わりませんので、選択する際には慎重に検討する必要があります。
現在の大学生が厚生年金をもらうのは65歳から
厚生年金がもらえる年齢は、昭和36年4月1日以前生まれの男性と昭和41年4月1日以前生まれの女性は支給開始年齢が異なりますが、それ以降の方は65歳からの支給となり本人が亡くなるまで受給できます。 年金額は、厚生年金に加入していた期間と年収によって異なります。 なお、冒頭でもご紹介しましたが、厚生年金は国民年金に上乗せ支給されるものなので、実際にもらえるのは国民年金+厚生年金となります。 厚生年金も66歳以降に繰下げ受給することができ、最大5年間で42%増減されます。
今話題の年金の問題を解説
年金についてはさまざまな問題が取りざたされていますが、年金を支払う立場になったからこそ、問題点についても理解しておく必要があります。
少子高齢化による現役世代の負担増
日本の公的年金制度は「賦課方式」といい、現役世代が納める保険料で高齢者の年金原資を確保しています。
そのため、現役世代や将来年金制度を支えるべき子供の数が減少すると、「年金制度の崩壊につながるのではないか」と危惧されています。
世代間格差をなくすための対策
現在の高齢者「納め得」と現役世代「納め損」の格差をなくすために、「マクロ経済スライド」制度が導入されました。
年金受給者の人口や社会情勢に応じて支給する年金額を減らしていくという内容です。 しかし、世代間格差を完全になくすことは難しいのが現状です。
公的年金以外の対策が必要
公的年金だけでは不安という方は、私的年金に加入し年金額を増やしたり、投資信託などで資産を殖やしたりすることもおすすめです。 ただし、投資信託にはリスクがつきものなので、正しい知識を身に着けることから始めましょう。
まとめ
大学生でも20歳になると国民年金に加入し、毎月保険料を納付することになります。 もし納付が難しい場合は「学生納付特例制度」の申請をしましょう。 ただし、猶予のままだと将来もらえる年金額が減額されてしまうので、10年以内に追納することを忘れないでくださいね。
文:金子 賢司
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。 以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、 年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。 <保有資格>CFP、住宅ローンアドバイザー、生命保険協会認定FP、損保プランナー 公式HP
制作:Media Beats
編集:マイナビ学生の窓口編集部
他の“学校では教えてくれない「お金の授業」”もチェック!