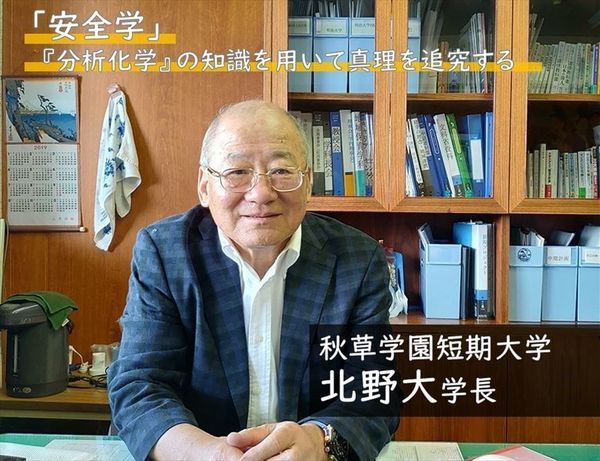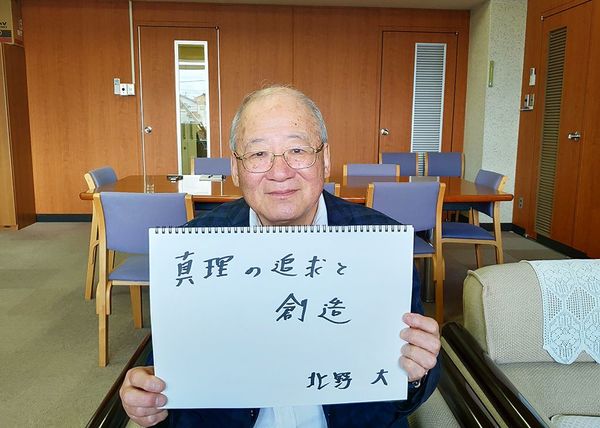「大学」で学ぶ意味ってなんですか? タレントとしても活躍する工学博士の北野先生に話を聞いてみた #学問の面白さ
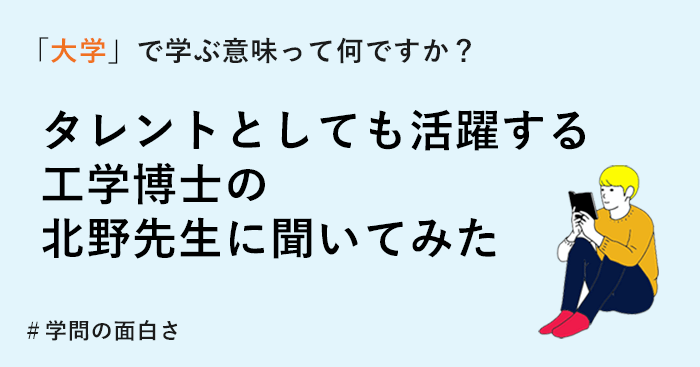
"Education is a progressive discovery of our own ignorance." – Will Durant (勉強とは自分の無知を徐々に発見していくことである。)
あまり勉強に熱が入らない大学生も多いのではないだろうか。もしそうなら、かなりもったいない。この連載では、勉強する意味を見出せていない諸君に向けて、文系・理系の様々な学問を探求する「知的好奇人」達からのメッセージをお届けする。ちょっとした好奇心が、諸君の人生をさらに豊かにしてくれることを祈って
今回の"知的好奇人"は?
今回お話を伺ったのは、秋草学園短期大学の学長・北野大先生です。工学博士であり、タレントとしても活動されている北野先生に、現在の研究内容や、理系の学問の魅力を聞いてみました。
最初は理系志望ではなかった
――先生は大学進学の際に、明治大学の工学部工業化学科に進まれて分析化学を学ばれましたが、理系の分野に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか?
工学部に進んだのは親の意向なんです。僕は英語の先生になるために、文学部に行きたかったのですが、母親が「手に職を付けてほしい」と強く希望していたので、工学部に進みました。
うちは私だけでなく、兄と弟も機械工学の道に進んでいますよ。
――最初は文系の道を希望されていたのですね。入学して理系の学問に本格的に触れてみて、どのような点が面白いと思いましたか?
「理系って面白いな」と思ったのは、大学院に入って研究をするようになってからですね。仮説を立てて、実験して、その成果が論文としてまとまると達成感が得られましたし、それが面白かったです。
私は研究は忍耐だと思っています。山登りみたいなもので、登っているときはつらいけど、登り切るとすごくうれしいですよね。その気持ちがまた次につながり、いろいろな研究をしようという気持ちになるのですよ。
人や社会の役に立つ安全学
――先生は分析化学や環境科学がご専門ですが、10年ほど前から「安全学」を専門に研究されていますね。この安全学とはどんな学問なのでしょうか?
安全学というのは、日用品、機械、食品、化学物質などが安全に使えるかどうかを分析・研究するものです。
私の場合、これまで研究してきた分析化学の知識を用いて、例えば洗剤に使われる薬品が人体や環境にどういった影響を与えるのかを事前に研究し、より安全に使う方法などを考えています。
――使ってから起こったことを検証するのではなく、事故を未然に防ぐための学問なのですね。
そのとおりです。私は化学面から研究していますが、他にも工学面での研究者もいますし、獣医さんもいます。さまざまな面から安全というものにアプローチしているのです。
――安全学の魅力はどのような点だと思われますか?
安全学には「機械は必ず故障する」「人間は必ず過ちを犯す」という2つの原則があります。
昔、渋谷の温泉施設で爆発事故がありましたが、これは換気扇のトラブルが原因の一つでした。この場合、換気扇が故障した場合にどうするかを考え、設備に生かすのが安全学ですが、この「どうするか」を創意工夫して考えることが難しい点であり、面白い点でもあります。
例えば、現在使われている水道の蛇口は、取っ手を上げると水が出ますよね。実は昔は下げると水が出るタイプでしたが、地震のときに蛇口の上に物が落ちて水が出っぱなしになるということがありました。そうしたトラブルを防ぐために現在のようなタイプになったのです。
これも安全学の一例ですね。
――上げると水が出る仕組みにはそうした事情があったのですね!
「安全」でないと安心して生活できないですからね。
また、安全学の周知活動も力を入れていることです。他にも、後の研究者のために、現在用いられている化学物質評価の試験法の成り立ちや、歴史をまとめる作業も並行して行っていることです。
――先生が学長を務める秋草学園短期大学は、卒業生の多くが幼児教育に関わりますから安全学は重要ですね。
そうですね。子供たちを安心して育てるためにも安全学を学んでほしいと思っています。また、学園祭で「環境コミュニケーション」をテーマにしたイベントを開催するなど、さまざまな活動を行っていますよ。
真理の追究と創造が理系の面白さ
――先生は「理系」という学問のどんな点が魅力だと思われますか?
「真理を追究すること」でしょうか。遺伝子研究はその最たるもので、「4つの塩基でできている」というのは最大の発見でしょう。自然というのは極めてシンプルにできているんだと実感しましたし、あらためて研究することの面白さを感じました。
他にも「創造する喜び」を得られることも魅力ですね。それが世の中の役に立つのも、理系の分野の魅力ではないでしょうか。
新しいことを知る喜びを感じよう
――昨今、大学で学ぶことに意味を見いだせない学生が増えています。先生は、大学で学ぶことの意味は何だと思われますか?
大学は「リベラルアーツ(一般教養)」が学べるのが最大の特徴だと思っています。もちろん、倫理や哲学を学んでも実生活にすぐに役立つものではないですけれども、そこで得た知識や倫理観は、科学が進歩するこれからの社会においても、必ずや重要になると思っています。
今は無駄だと思うかもしれませんが、こうした一般教養は社会に出てからでは、学ぶ時間がなかなかありませんから、ぜひ大学のうちに身に付けておくべきです。
――大学生活はいろんなことを学び、チャレンジする時間がありますから、有効に使うべきですね。
「How to」系の本は社会に出てからも読めますから、学生時代は文学書なり、研究書なり、時間がしっかり取れないと読めないものを読むといいですね。そこで得た知識は将来どこかで役立ちますよ。
また知識が豊富であれば、それだけ人生も豊かになります。例えば奈良県に出掛けて法隆寺を見るとしても、知識があれば伽藍(がらん)の配置や壁画などを興味深く見ることができますが、知識がないとどういうものか分からず見過ごしてしまうかもしれません。
どんなことも知識があれば興味深く観察できるはずですし、ぜひ学生たちには、役に立つか立たないかで考えるのではなく、「新しいことを知る喜び」を感じて学んでほしいですね。
――ありがとうございました!
北野先生が考える工学などの理系分野の魅力は、「真理の追究」と「創造する喜び」とのことです。最初は志望する分野ではなかったものの、次第に実験や成果が出ることに面白さを感じ、いつしか人生の軸となっていったようです。
たとえ興味がない分野であったとしても、新しい知識を得る点に面白さや喜びを見いだせば、気が付けばのめり込むようになるかもしれません。大学の授業も同じで、「意味がない」と一蹴するのではなく、ここでしか得られない知識だと考え、学んでみてはどうでしょうか。その知識が思わぬところで役立つでしょう。
(中田ボンベ@dcp)
【北野大先生プロフィール】
1942年生まれ。明治大学工学部卒業後、1972年に東京都立大学大学院工学研究科工業化学専攻博士課程修了。分析化学で博士号を取得。財団法人化学品検査協会(現:化学物質評価研究機構)・企画管理部長から淑徳大学国際コミュニケーション学部教授、明治大学理工学部応用化学科教授、淑徳大学人文学部教授を経て、2017年4月より秋草学園短期大学学長、淑徳大学名誉教授に就任。
⇒秋草学園短期大学HP
https://www.akikusa.ac.jp/akit...