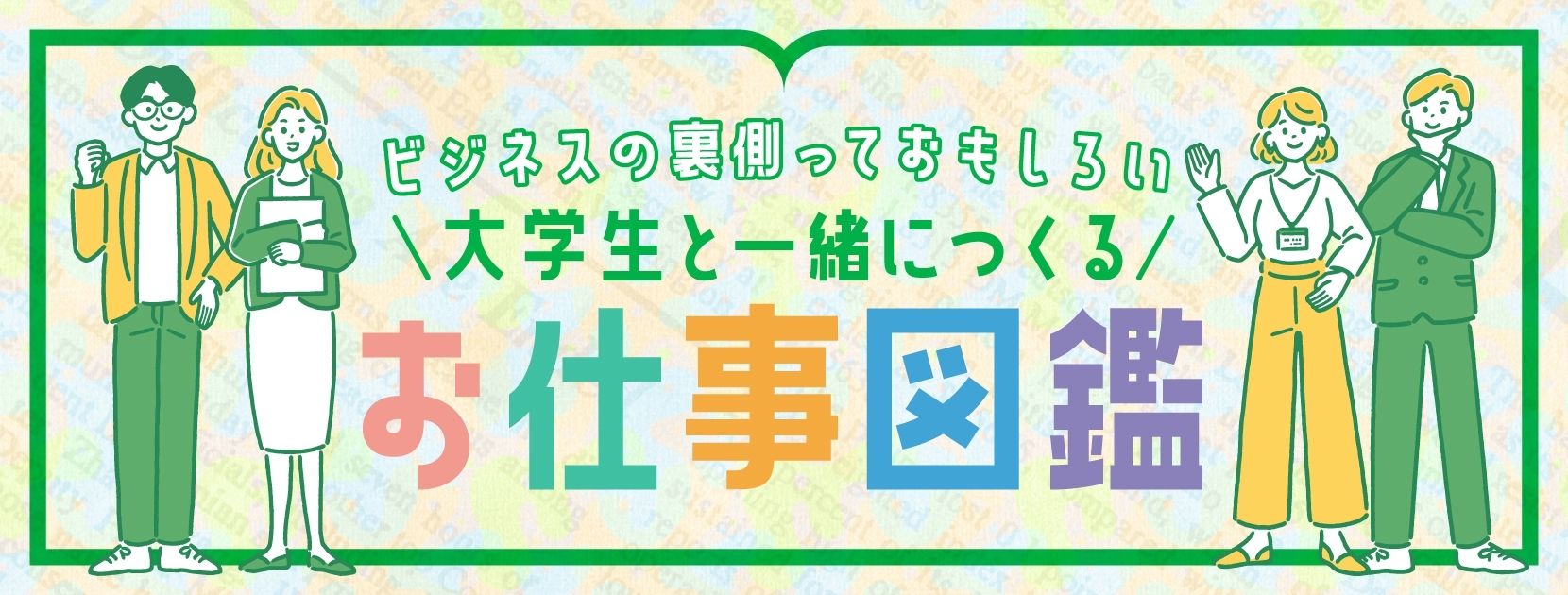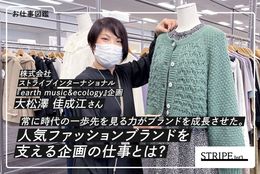普通の大学生だった私が“食べられるバラ”で起業!代表取締役社長・田中綾華さんの、好きを仕事にする生き方 【お仕事図鑑】

「食べられるバラ」の栽培・商品開発を行い、バラの魅力を世界へ発信しているROSE LABO株式会社 代表取締役社長の田中綾華さん。
ごく普通の大学生だった田中さんは、20歳のときに大学を中退しバラ農家への道を歩み始めました。勉強もあまり得意ではなく、将来についても「やりたいことが見つかっていなかった」と話す彼女は、なぜ起業することにしたのか。
起業のきっかけから、ROSE LABOが行う6次産業について、学生起業を目指す方へのアドバイスなど、お話を伺いました!
▼INDEX
1.大学を中退してバラ農家の道へ。起業しようと思ったきっかけ
2.食用バラ以外にジャムや化粧品を開発。「6次産業の面白さは“魔法使い”であること」
3.「新入社員は“応援される人間”になろう」求める人材とは?
4.アイデアの見つけ方、メリット・デメリット……起業を目指している学生へアドバイス
大学を中退してバラ農家の道へ。起業しようと思ったきっかけ
――起業するきっかけとなった背景を教えてください。
大学入学後、ゼミで将来の夢をキラキラと話す同級生を見て、劣等感を抱いたことがきっかけでした。
それまでの私は、ファッションやコスメが好きな普通の大学生。勉強もあまり得意ではなく、将来についても深く考えていませんでした。しかし大学では夢や目標を持った人たちが地方から集まっており、私と価値観が全く違ったんです。
「同じ年数を生きているのに、なぜこんなにも違うのだろう?」と人生で初めて劣等感を抱きました。そこで、自分の人生を一度見つめ直そうと決意しました。
自分と向き合う中で考えたのが「私の幸せってなんだっけ?」ということ。半年ほど時間をかけてノートに気持ちを書き、整理しているうちに見えてきたのが「私にとっての幸せは『健康寿命の間を楽しく生きること』」でした。
健康寿命を1週間、1日と因数分解していくと、圧倒的に仕事をする時間が多かったんですね。「仕事が楽しくないと、私は健康寿命を楽しく生きられない」と思い、好きなことを仕事にしようと決意しました。
――バラに着目したきっかけを教えてください。
もともと家族全員バラが大好きで、いつも身近な存在でした。母から「食べられるバラ」の存在を聞き、より興味を持ったことと、バラは見た目が美しいだけでなく美容成分が多く含まれており、可能性が無限にあることを知りました。バラをたくさんの人に広められる仕事をしようと思い、バラ農家の道を歩み始めました。

――なぜ大学を中退してバラ農家の道を歩もうと思ったのでしょうか?
「1秒でも若いうちにプロになりたい」と思ったからです。
農業は技術や経験が非常に重要な職種です。
私は家族や親戚に農家はおらず、都内で生まれ育ったため、農業とは遠い世界で生きてきました。そのため、幼い頃から農業が身近にある人たちと比べて、遅れをとっていると感じていたんです。
大学では国際政治学を学んでいましたが、卒業まで勉強していても農業に関する技術や経験が身につきません。日々の積み重ねが必要だからこそ、思いきって大学を中退しました。
両親に伝えたときは反対されましたね(笑)ただ、ここまで自己主張することが少なかったため、「将来こうなりたい」「こんな人生を歩みたい」と丁寧に思いを伝えたところ納得してくれました。起業後は母が脱サラをして3年間事業を手伝ってくれたり、今でも両親が週末に栽培の手伝いに来てくれたりと、とても感謝しています。

食用バラ以外にジャムや化粧品を開発。「6次産業の面白さは“魔法使い”であること」
――大学中退後は、大阪のバラ農家でおよそ2年間修業をした田中さん。バラ栽培の技術を学び、無我夢中で仕事をしていたと言います。 その後、埼玉県深谷市に移り2015年にROSE LABO株式会社を創業しました。2年で大阪の農家をやめた理由を教えてください。
バラは見た目が美しいからこそ、「SNSで発信してはどうか?」と師匠に相談したところ、「農家には必要ないのでは?」と言われ、価値観のズレを感じたためです。世の中に情報発信することはこれからの時代に必須だと思っていたからこそ、自分で可能性を閉じてしまうのはとてももったいないと思いました。
バラの可能性を広げて、多くの人にバラの素晴らしさを届けたかったからこそ「自分でやろう」と退職をしました。
――起業後、大変だったことを教えてください。
栽培していた3000本のバラを枯らしてしまったことです。売るものがない、お金がない状況は苦しかったです。
失敗した原因は、大阪時代に行っていた栽培方法を、そのまま深谷で実践してしまったこと。地域によって気温や湿度が違うため、バラに合った最適な環境を考えられていなかったことが一番の原因でした。気候に合わせた栽培方法に変え、農業に対する知識や技術を学ぼうと週末に通える農業の学校で一から勉強した結果、無事に咲かせることができました!
食用バラは農薬を使わないため、病気になりやすいです。天候によって開花が大きく左右されるので、細かな調整が必要になります。パソコン上でシュミレーションをしていても、思い通りにいかないことばかりです。
ただ、栽培では大変なことが多いですが、手間をかけて育てたバラが綺麗に咲いたときは、達成感がありますね。

――食用バラの栽培をはじめ、現在ではバラを使ったジャムや紅茶、化粧品の開発など多岐にわたる事業を展開しています。この仕事の面白さについて教えてください。
この仕事は「魔法使い」だと思っています。弊社は1次産業である生産から、加工(2次産業)、販売(3次産業)まで全て一貫する“6次産業”を行っています。
1次産業から行っているからこそ、自分たちで食用バラを作るだけではなく、バラ風呂用、スイーツ用、ジャム、化粧品……とさまざまなものに変化させられる仕事です。アイデア次第でなんでも生み出せる点が、仕事の面白さであり、やりがいだと思います。
――6次産業ならではの商品の特長を教えてください。
高品質のものを使い続けやすい価格帯で提供し続けられるところです。例えば一般的な化粧水は、80%が水で残りの20%に美容成分や防腐剤が含まれます。
ですが弊社では、バラから抽出した美容成分たっぷりのローズウォーターを100%に近い割合で配合しています。農業から一貫して行い中間マージンがかからないからこそ、実現できている品質の良さは6次産業ならではですね。

「新入社員は“応援される人間”になろう」求める人材とは?
――入社後、どのような人が活躍できると思いますか?
まずは好奇心が旺盛な人です。6次産業をしている弊社は一社で三社分の働きをします。さまざまな商品を生み出せるからこそ、好奇心を持って仕事に取り組める人は活躍できると思います。
あとは、ポジティブで素直なこと。
仕事をする上で「応援される人間」であるのは非常に重要です。私も20歳で農業界へ飛び込んで、右も左も分かりませんでしたが、たくさんの人に応援していただきました。分からないことは「分かりません!教えてください」と正直に言い、困難にぶつかっても一生懸命ポジティブに行動できると、まわりから応援され最短で成長ができるのではないでしょうか。
――今後6次産業は、どのように発展していくと思いますか?
ハイブリッド型6次産業が増えていくと思います。
今までの6次産業は2次産業の加工場を自社で持つことが多かったです。自社が工場を持つとなると、加工するための設備や人材、免許や知識など初期投資にお金と時間がかかります。6次産業をやりたいと思っていても、初期投資がネックとなり参入しづらい業界も多かったんですね。
しかし、弊社の場合は加工場を持っていません。例えばジャムですと、商品企画まで行い実際に手を動かして商品を使ってもらうのはジャム工場に委託をしています。委託をすることでお金と時間が大幅にカットできます。
このように、さまざまな会社と組み合わせて産業を行う“ハイブリッド型6次産業”が、今後はあらゆる業界で増えてくると思います。
アイデアの見つけ方、メリット・デメリット……起業を目指している学生へアドバイス
――起業を目指している学生に向けてアドバイスをお願いします。まず、アイデアはどのように見つけたらいいのでしょうか?
一つの業種に絞りすぎずに考えるのがおすすめです。日々生活をする中で「不便だな」「もっとこうなればいいのに」と感じることを、さまざまな角度からメモしておくと、アイデアに結びつきやすいです。
例えば私の場合は、農業に関する本を読むだけではなく、ITに関する本を読んだり、セミナーを受講したりします。情報をインプットしながら「この話はROSE LABOに活かせられないかな?」と自分ごとにして考えるようにしていますね。そうすると柔軟なアイデアが出やすくなると思います。
――学生起業のメリット・デメリットを教えてください。
メリットは仲間を集めやすいこと。コミュニティが多いため、理念や行動指針に共感してくれる人や自分の苦手分野をカバーしてくれる人をスカウトしやすいです。他には、まだ学生起業家が少ないからこそ、注目を集めやすいのもメリットの一つです。
デメリットはお金がないこと。学生は本業があるからこそ、資金が集めにくいです。私の場合は親族や銀行からの借入で資金を集めましたね。日本政策金融公庫では、若者の女性を対象に新規開業資金の支援を行う制度があるため、このような制度をうまく活用するのも一つの手だと思います。

――「将来何をしたらいいのか分からない」と悩む学生へアドバイスをお願いします。
まずは「私の幸せってなんだっけ?」と考えてみましょう。どのようなときに幸せを感じるのか、思いつくままに紙に書き出してみる。そうすると共通項が見えてきます。私の場合は「健康寿命を楽しく生きること」でした。幸せのカケラが見えて、自分を知ることができたら、次にするべき行動が分かってきやすいです。
あとは、なんでもやってみること。
実際に経験する・しないとでは大きく違います。「頭では理解しているものの、実際に経験してみると違っていた」なんてことも多いですよね。興味があることはとにかく挑戦してみて、その中で「自分に合う・合わない」を考えたり、どこが合わなかったのかを記録したりすると見つけやすいと思いますよ!
――ありがとうございます!最後に今後の展望とメッセージをお願いします。
人生100年時代の今、健康寿命が終わってからも生活は長く続いていきます。今後は健康寿命を1日でも長くすることにも貢献できたら幸いです。バラを使って新薬を開発したり、植物療法で皆さんの人生をより健やかにしたりと、幅広い取り組みをしていきたいです。
学生時代は将来にとても悩んでいたため、私の経験が少しでも皆さんの人生の参考になれば嬉しいです。人生は一度きりなので、後悔のない決断をしてください。行動することが一番の近道だと思います!

1993年生まれ、東京都出身。大学を2年次に中退後、大阪の食用バラ農家にて修業。2015年に独立し「"食べられるバラ"を通して美しく、健康に、幸せに」を理念にROSE LABO株式会社を設立。"食べられるバラ"の栽培、バラを配合した加工食品や化粧品などの商品開発、販売を行なう「6次産業」の農家として、講義、セミナー、農業コンサルティングなども行っている。2019年「マイナビ農業アワード」などで最優秀賞を受賞。
※記事内容及び社員の所属は取材当時のものです。
提供:農業の魅力発信コンソーシアム
============
文:田中青紗
編集:学生の窓口編集部
取材協力:ROSE LABO株式会社
https://www.roselabo.com/