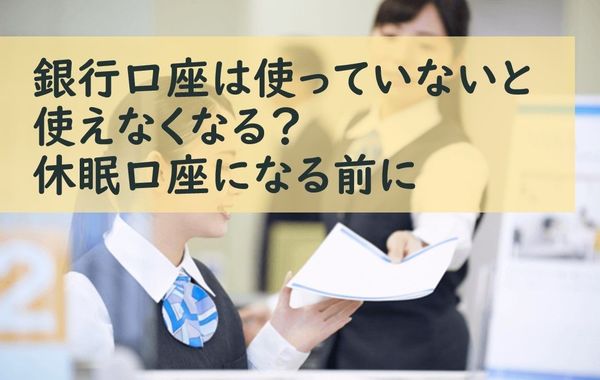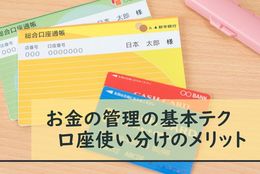休眠口座とは? 銀行口座を使わず放置したらどうなるか解説
休眠口座とは何か、また解約手続きについて解説します。何年も使わずに放置している銀行口座をそのままにしていると、やがて「休眠口座」とされて、利用したいときにすぐ引き出せない、といった面倒事が発生します。しばらく使わずに放置している口座があれば、一旦解約するなどご自身の口座を適切に管理するようにしましょう。
▼目次
1.長期間未使用の口座は休眠口座とされる
2.休眠口座になる前の事前通知について
3.休眠口座になったらどうなる?デメリットは?
4.まとめ
長期間未使用の口座は休眠口座とされる
子どもの頃に親に作ってもらった口座を、大人になってすっかり忘れてしまっている。あるいは亡くなった家族の口座をそのままにしてしまっている。
ーーこんなことはありませんか?
10年以上にわたってお金の引き出しや預け入れなどの取引がない口座をそのまま放置しておくと、「休眠口座」とされてしまいます。そして休眠口座の預金は「休眠預金」となります。
これは2018年1月に施行された「休眠預金等活用法」に基づいています。実は、日本では毎年1200億円程度の休眠預金が発生しているとも言われているのです。
休眠預金等活用法とは
「休眠預金等活用法」とは、正式名称「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」のことで、2018年1月に施行されました。
この法律によれば、10年間何の動きもない預金は「休眠預金等」とされます。そして2019年1月以降、順次発生する休眠預金は、社会課題の解決や民間での公益的な活動の支援に活用されるようになっています。
たとえば若者の支援や地域支援など、さまざまな社会的課題の解決を目指して、長期間眠っている預金を有効活用しようという目的で作られたのが「休眠預金等活用法」なのです。
休眠預金となるのは普通預金だけ?
実は普通預金だけではなく、定期預金や貯蓄預金なども休眠預金の対象となります。
・普通預金・通常貯金
・定期預貯金・定額貯金・定期預金
・当座預貯金
・貯蓄預貯金 など
※外貨預貯金や仕組預貯金、財形貯蓄などは休眠預金の対象にはなりません。
上記の中で特に注意したいのが、自動継続し続けている定期預金。最初に定期預金を預けたときの最初の満期日から10年間、単に自動継続しているだけでは休眠預金になってしまいますので要注意です。
使っていない口座は解約しよう
引き出し・預け入れ・振込入金・口座振替・通帳や証書の発行などを行えば、その後10年間は休眠預金にはなりません。しかし、記帳、残高照会、利子支払いだけでは、銀行によっては使用したとみなされない場合もありますので、注意が必要です。
長期間にわたって使用していない口座や、今後使わないと思われる口座は、休眠預金になる前に解約してしまいましょう。
解約するには、一般的には登録の印鑑・通帳・キャッシュカード・本人確認書類などを持って銀行の窓口に行きます。手続きを済ませれば、残った預金が手元に戻ってきて、口座解約となります。
詳しくは、各銀行に事前に解約方法について確認されると安心です。
休眠口座になる前の事前通知について

休眠口座(休眠預金)になる前には、事前に通知するしくみがあります。
預金残高が1万円以上の場合には、何も動きがなく9年を経過した頃に郵送あるいは電子メールで通知が送られることになっています。
このとき、郵送あるいは電子メールが「宛先不明」にならずにきちんと届けば休眠預金にはなりません。連絡先が明らかな預金ということで、引き続き通常どおり使えます。
しかし郵送あるいは電子メールがきちんと届かないと、連絡先不明の宙ぶらりんな預金とみなされて休眠預金になってしまいます。金融機関に届け出ている住所やメールアドレスは、定期的にチェックしておくことが大切ですね。
そして預金残高が1万円未満の場合は、上記のように郵送や電子メールでの通知はありません。
何も動きがなく9年を経過した頃に金融機関のwebサイト上で公告されるだけですので、残念ながら気づかずに10年を経過してしまう可能性は高いでしょう。
休眠口座になったらどうなる?デメリットは?
「休眠預金等活用法」によって、10年以上動きのない休眠預金は各金融機関から「預金保険機構」に移管されます。そこから民間の公益活動に活用できるようになりました。
実際に2019年1月1日以降は、この休眠預金が発生し、公益活動に使われるようになっています。あなたの休眠預金も、いつの間にか公益活動に使われている可能性があるということになります。
休眠口座になっても引き出しはできる
休眠口座(休眠預金)になってしまったからといって、お金はもう返ってこないというわけではありません。再開の手続きを経て、引き続き口座からお金を引き出すことができます。公益活動に使われたか否かも関係ありません。
休眠預金になったとはいえ、預金者としてはきちんと保護されるしくみになっているのです。
引き出しに時間や手間がかかる
休眠預金のデメリットは、取引を再開するための手続きに手間や時間がかかるということ。
一度休眠預金になると、キャッシュカードやATMなどを普通に使うことができません。金融機関の窓口で手続きが必要となります(郵送などで手続きできるケースもあります)。
具体的な手続きの内容については金融機関により異なりますので、必ず事前に確認するようにしましょう。一般的には通帳・キャッシュカード・本人確認書類・お届け印などが必要になると考えられます。
そして、実際に預金を引き出せるようになるには数日程度かかるケースが多いようです。このように手続きの煩雑さを考えると、日頃から眠っている口座がないかどうか意識して、必要に応じて解約していくことが大切です。
まとめ
10年以上使っていない銀行口座は、2019年1月1日から順次休眠口座(休眠預金)となり、公益活動に使われるようになります。預金者としては保護されていて引き続き預金の引き出しも可能ですが、銀行口座は適切に管理して、必要に応じて解約の手続きをするようにしましょう。

【監修】森 幸江(FP Office株式会社)
大学卒業後、三菱UFJ銀行(旧東京三菱銀行)にて15年勤務。預金、投資信託、住宅ローン等の総合相談窓口、証券仲介業務に携わる。子育て世代からシニア世代まで、1,000件以上の相談業務経験あり。お金にかかわる全てのことをどの世代にも分かりやすく話すのをモットーにしている。 小学校にて、金融教育の授業を行っており、日本のリテラシー向上の為、日々活動している。