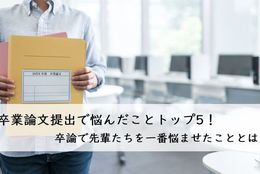卒論でのインタビュー調査のやり方は?アポ取りの例文から質問項目例まで解説!
※記事全文を読むには会員登録(無料)が必要です。

卒論でインタビュー調査を実施するケースは多いものです。ですが、はじめてのインタビュー調査は分からないことばかり…。相手があることなので、失礼はないか、ご迷惑になっていないか心配になりますよね。特に「アポ取り」は相手とのファーストコンタクトなので、緊張してしまうのではないでしょうか。
そこで今回は、卒論でのインタビュー調査のやり方について徹底解説。そもそも何人にすべきかといった疑問から、アポ取りの手順、事前準備や当日の流れまでご紹介します。最後までお読みいただくことで、心を落ち着けてインタビューに臨めるようになりますよ。
卒論のインタビューは何人にすべきか
「そもそも卒論のインタビューって何人?1人でもいいの?」
卒論のインタビューを何人にすべきかというのは、インタビューでどんなことを聞き出したいのかによりケースバイケースです。
例えば非常に特異性のあるケースについて詳しく聞きたいなら、その特異性を持つ相手「1人」で良いこともあります。あるいは、多様なケースについて明らかにしたいなら、ある程度の人数が必要となるでしょう。
このようにインタビューの人数はあくまでケースバイケースであることをふまえた上で、次のような事例や考え方があることをお伝えしておきます。よろしければ参考にしていただき、あとはご自身の指導教員ともよく相談した上で決めていくようにしましょう。
1.社会福祉の分野でのインタビュー例
「質的調査法の指導:卒業論文およびゼミ論文指導の経験から」(上智大学社会福祉研究 2000.3)という論文の中で、長年学生の論文指導をされてきた岡 知史先生は次のように述べています。
私の場合、卒業論文なら7人、ゼミ論なら5人の質的インタビューを目指すよう指導している。もちろん、質的調査のサンプル数を何人かと定めるのは無意味なことだが、1時間のインタビューをトランスクライブして、綿密に分析するには、時間的にも、労力的にもこれくらいが適当だと私は経験的に判断している。
(引用:岡 知史「質的調査法の指導:卒業論文およびゼミ論文指導の経験から」)
このように、インタビュー人数について5人〜7人が適当と述べています。
2.ヤコブ・ニールセン博士の説
ユーザビリティ研究の第一人者であるヤコブ・ニールセン博士は、
という研究結果を導き出しています。
これは、もともとはシステムなどのユーザビリティ(使い勝手)評価を扱った研究です。これを「5人いれば大部分の問題が発見できる」ととらえ、インタビュー人数の目安とする考え方があるようです。
卒論インタビューのアポ取りまでの流れと注意点
卒論インタビューで大きなハードルとなりやすい「アポ取り」。まずはこのアポ取りまでの流れと注意点について、詳しく解説します。
2.調査目的を明らかにする
3.教員に相談する
4.いよいよアポ取りで協力を依頼!
特にアポ取りについては、企業の代表窓口経験もある筆者が、企業側からの視点でしっかり解説します。例文もご紹介していますのでぜひ参考にして下さい。
1.事前にしっかり勉強しておく
インタビューに取りかかる前に、まずは勉強です。書籍や雑誌などで分かる部分と、インタビューで特に知りたい部分はしっかりと切り分けなければなりません。限られたインタビューの時間を有意義なものにするためにも、書籍や雑誌などで専門分野についてしっかり学んでおきましょう。
あらかじめ知識の土台をしっかりさせておいた方が、インタビューで話していただく内容への理解も深まるでしょう。
2.調査目的を明らかにする
次に、インタビューでの調査目的を明らかにしておきます。書籍や雑誌を通じて勉強していく中で「文献では分からない」「より深く掘り下げたい」「現場の声を聞きたい」など、インタビューで聞き出したい部分を明確にします。「何のために、あえてインタビューを行うのか?」を明確にするということです。
目的を明らかにすることで、インタビューの質問項目をしっかり設定でき、意義のあるインタビューとすることができます。それから「誰にインタビューすべきか」もおのずと絞られてくるはずです。
3.教員に相談する
ある程度方向性が決まってきたら、指導教員へ相談です。インタビューは対外的には「〇〇大学の研究室・ゼミ生」としての研究活動となるため、教員には了承をもらっておく必要があります。
もし先方から研究室に連絡が入るようなことがあった場合、「教員が知らない」では困ってしまいます。必ず教員には相談し、了承を得てから対外的なアクションを起こすようにしましょう。
4.いよいよアポ取りで協力を依頼!
いよいよアポ取り開始です!連絡手段としては、まず公式HPやSNSなどに「取材依頼はこちら」という窓口があれば、それを利用するというのが第一です。そうした窓口がなさそうな場合、手紙や電話、メールなどの方法を考えます。
手紙
最もフォーマルな依頼方法が手紙です。例文をご紹介しましょう。
○年○月○日
〇〇株式会社
広報ご担当者 様
〇〇研究に関する取材ご協力のお願い
ABC大学 社会学部環境学科
田中ゼミ
(担当:4年 鈴木三郎)
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
私は、ABC大学社会学部環境学科の田中ゼミにおいて、ゼロカーボンに関する研究を行なっております。
貴社におかれましては、カーボンニュートラルに関して先進的な取り組みをされていると知りました。そこで是非一度、その取り組みの経緯や現在の状況、今後の課題などをお伺いしたいと考えております。
つきましては、貴社にお伺いし、ご担当者様から1時間程度のインタビューという形でお話をお聞かせいただくことは可能でしょうか。ご多忙の折まことに恐縮ではございますが、何卒ご検討賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
<連絡先>
ABC大学 社会学部環境学科 田中ゼミ
指導教員 田中一郎先生
担当:4年 鈴木三郎
研究室住所:〒123-4567 東京都文京区△△1-2-3
電話:03-1234-5678 FAX:03-1234-5679
メールアドレス:suzuki@ABC.ac.jp
※下記に取材の可否をご記入の上、お手数ですがFAXにてご返信頂ければ幸いです。
もしご承諾いただけましたら、改めて詳しい取材内容をお送り致します。
ーーーーーーーーーーーーーーー
ABC大学 田中研究室(担当:鈴木)行
FAX:03-1234-5679
会社名・部署____ ご担当者名____
ご連絡先TEL____ メール______
取材可(対面)/ 取材可(zoom)/ 取材不可
ご要望やコメントがございましたら下記にご記入下さい。
メールや問い合わせフォーム
最近ではメールや公式HPの「問い合わせフォーム」を使ったアプローチが増えてきているようです。特にweb系やIT系企業など、ネットコミュニケーションが活発な業界にはおすすめ。
ですが、業界や相手によっては「問い合わせフォーム」があまり使われていないケースも。代表メールアドレスに送っても、迷惑メールに埋もれてしまって見過ごされる可能性も否めません。もしメールや問い合わせフォームで全く反応が見られない場合は、改めて書面で送ってみるなどの工夫も必要かもしれません。
ちなみにメールを送る際は、大学のメールアドレスを使うのが賢明です。
文面は先ほどの手紙版と基本的に同じ内容で、メール用に少しアレンジしてみるといいでしょう。
電話
個人事務所など、比較的小規模な組織で活動されている方には、電話が意外に話が早いかもしれません。
ですが、企業によっては電話応対の担当者が面食らってしまい、とっさに対応できないことも考えられるため注意が必要です。 企業の総合受付には悪質な電話も多く、取り次ぎの判断が難しいケースも多いためです。
電話でうまく伝わらなかった場合は、メールや書面など別の方法でのアプローチも考えてみましょう。
TwitterのDMはどうなの?
SNSで多くのフォロワーを持つ著名人の中には「DMが来て、気になったから会ってみた」というケースもあります。公式問い合わせ窓口が見つからない場合はDMを使うことも考えてみましょう。
ただしDMだからといって、カジュアルな文面になってしまうのはNG。基本的には手紙のところでご紹介した例文を参考に、少しコンパクトにまとめるなど工夫してみましょう。
日程調整と主旨説明について
インタビューの依頼に了承を得られたら、日程などの詳細を詰めていきます。あわせて相手が「何を聞かれるのか?」と不安になることのないよう、あらかじめ質問内容をWordなどで箇条書きにして送信しておくといいです。例文をご紹介しておきます。