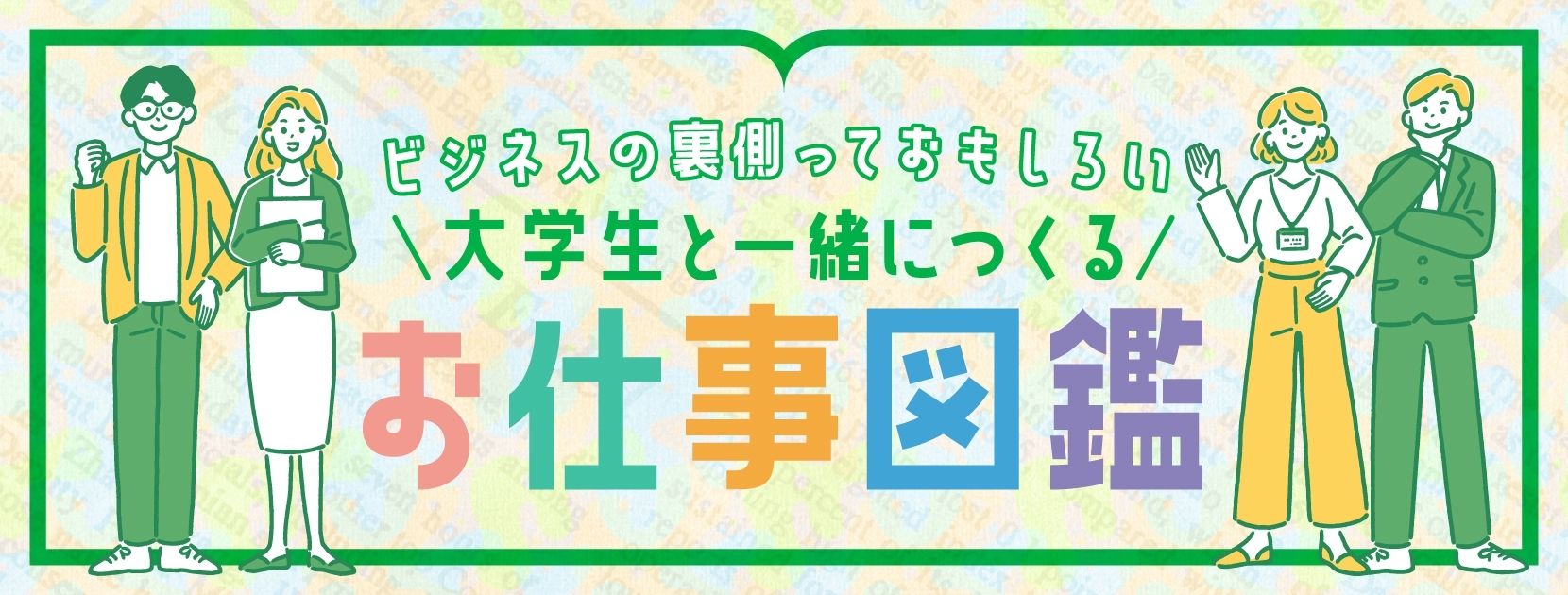【お仕事図鑑】チョコレートの原材料にまでこだわる商品開発とは? #株式会社 明治

株式会社明治 研究本部商品開発研究所カカオ開発研究部 カカオクリエイター
チョコレートの原材料・カカオの研究を行い、10年以上前からカカオ原産地での活動に注力している。明治のカカオ農家支援「メイジ・カカオ・サポート」の立ち上げメンバー。現在はチョコレートの開発業務に携わる。
世の中にはさまざまな「仕事」があります。中には、どのような仕事なのか、その中身があまり分からない職種も少なくありません。
例えば、食品メーカーの「研究開発」の仕事はどうでしょうか? お菓子を生み出す仕事には、どんな魅力や面白さがあるのでしょうか?
今回は、数多くの人気菓子や食品を手掛ける『株式会社 明治』で研究開発に携わる宇都宮洋之さんに、商品開発の仕事内容や、自身が手掛けられたヒット商品の裏側を伺いました。
▼INDEX
1.研究開発は「商品を具体化していくためのなんでも屋」
2.『明治 ザ・チョコレート』は「そこまでやるか」というレベルで作った
3.こだわりを貫いた二代目ザ・チョコ
4.世に出るモノを生み出せる仕事
5.他のメーカーはまねできないカカオから追求するお菓子作り
6.世界で明治しかしていない、できない仕事をする
7.「やらされている」という感覚を捨てること
研究開発は「商品を具体化していくためのなんでも屋」
――まず自己紹介をお願いします。

株式会社 明治 研究本部商品開発研究所カカオ開発研究部の宇都宮洋之です。1993年に明治、当時の「明治製菓」に入社し、これまで約27年、チョコレートとカカオを追究する仕事をしております。
――「商品開発」とはどんな仕事なのでしょうか?
商品開発は、市場のニーズに向けてシーズ(基礎的な研究開発)を材料に、どのような商品を打ち出せば市場に響くかを考え、商品を作っていく仕事です。簡単にいえば、「こんなのが作りたいです!」と会社に提案して、具体化する仕事ですね。
ただ、作りたいと提案してもそう簡単に実現できるわけではありません。作るのは工場ですから、設備は大丈夫か、素材は大丈夫かと考えないといけませんし、原価コストも重要です。会社として、これらをすべて網羅して儲かります、というところまで話を全部考えて組み立てる必要があります。
――商品を生み出す「頭脳」なのですね。
そうともいえるかもしれません。まあ「商品を具体化していくためのなんでも屋」ですね。情報やアイデアは持っていますが、商品を作るのは自分たちだけではできません。商品を世に送り出すべく、社内のさまざまな部署に協力してもらい、ひとつの意見にまとめあげるのが仕事だといえます。
『明治 ザ・チョコレート』は「そこまでやるか」というレベルで作った
――宇都宮さんが世に送り出したヒット商品『明治 ザ・チョコレート』の開発について教えてください。

実は「ザ・チョコ」を作る前にも、当社は、同じようなチョコレートを出してきました。しかし、結果として市場に残っているのは一個もない状況でした。そこで何をすればいいのかと考えたのですが、自分が頑張ってきた「カカオ」で勝負しようと思ったのです。
私は入社10年目くらいから、チョコレートの原材料であるカカオの品質向上に取り組んでいます。今は「明治カカオサポート」という名前も付きましたが、ずっと現地に行き、農家の方にカカオ豆生産の技術指導を行ったり、より良い形で作業ができるよう労働環境の改善や意識改革に取り組んだりといったことをしています。その取り組みが実を結び、現在明治のカカオ豆の品質は世界でもだいぶ上のレベルになったと思います。「メーカーがそこまでやるか」というレベルで取り組んでいます。
ただ、それだけ高品質のカカオでチョコレートが作れるように頑張ってきたのに、その頑張りをうまくお客さまに伝える商品がありません。そのため、「カカオの産地ごとに味の異なる商品」というコンセプトで生まれたのが『明治 ザ・チョコレート』です。
こだわりを貫いた二代目ザ・チョコ
――『明治 ザ・チョコレート』がヒットした要因は何でしょうか?

実は今の商品は二代目です。初代はあまり売れませんでした。二代目を作る際は、初代の製品に何が足りなかったのかを検証するために、カカオ、チョコレートに携わっている方々、例えばサロン・デュ・ショコラ(チョコレートの祭典)の創設者や品評会の審査員など、いろんな人にアポなしで評価してもらいました。
そうして初代の問題点を改善したのが現在の商品です。味だけでなく、デザインやパッケージングなど、一つ一つにとことんこだわりました。
――特にこだわった点は?
やはり素材です。自信がありました。チョコレートの専門家の方々からも高評価をもらいましたし、特にチョコレートの本場であるフランスの方から、「発売品が楽しみ」と高く評価されました。
パッケージもこだわっています。日本のチョコレートは、一般的に「横型」のパッケージが主流です。しかし、ザ・チョコのパッケージは「縦」です。実は欧州は縦のパッケージが多く、日本だけでなく海外でも勝負したいという気持ちもあって、この形にしたのです。
――これまでと違う形にするに当たり、反発もあったのではないでしょうか?
会議ではケンカになりましたね。でも素材から何からこだわって作ろうとしているのに、妥協したら台無しです。絶対に譲れないという意思を示したら、最後は「好きにしろ」と言ってくれました。
――他にはどんな「こだわり」が込められていますか?
コントロールの効く範囲でしか作らないようにしました。
以前、同じように品質にこだわった商品を出してヒットしたのですが、在庫切れしないように素材をかき集めた結果、品質が維持できなくなったのです。同じ轍を踏まないよう、今回はヒットしてカカオ豆が足りなくなっても「発売を休止する」ことも想定して取り組みました。
これもそれまではあまりなかった決断だと思います。
世に出るモノを生み出せる仕事
――商品開発の魅力は?
若い頃に感じたのは、「自分が作った商品が店頭に並ぶ喜び」ですね。発売されたら、やはり気になって見に行くわけですよね。「おっ、カゴに入れてくれた」「買ってくれている」と、いちいちうれしい。世に出るモノを生み出せるのはこの仕事の魅力だと思います。それに、作った商品は明治の歴史に残るわけですよ。
――『明治 ザ・チョコレート』もずっと名前が残りますね。
自分の仕事が歴史に残るってすごいですよね。仕事を覚えて経験を積んでいけば、商品につながるまでのシステムや、市場を丸ごとごっそり動かすような大きな仕事ができるようになる。商品そのものを生み出すのも面白いですし、商品を通して市場を動かすというダイナミックなことができるのも商品開発の面白い点ではないでしょうか。
他のメーカーはまねできないカカオから追求するお菓子作り
――宇都宮さんは「カカオクリエイター」という肩書でも活躍されていますが、元からカカオに関する仕事がしたかったのですか?

いえ、学生時代はカカオのことは全く知らないですし、チョコレートもよく口にしていたものの、どうやって作るのか知りませんでした。ただ、大学で勉強してきたのが「食品化学」だったことや、それまで育った環境の中で、明治の商品をよく口にしていたので一番力を入れて就職活動をしたのを覚えています。
――なぜ「カカオ」を追求するようになったのでしょうか?
チョコレートを作る工場で製造業務を担当していたときに、「原料のカカオもこだわった方がいいのでは?」と思ったのがきっかけです。工場でのチョコレート作りは、基本的に会社が「これ」と決めたものを、いかに決められた通りに商品にするかです。つまり、工場に入ってくるカカオは最初からどこのものか決められているのです。
そこで、ただカカオを買ってきて作るのではなく、カカオの産地に足を運び、自分たちでイチから管理するとどうなるのかを考えました。2005年くらいだったと思いますが、会社に提案すると、まあやってみようとOKをもらえて、そこからずっとカカオの品質を向上させる仕事をしています。
――その情熱はどこからきているのですか?
「誰もやっていない」というのが大きいですね。今ほとんどのメーカーは産地からは離れていく傾向にあります。「我々は商品を作るメーカーであり、原材料の部分は分業化して効率化する」というのが世界の流れですね。
そんな中で、カカオの品質まで自分たちで行っているのは明治くらいです。最初から最後まで自分たちで行っているからこそ、責任が持てるし、良い商品作りにつながっていると思います。現地は日本の住環境に慣れている人にとっては厳しい環境ですけど、行けば楽しいので、また行きたくてしょうがないです。
世界で明治しかしていない、できない仕事をする
――今後の展望を教えてください。
「明治にしかできないこと」をしたいですね。例えば、今ホワイトカカオの研究を一生懸命進めています。ホワイトカカオは貴重なもので、あまり世間に出回っていません。明治では2016年ぐらいから研究と商品化を進めており、これは自分たちしか商品化できない領域です。
また、2020年に「ルビーカカオ」という、ピンク色のチョコレートが注目されましたが、明治としても、世界を驚かせる研究をしていますので、今後に期待していただきたいですね。
発表された際には、「あのインタビューで言っていたのはこれか!」となるでしょう(笑)。
――遺伝子的な研究もされているのでしょうか?
そうですね。味を追求するだけでなく、歴史や遺伝学的な要素の研究も明治としてできるのではと考えています。
『JICA』(独立行政法人国際協力機構)さんと共同でマダガスカルでも研究を頑張っていて、世界のカカオの品種的なつながりや、世界的に貴重な品種の保存にも取り組んでいます。とにかく誰も行っていないので、それなら自分でやってしまおうというわけです。
将来的には、世界的に貴重なカカオは明治が持っている、なんてことになるかもしれません。
「やらされている」という感覚を捨てること
――最後に学生へのメッセージをお願いします。

「やらされている」という感覚で働かないことですね。
「なんでやんなきゃいけないんだ」と考えているとそこで止まります。いつか必ず自分のためになる、と思うことです。日々仕事をこなしているだけでは自分の肥やしにならないし、いつか巡ってきたチャンスをチャンスと気付けません。 幾つになっても勉強です。
私もこの会社入って27、8年ですけどずっと勉強しています。資料、文献を読むのもいいですし、私のように現地に行って何かをするなど、体験することもいいでしょう。 目標にたどり着くには、とにかくずっと思い続けないといけません。どこかで諦めたら絶対到達できません。
皆さんがどんな職業に就くかは分かりませんが、前向きな姿勢でいれば、会社にとっても自分にとっても双方がいい関係でいられると思います。人生はそう甘いものではありませんが、楽しいこともあります。お互い頑張りましょう(笑)。
――ありがとうございました!
※記事内容及び社員の所属は取材当時のものです。
編集後記
「研究開発」では、商品につながるアイデアを出すだけでなく、商品として世に出すことができる仕事です。自分が生み出したお菓子を親子がおいしそうに食べてくれる、そんな風景を生み出すことも可能です。多くの人を幸せにする商品を生み出すには、幅広い知識とコミュニケーション力、商品を形にするための情熱が必要です。もし商品開発の仕事を目指すのなら、知識や経験だけでなく、「熱い心」も忘れないようにしたいですね。
============
編集:学生の窓口編集部
取材協力:株式会社 明治
https://www.meiji.co.jp/