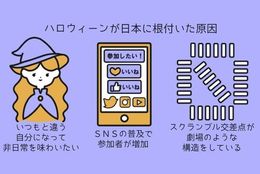「半ドン」や「花金」の意味ってなに? #もやもや解決ゼミ
日常に潜む「お悩み・ギモン」=「もやもや」を学術的に解決するもやもや解決ゼミ。
みなさんは「半ドン」や「花金」という言葉を聞いたことはありますか? 「半ドン」は40代以上の人が使うことが多いのですが、「花金」は若い世代の人はあまり聞いたことがないかもしれませんね。では、この2つの言葉の意味はご存じでしょうか?
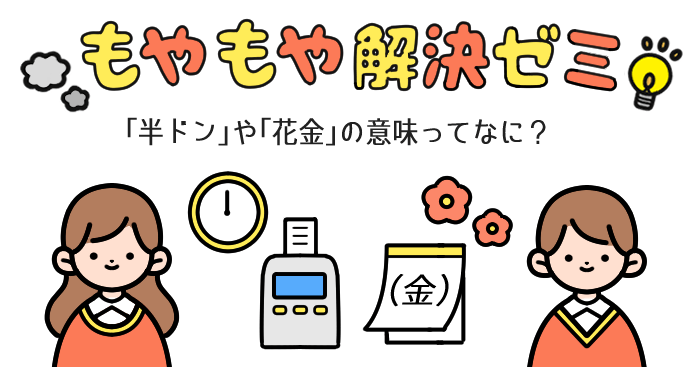
今回は、「半ドン」と「花金」の意味、いつから使われているのか、さらには誕生の背景を、日本語学者である梅花女子大学・米川明彦名誉教授に解説していただきました。
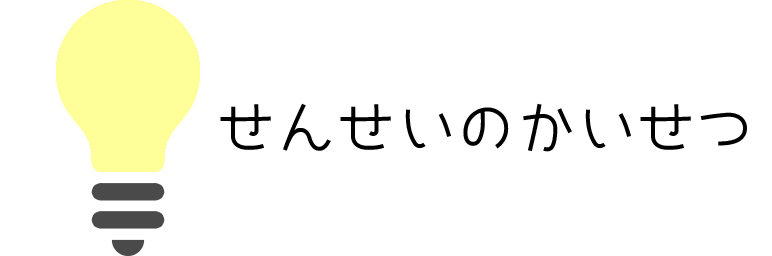
半ドンは明治時代から使われていた言葉
「半ドン」は「半分ドンタク」という言葉の略語です。「ドンタク」は、日曜日という意味のオランダ語「Zondag(ゾンタク)」が転訛(てんか)した言葉。つまり、「半ドン」は「半休」という意味になります。
1876年3月12日の太政官達により、この年の4月から官員(公務員)は日曜日を休日、土曜日を半休とすることとなりました。そこで、半休である土曜日を半分ドンタク、略して「半ドン」と言うようになったのです。つまり、「半ドン」というのは、「土曜日」を指す言葉でもありました。
わたしが見つけた「半ドン」の用例で最も古いのが、1877年の『団々珍聞』第5号にある「其間には幾度も指を繰り半ドン(土曜日のことか)を待つ」という一文。少なくとも今から130年ほど前から「半ドン」という言葉は使われていたようです。
長く使われてきた半ドンですが、1980年代に入って週休2日制が導入され、土曜日が半休ではなくなります。そのため、本来の「土曜日の半分が休み」という意味での「半ドン」は消えてしまいます。現在でも「半ドン」を使う人はいますが、これは特定の曜日ではなく、単なる半休という意味で使われているだけで、本来の意味ではないのです。

花金は1980年代に広まった流行語
「花金」は「花の金曜日」を略した流行語です。「金曜日の夜は遊んで楽しむこと」という意味で、OL用語として1985年に登場しました。
先ほどの「半ドン」にもつながる話ですが、1980年代の半ばに民間大企業で週休2日制が導入され、土曜日が丸々休みになる企業が増えました。そのため、休みの前日である金曜の夜に気兼ねなく楽しもうということで、OLを中心に「花金」という言葉が広まったのです。ただ、使われたのは数年間だけで、90年代に入ると使う人は減りました。
「花金」だけでなく、1987年には「花木」という言葉も流行しました。週休2日制が定着した当時は、日本経済が絶好調で、初任給も急上昇。金曜日の夜から旅行やレジャーに出掛けるというリッチな若者が増えました。そのため、飲んだり遊んだりするのは金曜ではなく木曜の夜が最適だと考えられるようになったのです。
「花木」は1988年の第5回新語流行語大賞の新語部門・銀賞に選ばれ、松屋百貨店が受賞しました。実は松屋百貨店は、若者が木曜日の夜を楽しむという流行をいち早く感じ取り、定休日を木曜日から火曜日に変更。従業員が花木を楽しめるようにしたので、「花木」が新語部門・銀賞になった際に、受賞対象になったようです。
ただし、この花木も1年ほどで使われなくなり、1989年になるとほとんど見なくなりました。最近では、「プレミアムフライデー」(2017年~)という、月末の金曜日は15時に仕事を終えて退社することを提唱する運動もありましたが、これは全く定着しませんでしたね。
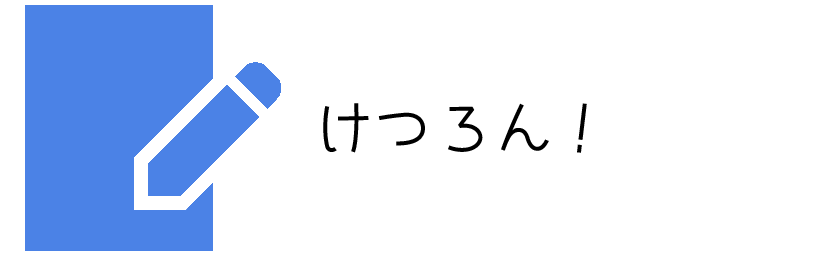
「半ドン」と「花金」の2つの言葉について米川先生にご解説いただきましたが、いかがだったでしょうか? 「半ドン」は実は明治時代から100年以上も使われていた一般語で、「花金」はわずかな期間しか使われなかった流行語なのです。どちらも若い世代はまず使わない死語ですが、みなさんが当たり前のように使っている言葉も、そのうち死語になってしまうかもしれませんね。
イラスト:小駒冬
文:高橋モータース@dcp
教えてくれた先生

米川明彦(よねかわ あきひこ)先生 Profile
梅花女子大学名誉教授。日本語学者。
1955年生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。学術博士。梅花女子大学名誉教授。『平成の新語・流行語辞典』(東京堂出版)、『明治・大正・昭和の新語・流行語辞典』(三省堂)、『俗語発掘記 消えたことば辞典』(講談社選書メチエ)、『俗語入門』『ことばが消えたワケ』(以上、朝倉書店)