バナナはおやつに入るの? 永遠の謎に哲学の先生が答える #もやもや解決ゼミ
日常に潜む「お悩み・ギモン」=「もやもや」を学術的に解決するもやもや解決ゼミ。
小学校の遠足のとき、先生から「おやつは500円以内ですよ」と言われると、ある小学生が「バナナはおやつに入りますか?」と質問する。こんな場面が実際にあるかどうかはさておき、“あるあるネタ”としてよく知られていますよね。大学生の間でも、旅行にいくときなどは一種のボケとしても使っている人もいるのではないでしょうか。
「バナナはおやつなのか、それともおやつでないのか」
この永遠の問いに、哲学の先生が真剣に答えます。

今回答えてくれたのは、山口大学 国際総合科学部の小川仁志教授。小川先生は、一流商社、市役所勤務の経験もある異色にして気鋭の哲学者として知られています。
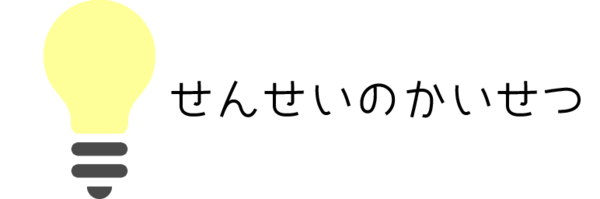
「哲学的思考」の3ステップで物事の本質をみる
これは直球ストレートの質問を投げかけられましたね。哲学しがいがあります。
そこで今回は歴史上の哲学者の考えを応用するのではなく、私も素直に3回バットを振ります。つまり、哲学の基本を実践することで、答えを出したいと思います。
3回バットを振るといいましたが、哲学の基本というのが、次の3ステップから成っていることからそのように表現しました。
(1)既存の思い込みを疑う
(2)複数の視点で見直す
(3)それらの情報を再構成してまとめる
この3ステップを踏んで考えることで、今まで見えていなかった物事の本質が立ち現れてくるのです。
そもそも「遠足のおやつとは何か?」を哲学する

実際にやってみましょう。今回問題になっているのは、そもそも「遠足のおやつとは何か?」ということだと思います。
(1)既存の思い込みを疑いましょう。
すると、一般には「遠足のおやつというのは、お弁当以外のスナック菓子」だと思っている人が多いと考えられます。だからこそ、バナナがおやつに入らなそうな気がするわけです。これを「思い込み」だとして疑ってみましょう。じゃあ一体なんなのか?
(2)複数の視点で見直します。
例えば、栄養の視点からすると、遠足のおやつは「疲れたときに栄養を補給する糖分」とみることができますね。あるいは、遠足の楽しみの視点からいうと、みんなで見せ合ったり、交換することこそが楽しいので、おやつは「コミュニケーションツール」だともいえます。
もちろん私たちが思い込んでいるように、おなかがすいたときにお弁当を補完する食べ物としての側面もあるわけですが。もっとほかにもいろいろな見方ができるでしょう。
(3)こうした視点をあらためて眺めてみて、再構成します。
そうすると、どうやら遠足のおやつは食べるというだけでなく、もう一つ友達とコミュニケーションを取るという重要な側面があったことに気づきます。いわば、遠足のおやつは「食べるコミュニケーションツール」なのです。
バナナはおやつに入る。なんなら納豆も入る。
さて、それが遠足のおやつの本当の本質だとしたとき、大事なのは平等性です。
子どもたちが楽しくコミュニケーションを取るには、上下の差があってはいけません。例えば、お金持ちが大量に高級なおやつを持ってきたとしたらどうですか? もう見せ合う楽しみも、交換する楽しみもなくなってしまいますよね。だから条件を平等にしなければならないのです。一番分かりやすいのは「金額」です。
とすると、バナナも「食べるコミュニケーションツール」ですし、金額の範囲内であれば、遠足のおやつの条件を満たし得ます。1本いくらか計算することは可能ですから。
それどころか、納豆であろうが、キムチだろうが食べ物ならなんでも入るはずです。ちなみにいずれも実際に私がおやつに食べるものです。コミュニケーションツールとしては最高でしょう? ただし、保存と匂いに注意が必要なのはいうまでもありません(笑)。
「哲学的思考」で物事の新しい見方を
大学生のみなさんも、先ほど紹介した哲学的思考の3ステップを覚えておくようにするといいですね。
今回は「バナナはおやつに入るのか?」という命題でしたが、この思考方法はどんな問いに対しても使えるものです。
既存の思い込みから解放された、新しい物の見方を導けるようになりますよ。
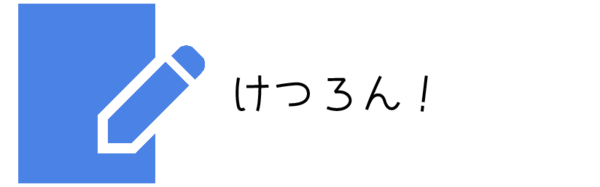
「バナナはおやつに入るのか?」は、おやつをどう定義するかの問題にいきつくようです。たしかに、既存の思い込みを排除して、おやつを「食べるコミュニケーションツール」と考えるなら「バナナもおやつに入る」ことになります。このように明解な回答を得られるのも「哲学的思考の3ステップ」のおかげです。小川先生のアドバイスにあるように、ぜひみなさんもこの思考方法を身につけてみてください。自分の世界を広げることにつながることでしょう。
イラスト:小駒冬
文:中田ボンベ@dcp
教えてくれた先生

小川仁志(おがわひとし)
1970年、京都府生まれ。哲学者・山口大学国際総合科学部教授。京都大学法学部卒、名古屋市立大学大学院博士後期課程修了。博士(人間文化)。商社マン(伊藤忠商事)、フリーター、公務員(名古屋市役所)を経た異色の経歴。徳山工業高等専門学校准教授、米プリンストン大学客員研究員等を経て現職。大学で新しいグローバル教育を牽引する傍ら、「哲学カフェ」を主宰するなど、市民のための哲学を実践している。また、テレビをはじめ各種メディアにて哲学の普及にも努めている。NHK・Eテレ「世界の哲学者に人生相談」には指南役として出演。最近はビジネス向けの哲学研修も多く手がけている。専門は公共哲学。著書も多く、ベストセラーとなった『7日間で突然頭がよくなる本』や『ビジネスエリートのための!リベラルアーツ哲学』、『これからの働き方を哲学する』をはじめ、これまでに約100冊を出版している。





























