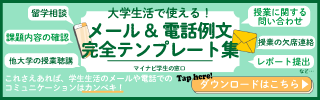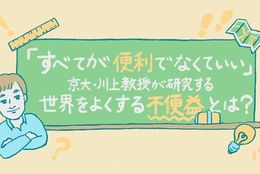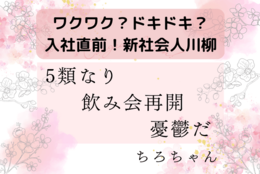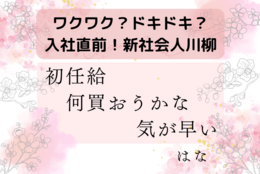日本の漫画、アニメ、特撮を歴史学の観点でひもとく! 創価大学・森下達博士の研究
現在「マンガ」「アニメ」「特撮」といった、日本のポピュラー・カルチャーは世界中で愛好されています。しかし、これらは昔から現在のように人気を博していたわけではありません。その成立過程や評価の変遷は研究対象になりえます。
今回は、日本独自のポピュラー・カルチャーをテーマとする創価大学 文学部の森下達博士の研究をご紹介します。
日本のポピュラー・カルチャーについての研究
森下先生は、日本のポピュラー・カルチャーについての気鋭の研究者です。
森下先生の博士論文は「『特撮映画』・『SF(日本SF)』ジャンルの成立と『核』の想像力 ―戦後日本におけるポピュラー・カルチャー領域の形成をめぐって―」というもので、「特撮」「SF」「ゴジラ」など、日本を代表するポピュラー・カルチャーがどのように生まれ、評価され、どのような関連性を持つのかといった点を論じています。
また「ゴジラはいかにして倒されたか 映画『ゴジラ』(1954年)におけるスペクタクルと物語」という論文では、最初のモノクロ映画『ゴジラ』でどのようにゴジラが倒されたのかをカット(シーン、シークエンス)を取り上げながら、周到に練られた物語性がそこに潜んでいることを指摘しています。
『ゴジラ』第1作のような、論じる人が世界中にいる有名作品では、批評のための新しい視点を探すのは難しいものです。
この論文は森下先生の洞察力の深さを示しているといえるでしょう。このように森下先生の研究は日本のポピュラー・カルチャーを対象にした興味深いもので、世界中の人が日本の「マンガ」「アニメ」「特撮」などに注目している現在だからこそ一層必要とされるものだといえます。
⇒参照:『京都大学学術情報リポジトリ』「『特撮映画』・『SF(日本SF)』ジャンルの成立と『核』の想像力 ―戦後日本におけるポピュラー・カルチャー領域の形成をめぐって―」
※森下先生の博士論文の「序論」を読むことができます。
⇒参照:『怪獣から読む戦後ポピュラー・カルチャー 特撮映画・SFジャンル形成史』(青弓社、2016年)
※上記論文を改稿し青弓社より刊行
⇒参照:『東京成徳大学・東京成徳短期大学』「ゴジラはいかにして倒されたか:映画『ゴジラ』(1954年)におけるスペクタクルと物語」
「歴史学」の手法で日本のポピュラー・カルチャーを研究したきっかけは偶然だった
創価大学 文学部の森下先生にお話を伺いました。
――そもそも森下先生が日本のポピュラー・カルチャーの研究を始めようと思われたきっかけは何でしたか?
森下先生 私は大学時代、京都大学文学部の「二十世紀学専修」というところに所属しておりました。ここは、現代史学専修から派生したところなんですね。現代史学では主として政治文書が研究対象になりますが、現代という時代を考えるに当たっては、政治文書だけでは回らないところがあるのです。
私も、政治を研究したいわけではありませんでしたし、二十世紀学専修でなら自分の興味があるものが扱えると思い、この道に進むことにしました。
――その興味の対象が日本のポピュラー・カルチャーだったのですか。
森下先生 父親がマンガ好きで、家には手塚治虫、石ノ森章太郎などのマンガがそろっていました。家庭環境が影響したのでしょう。
――歴史学の研究対象で、マンガなどのポピュラー・カルチャーを選ぶのは異色ではないでしょうか?
森下先生 二十世紀学専修というところは、京都大学の歴史学の流れをくんでいるのですが、扱う対象は自由だったんです。現代を知るには、メディアのことも視野に入れなければならないということで、映画やマンガなど、どんなものでも好きに研究対象にしてよかったものですから、学生に大変人気がありました※。
――それはなんだか京大らしいですね。京都大学の研究者には、面白いと思うことを自由に研究するという人が多いような気がします。
森下先生 そうして二十世紀学専修で自分の興味のあるものを対象に研究を進めることになったのです。ですから、きっかけはあくまでも偶発的なものですね。ただ、京都大学の歴史研究の作法はしっかりと叩き込まれました。「原典に当たれ」ということです。これはとても大事な点で、私もこの「原典に当たれ」という作法を守って研究を行っているつもりです。
※京都大学大学院文学研究科・文学部に設立された「二十世紀学専修」ですが、残念ながら現在はありません。
マンガはいつどのようにして「近代的な物語性」を獲得したのか?
――先生は特撮、SFなどを研究対象にしていらっしゃいますが、これからどのような研究を行うおつもりでしょうか?
森下先生 これまで「特撮」「SF」に絞っていましたが、いよいよと言いますか「マンガ」についても研究対象としていきたいと思っています。ただ、現在のようにジャンルも作品数も大きく広がってしまったマンガを全て論じるのは不可能ですし、また論じるにしても何か統一的な視点を持って臨まないと難しいですよね。
――確かに、マンガと一口に言っても今では作品も数え切れないぐらいあります。
森下先生 マンガは今ではあって当たり前のものになっていますが、昔はそうではありませんでした。マンガという言葉が「画風」を指す言葉だった時代もあったのです。今の人たちはすっかり忘れていますが、マンガがカウンターカルチャー化した1960年代後半までには「マンガ批評」も盛んではありませんでした。批評の対象になるようなものとは見なされていなかったのです。
しかし現在では、マンガという言葉は「物語メディア」といった意味で用いられており、また批評に足る対象となっています。これはなぜ、どのようにしてそうなったのでしょうか?
そのような流れを、手塚治虫を中心とした1940-50年代のマンガ作品の「物語性」に着目して研究できたらと考えています。実はマンガの物語性、物語そのものについて論じた研究というのはあまりないのです。マンガはいかにして近代的な物語性を獲得したのかを明らかにしていきたいですね。
――先生の研究が社会に与える影響についてどのようにお考えでしょうか?
森下先生 そうなったらいいな、と思うことを述べてもいいでしょうか?
――もちろんです。ぜひお願いいたします。
森下先生 今、日本のポピュラー・カルチャーは激動期にあり、これまでの立ち行き方が成立しなくなっています。例えばマンガ一つ取っても、これまでは週刊マンガ誌に寄り添って発展してきました。しかし、雑誌が売れない、単行本が売れないといった時代の趨勢(すうせい)によって、大きな変化を余儀なくされています。
――出版業界は苦境に立たされていますね。
森下先生 また、マンガではキャラクター人気が立って、それがより大きく評価されているという変化もあります。もちろんキャラクター人気が悪いと言っているのではありません。ただ、キャラクターと物語は寄り添うものであるはずで、それが乖離(かいり)するのは気になります。
最近ではキャラクターに過度に注目することで、大事な物語性が失われている面があるのではないでしょうか。マンガは「物語メディア」ですから、物語性を持っていてほしいですね。物語性の重要さについての自分の研究が、マンガのこれからに何か絡んでお役に立てれば、と考えています。
――日本を代表するポピュラー・カルチャーの一つである特撮についても、庵野秀明監督が失われていく日本の文化を危惧するといった主旨で言及されていますね。
森下先生 そうですね。これまで現場の職人さんによって受け継がれてきた技術が失われようとしています。ただ、その代わりにCGのような新しい技術が特撮に取り入れられ、これまで以上にスペクタクルを視聴者に感じさせるように変化しています。
しかし、スペクタクル一辺倒ではやはり寂しいですし、そもそもスペクタクルと物語性は対立するものではないし、両立するものだと思います。特撮の場合にもマンガと同じく「物語性」があってほしいですね。
――ポピュラー・カルチャーの激動期だからこそ、マンガや特撮の作品にはもう一度物語性を問い直してほしいということですね。
研究の「面白い点」と「つらい点」
――先生の研究の面白い点はどんなところでしょうか?
森下先生 「当たり前のことを問い直すこと」だと思います。例えば、現在の若い人たちにとって、ポピュラー・カルチャーと呼ばれるものは、生まれたときから存在したし、あるのが当たり前でしょう。しかし、実はあって当たり前のものではないんですね。
それらがない時代があり、やがてそれが私たちの社会・生活と密接に関係するようになり、当たり前のものになる。僕らが当たり前だと思っていることは当たり前じゃないんだ、ということが分かるのは面白い点です。
――では逆に研究のつらい点はどんなことでしょうか。
森下先生 息抜きができない点でしょうか。映画やマンガは本来人が息抜きで楽しむものですが……こういう研究をしていますと、気分転換にと思って映画を見たり、マンガを読んでもつい研究者の視線で見てしまうのです。そのせいで息抜きにならなかったりします(笑)。
――なるほど。気分転換が気分転換にならないのはつらいですね。
森下先生の研究室は創価大学キャンパスの中央教育棟にあります。
「自分を鳥瞰(ちょうかん)できる視点」を養おう!
――当サイトは、現役大学生から大学進学を目指す高校生までたくさんの方が読んでおり、中には研究者になりたいと思っている読者もいます。「研究者の道が気になっているけれど踏み出せない」という学生へのアドバイスがありましたら、読者の背中を押してあげられるかもしれませんので、ぜひお願いいたします。
森下先生 背中を押すというか、おなかを押すことになってしまったらごめんなさい。もし躊躇するようならやめたほうがいいと思います。世間でよくいわれるように、研究者のポスト難というのは現実問題としてあります。上が抜けないと仕事がないという状況ですから、よほど自信がないと痛い目に遭うかもしれません。
――なるほど。
森下先生 ですから悩むのであればやめたほうがいい。なぜそれをしたいのか、鳥瞰(ちょうかん)的に問い直せるようにしたほうがいいですね。その上で、研究者になるという信念を持つのなら、そこに社会的な意味を持たせてほしいですね。研究というのはあくまでも自分の関心が鍵になりますが、その問題を敷衍(ふえん)して論じることは意味があるのか……そこは自問自答すべきです。
――それも「問い直し」ですね。
森下先生 研究者にもプレゼン能力は必要になったりしますし、「自分にはこのような強みがある」と自分で気付くことは大事です。ですから「自分をよそから見る力を養っておく」のがよいのではないでしょうか。
――ありがとうございました。
森下先生の研究は、歴史学の手法を用いて日本のポピュラー・カルチャーに切り込む非常に興味深いものです。ポピュラー・カルチャーはあって当たり前ですが、昔からあったものではないというのは、意外な視点なのではないでしょうか?
ポピュラー・カルチャーの歴史をたどってみると、埋もれていた事実や新発見があるようですし、私たちの生活、社会と密接に関係しているポピュラー・カルチャーは非常に魅力的な研究対象です。森下先生の「手塚治虫を中心とする1940-50年代のマンガ作品の『物語性』研究」についても成果が期待されますね。
(高橋モータース@dcp)
森下達
創価大学 文学部 講師。博士(文学)。
奈良県出身。2009年京都大学文学部(基礎現代文化学系二十世紀学専修) 卒業。東京成徳大学人文学部 助教を経て現職。著書に『怪獣から読む戦後ポピュラー・カルチャー』(青弓社、2016年)がある。