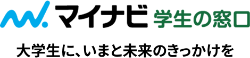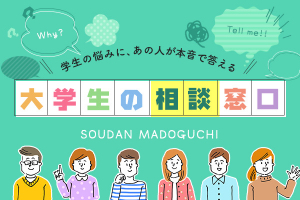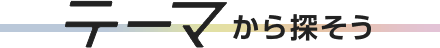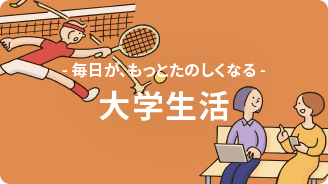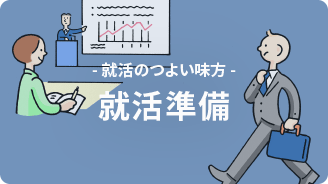「顕微鏡」でどこまで小さい物が見えますか? #もやもや解決ゼミ

日常に潜む「お悩み・ギモン」=「もやもや」を学術的に解決するもやもや解決ゼミ。今回のギモンは「顕微鏡ってどこまで小さい物が見えますか?」です。
大学生読者の皆さんも小学生のときには、理科の授業で顕微鏡を使ったでしょう。プレパラートに植物の細胞やミドリムシなどをセットして見ましたね。
では、現在の最先端の顕微鏡を使うと、どこまで小さい物が見えるでしょうか? 今回は、極限計測とナノ物性を研究されている『筑波大学』の重川秀実教授に答えていただきました。
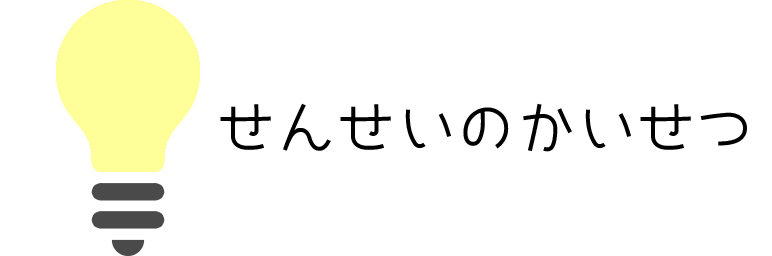
◇せんせいのかいせつ
「どこまで小さい物が見えるのか」という問いは――、
「何をどこまで見たいのか」また「何をどのように見たいのか?」
につながります。
何を見たいのか? 「何」のスケールを考えてみよう!
まず、「何」にあたる「小さい物」のスケールを考えてみましょう(図1)。
【図1】

↑肉眼、光学顕微鏡、電子顕微鏡で見える世界のスケール。
⇒参照・引用元:『JAIMA 一般社団法人 日本分析機器工業会』公式サイト「電子顕微鏡の原理」
https://www.jaima.or.jp/jp/analytical/basic/em/principle/
幅広い範囲にわたって異なる大きさを表すには、「べき乗」の表示を用いるのが便利です。
例えば、われわれが暮らしている世界では人間の大きさはおよそ1メートル(1m) = 10のゼロ乗m」と表せます。
1/10のx乗を「10のマイナスx乗」と書きますので、
1mの1,000分の1(10のマイナス3乗)mが1ミリメートル(mm)
100万分の1(10のマイナス6乗)mがマイクロメートル(μm)
10億分1(10のマイナス9乗)mが1ナノメートル(nm)
になります。
リンゴの大きさは、およそ10cm = 10のマイナス1乗m = 100mm 、10円玉や1円玉などの硬貨は、およそ1cm = 10のマイナス2乗m = 10mm、アリの大きさがおよそ数mmでしょうか。
これらスケールは人間の目で普通に見えます。
小さくなると、赤血球が10μm、ウイルスは10〜100nm程度のスケールです。
分子を見ようとすると必要なスケールは1nmになります。
ナノテクノロジーという言葉を耳にすることも多いかと思いますが、ナノメートルの大きさで表される領域で、いろいろな機能を生み出す技術を開発するのが現在の世界です。
原子を見ようとするとさらに一桁上がって 0.1nm(1オングストローム(Å)とも呼びます)のスケールになります。
肉眼では、0.1mmとか0.2mm、すなわち100μmの世界を見ることができます。髪の毛1本の直径はこのくらいです。
小学校や中学、高校の理科の時間に使った光学顕微鏡を思い出すかも知れません。
光学顕微鏡を使うと三桁ぐらい上がって、1μmの世界まで見ることができます。通常、ウイルスは見えないとされてきましたが、工夫を凝らすことでコロナウイルス(およそ100nm)の観察が実現しています
しかし、さらに小さい物を見るには電子顕微鏡を用います。
電子顕微鏡を使うと原子が見えます。つまり「ナノの世界」まで見えることになります。
顕微鏡で小さい物を見る際に「何」が制限になるのか
ところで、顕微鏡はどうやって小さい物を見ているのでしょうか?
光や電子は粒子と波の性質を持っていて、光学顕微鏡、電子顕微鏡どちらも「それらの性質」を利用して小さい物を見ています。
しかし、これが制限を生むことにもなります。対物レンズや接眼レンズを通して焦点を合わせて見ますが、どこまで近接する小さい物を分解して見られるかが「分解能の限界」になります。
人間の目でも、物があまりに小さくなると、一つあるのか二つあるのか見分けがつかなくなるでしょう。
この近接した二つの物を分解して見分けられるかどうかの限界(分解能の限界)は、回析現象によって生じます。
回折とは、波が物体(今の場合は見たいもの)の影に回り込む現象です。
回折が生じると近接した二つの物体の像が重なり合って区別がつかなくなり、「分解能の限界(回析限界)」が生じることになります。光と電子の波の性質によって、こうした限界が現れます。
波長が短い方が回り込みが小さく、分解能は高くなります。
つまり、分解能を上げるためには(小さい物を見るためには)できるだけ波長の短い光や電子を使えばいいということになります。
分解能の限界としては、
人間の肉眼では約0.1mm
光学顕微鏡では約0.2μm
電子顕微鏡では約0.1nm
となっています。
なぜ「光学顕微鏡より電子顕微鏡の方がより小さい物が見えるか」というと、より波長が短い電子の波の性質を利用しているからです。
肉眼と光学顕微鏡は、同じように可視光(目に見える光)を用いますが、分解能の差は、それぞれのレンズの違いによっています。
波長を比較してみると以下のようになります。
光学顕微鏡:~500nm
※目に見える可視光の代表的な値として示しています。
電子顕微鏡:0.0037nm(100kV)~0.0025nm(200kV)
※( )内の大きさの電圧を使って加速した電子の波長です。
電子の波長は、電子線を加速する電圧によるので、いくらでも高い電圧を使えばいいと思うかも知れませんね。
しかし、実際には電磁レンズの収差他の制限により、およそ0.1nmが限界です。
また、あまり大きな電圧で加速した高いエネルギーの電子を物に当てると、見たい物が焦げるといったことなどが起きます。
そのため、電子顕微鏡では、昔は生物を見るのが難しいと考えられていました。
現在ではいろいろな技術が導入され、装置も改良されて生物関係の小さな構造も見えるようになっています。
※しかし、試料を凍らせたり、回折パターンから実際の構造を計算して導く手法が用いられたりすることもあり、ここでは詳細は割愛します。
「極微の世界」を見る別の形の顕微鏡(STMとAFM)
それでは、次に「走査プローブ顕微鏡」という異なる仕組みの顕微鏡について見てみましょう。
この顕微鏡は、試料表面の原子構造が見えるだけでなく、個々の原子をいじったり、試料の電子状態(機能)を調べたりできる顕微鏡です。
さらに、最近では、非常に短いパルス光を用いる超短パルスレーザー技術を組み合わせることで、原子スケールで生じる現象を1000兆分の1秒(10のマイナス15乗秒:フェムト秒)の時間分解能(時間領域の分解能)で調べることも可能になっています。
いろいろな手法が含まれていますが、代表的なものとして、
・走査トンネル顕微鏡 :STM(Scanning Tunnelling Microscope)
・原子間力顕微鏡:AFM(Atomic Force Microscope)
の2種類があります。
走査トンネル顕微鏡(STM:Scanning Tunnelling Microscope)とは?
下の図2のように、鋭い先端を持つ「探針」を見たい物に近づけて、物を見ます(計測します)が、原子構造に加えて、原子レベルの空間分解能で試料の状態の情報を得ることができます。
光学顕微鏡や電子顕微鏡と同じように電子の波の性質を使いますが、図に示すとおり、それらとは全く異なる原理によります。
【図2】
↑走査トンネル顕微鏡(STM)の模式図
探針は先端に原子が1個という極微構造を持つもので、これを試料(見たい物)に1nm程度の距離まで近付け、試料と探針の間に数10mVから1V程度の電圧を印加すると、1nA程度の電流が流れます。
電気のスイッチなどから考えられるように、普通は導体の間に隙間があると電流は流れないのですが、このスケールになると「トンネル電流」と呼ばれる電流が流れます。
これは、ナノメートルの世界では、中学や高校で習ったなじみのあるニュートン力学とはちょっと違う、量子力学という物理の規則が働いて、隙間があっても、まるでそこにトンネルがあるかのように電子が移動するのです。量子力学的な現象を代表する効果の一つで、「トンネル効果」と呼びます。
トンネル電流の大きさは、試料と探針先端の間隙の距離に非常に敏感で、距離が0.1nm (1Å)、すなわち「原子1個分」ほど変化すると電流が一桁変化します。
そこで、間隙の距離が一定になるように探針の高さを制御しながら探針を試料表面に沿って精密に走査(スキャン)し、探針先端の位置の変化(凹凸)を記録すると、試料表面の原子の3次元的な凹凸を精密に再現できることになります。
探針の位置制御には、ピエゾ素子と呼ばれる、印加する電圧により長さが変化し、その値を精密に調整可能な素子を用います。
図3は、代表的な半導体材料であるシリコン(Si)清浄表面の原子構造をSTMで計測した構造を再現した原子像です。走査した各点での探針位置と高さのデータから原子構造の画像を作っています。
一つ一つの白いつぶつぶがSi原子で、きれいに配列する様子が見られます。
【図3】

↑STMで見たシリコン清浄表面の原子構造。一つ一つの白いつぶつぶがSi原子で、きれいに配列している様子が見られます。通常の結晶構造の7倍の周期を持つことから、7x7構造と呼ばれています。
STMでは何を見ているのか?
「図4」は、図3を拡大したものです。
【図4】
原子のモデルとして太陽系のように、原子核の周りを電子がくるくる回っている絵が描かれた図を教科書などで目にしますが、実際には、電子は雲のように原子核の周りに確率的に広がって存在しています。
1nmまで拡大すると図4のようにもやっとしていますが、これは、それぞれの原子の周りに局在した電子の「雲」です。
量子力学で説明される原子の理論モデルでは、陽子や中性子からなる原子核と、その周りに広がる確率的な電子の「雲」から構成される、となっています。
STMを使うと、こうした電子がトンネル電流として測定されることから、STM像では原子の周りに局在した電子の様子(状態)を見ていることになります。
原子が見えるとはいえ、実際は、こうして電子の様子を計測していることから、STMを使うと、物質の電子の状態や特性(物質の性質を生み出す基本の特徴)を、原子1個のレベルの分解能で調べることができるのです。
例えば、試料の特定の場所を選んで、印加する電圧を変化させ、トンネル電流の値が変化する様子を調べれば、試料の局所的な電子状態(局所電子状態密度と呼びますが、詳細は割愛します)の情報を原子スケールの空間分解能で得ることができます。
原子間力顕微鏡(AFM:Atomic Force Microscope)とは?
もう一つの「原子間力顕微鏡」もご紹介しましょう。
AFMでは、探針を板バネ(カンチレバー)に付け、これを試料に沿って走査するという仕組みになっています。
板バネのばね定数を調べておけば、板バネの曲がり具合から、試料と探針の間に働く力を測定することができます。
STMでは、トンネル電流一定として試料表面を走査しましたが、AFMでは、力一定として走査すれば、力一定の表面の像(原子間力像)が得られることになります。
場所を選択して、探針と試料間の距離を変化させ、力の変化の大きさを読み取れば、探針と試料の間に働く力の詳細を調べることができます(図5)。
【図5】
↑原子間力顕微鏡(AFM)の原理を示す模式図です。バネ定数が分かったカンチレバー(先端に探針を取り付けた板バネ)を試料に近づけ、カンチレバーが上(斥力の場合)下(引力の場合)にたわむ量をレーザー光の反射角度の大きさから見積もることで、試料と探針の間に働く力の情報が得られます。
したがって、探針先端の原子構造などが分かっていれば、力の変化を通して、探針の真下の試料の状態を調べられることになります。
高感度の測定では、カンチレバーを振動させながら試料に近づけ、共振周波数や振幅の変化を測定することで、探針と試料の間に働く力を高精度に定めることができます。
さらに、試料表面に沿って探針を走査し、それぞれの場所で得られる力の大きさを画像化することで、試料の原子構造や、試料の固さの分布を可視化(目に見えるように)することも可能になります。
このAFMを使っても「nmの世界」を見ることができます。
例えば図6は、実際にAFMで見たDNAの画像です。
【図6】

↑通常の右巻きDNAと特殊な左巻きDNAのAFM像(左)とモデル図(右)。赤色と青色の矢印は、それぞれのDNAの主/副溝を示している(画像提供:『京都大学』)。DNAのサイズは生物によるが、直径は2nm程度(図1参照)、人の場合、長さは平均数cmで、一つの細胞のDNAをつなげると2m程になる。
⇒参照・引用元:『京都大学』公式サイト「左巻きDNAの2重らせん構造の直接可視化に成功 -液中原子間力顕微鏡によるDNA高分解能観察とその電荷分布計測-」
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2019-05-17-0
例えば、DNAやその周りに並んでいる水分子の構造、また、表面に分布する電荷の様子などを高い空間分解能で見ることも可能です。
STM(走査トンネル顕微鏡)とAFM(原子間力顕微鏡)の分解能とは
STM(走査トンネル顕微鏡)とAFM(原子間力顕微鏡)のおよその空間分解能をまとめると、以下のようになります。
横方向の分解能が縦方向に比べて落ちるのは、探針の位置をそれら方向に変化させたとき、試料との間の相互作用(トンネル電流や力)が変化する大きさや領域の広さの違いなどによります。
・STM(走査トンネル顕微鏡)の分解能
横方向:0.1nm
垂直方向:0.01nm
・AFM(原子間力顕微鏡)の分解能
横方向:1nm
垂直方向:0.1nmナノメートル以下
もっと小さい世界を見ることはできる?
上記のとおり、顕微鏡を使って原子を見ることはできます。では、例えば「原子核の中を見ることはできないのか?」――というと「できます」。
大きな宇宙の成り立ちなど、いわば、宇宙や物質の起源の秘密を、小さな世界を探ることで解明しようとする多くの実験が行われています。
ただ、光学顕微鏡のイメージとは、さらに異なる世界になります。
これは、「高エネルギー加速器」を使って陽子や電子などを衝突させ、対象の構造や、壊れたもの、また、その壊れ方を見て、中がどうなっているのか、それら物質の性質はどうなっているのか、を探るという手法です。
原子核の中、「素粒子の世界」を見ようというもので、「1,000兆分の1m:1フェムトm」より小さな極微の世界を分析します。
素粒子とは、物質を構成する基本的な粒子のことです。素粒子に質量を与える粒子や力を媒介する粒子も含まれます。
データは、構造を映す画像ではなく、物質の要素が異なる状態に変化していく様子や、消えてなくなる様子を示すもので、通常の顕微鏡のイメージではありません。
しかし、「何をどこまで、どのように見るか」の意味を広く考えると、見ようと思えば、原子核の中の世界、素粒子の世界まで見えるようになっているのです。
異なる分解能を「掛け合わせて」見られないか?
ここで、再度「分解能」について考えてみましょう。
分解能では、例えば空間、時間、エネルギー、力、感度、精度などが思いつきます。
「空間」についての分解能というのは、近接する対象を分離、区別して見えるかといったことですが、「時間」的な分解能というのはどこまで速い変化を捉えることができるかといったことになります。
また、原子や電子がどれ程のエネルギーを持っているか、といった分解能もあります。
電子のエネルギーは、素子の機能や化学反応などに関わります。どこまで微弱な信号を雑音から分離し、どれほど高い精度で測定できるか、といったことも、顕微鏡としての重要な要素でしょう。
先に「空間的な分解能」(近接した空間の2点を区別できる分解能)として、人間の肉眼ではおよそ0.1mm、光学顕微鏡ではおよそ0.2μm、電子顕微鏡ではおよそ、0.1nmとしましたが、
時間の分解能(どれほど速い現象を追えるか)を考えると、例えば、人の目の分解能は約50msから100ms程度で、この時間よりも短い光の点滅は、連続点灯しているように知覚されます。
例えば、蛍光灯の光はインバータ式を除き、商用電源周波数が60Hzの地域の場合は、1秒間に120回点滅していますが、普通はチラツキを感じません。
「どこまで小さい物が見えるのか」という質問は、空間的な分解能についての問いでしょう。
これまで紹介してきましたように、「どのように見るか」を広く捉えた顕微鏡では、原子レベルの観察だけでなく、原子レベルの分解能で電子状態を調べることも可能になっています。
さらに、表面の原子を取り除いて別の原子に入れ替え、その効果を調べたり、二つの分子が結合する力の相互作用を直接調べたり、あるいは原子1個のレベルで化学結合力を評価したり、といったことが実現しています。
しかし、さらにもう一歩進んで考えると――、
「高い空間的分解能」と「高い時間的分解能」を一緒にして「見る」ことができないか?
――というのが、「何をどこまで、どのように」の次の課題になります。
実は、これこそが最先端の顕微鏡開発とそれを用いた研究の場で行われていることです。
「空間的分解能」と「時間的分解能」を掛け合わせて見る
AFM(原子間力顕微鏡)のカンチレバーを高速に走査して(実際には試料ステージの方の位置制御など)試料のダイナミクスを観察する高速AFMと呼ばれる技術があります。
これを用いると、筋肉を伸び縮みさせるタンパク質分子の動きや、細胞膜を通して細胞の中に機能分子が入っていく様子などを見ることができるようになっています(図7)。
こうした動画はミリ秒単位でそれほど時間分解能は高くないですが、これまでにない多くの新しい情報が得られています。
【図7】

↑活動中のタンパク質分子の姿を直接可視化できるようになっています。
⇒参照・引用元:『NanoLSI』「高速原子間力顕微鏡(高速AFM):動くタンパク質分子を直接可視化」
https://nanolsi.kanazawa-u.ac.jp/researcher/toshio-ando/toshio-ando-page/
他に、フェムト秒幅の超短パルス光を活用する量子光学の技術を組み合わせる方法で、原理的には1,000兆分の1秒(1fs、フェムト秒)の単位で起こっている局所現象を捉えることも可能になってきています(図8、図9、図10)。
例えば、「1nmの空間分解能」かつ「1フェムト秒(1,000兆分の1秒)の時間分解能」で極微の世界の局所電子状態の変化をトンネル電流や力の変化として捉えることができるところまできているのです。
【図8】

↑超短パルス光レーザーとSTMを組み合わせた時間STMのイメージ図。
【図9】
↑金基板上にC60を蒸着して作製した薄膜構造に、光を照射して金基板から注入した電子が、時間と共に金基板に戻っていく(緩和していく)様子を時間分解測定した様子です。
ACS Photonics 8,315(2021)
【図10】

↑上記の時間分解STMにより計測した光照射にともなうMoTe2試料のフェムト秒領域での相変化がこのように計測できます。
ACS Photonics9,9,3156(2022).
新しい顕微鏡によるナノ世界の計測が新しい世界を開く!
「極微の空間分解能 × 極微の時間的分解能」という新たな世界が実現されており、「静止画ではなく、ダイナミクスを動的に見る」ことが次世代を開くことにつながります。
例えば、最近、半導体開発のニュースを目にすることが多いですが、次世代半導体は2nmプロセス(機能の基本的な構造が2nmの領域)という極微の世界です。
半導体は不純物原子を入れて機能を制御しますが、不純物原子一個の位置やその周囲の環境が特性に大きく影響してしまいます。
超高速素子として働かせるには光との相互作用を活用することも重要で、こうした光電素子(光と電子を絡めた機能を使う素子)の様子を正しく評価するには、光との相互作用を含めて高い空間・時間分解能を併せ持つ顕微鏡が必要不可欠になります。
光触媒※などの機能解析や高効率電池の開発にも、時間・空間両領域においてナノスケール単位での計測が必要不可欠です。
※光触媒:例えば、壁に吹きかけておけば、紫外線が当たると、光反応を利用して壁の表面の汚れを分解してきれいにしてくれる物質。既に実用化されている。
われわれは、フェムト秒領域の超短パルス光を発信するレーザーをSTMやAFMと組み合わせることでこうした夢の顕微鏡を実現してきました。研究室レベルでは高度な技術が必要とされますが、簡易化して、より多くの人に扱えるよう製品化もされています(図11)。
【図11】

↑次世代時間分解走査プローブ顕微鏡。レーザーシステムの制御を簡易化して、より簡便に活用することを実現。すでに製品化されています。
Imaging & Microscpy 26,34-35(2024)
医療の世界でも、ナノカプセルといって、普通は不安定な物質を極微のカプセル(20~100nm)で一つにくるみ、これを必要なところにもっていって治療する――といったケースが考えられています。
薬の効果としては平均的な作用が働きますが、薬をデザインしたり効き目を調べたりするには、個々の分子の動作を調べることが大切で、半導体などと同様に極微の世界を計測する手段が必要になります。
細胞のレベルでのがんの先端治療においても、細胞の膜の厚さが7nmとか、ミトコンドリアが100nmとかの世界で、細胞の中でどんな反応が起こっているのかを調べなければなりません。
一般に、細胞の中の生命活動は数秒とかミリ秒とか遅いとされていますが、それぞれの過程を誘起する電子構造の変化や光との相互作用は本顕微鏡を必要とする時間領域になります。
次世代を開くには「空間 × 時間の極微の世界」を観測する必要がある!
現在では、「原子レベルの空間分解能で、1,000兆分の1秒レベルの超高速ダイナミクスを見ること」が求められています。
対象には、
量子素子
反応制御
ナノマシン
ナノマテリアル
単原子分子熱力学
エネルギー変換
分子素子
ドラッグデリバリー
超高速素子
量子センサー
など多様な分野が含まれます。
こうした機能を生み出し活用していくためには、紹介してきたような新しい顕微鏡技術が必要不可欠です。
電子がどんな動きをしているのか、分子の結合状態はどうなっているのか、そこでどんな変化が生じているのかなどを調べることで、初めて量子力学で表される基本的な世界で起こるさまざまなダイナミクスの理解と制御が可能になり、新しい世の中を創生することができます。
これまでに見えなかった新しい世界が見えてきてはいますが、まだまだ乗り越えるべき課題は多くあります。
現在の技術をさらに発展させ、さらなる夢の実現を目指して開発を進めている――というのが最先端の現状です。
ぜひ多くの大学生の皆さんにもこうした世界に興味を持っていただき、さまざまな分野で全く新しい科学技術を生み出し発展させることで、将来、より豊かな夢のある幸せな社会が広がるよう、思う存分に活躍してほしいと心より願っています。
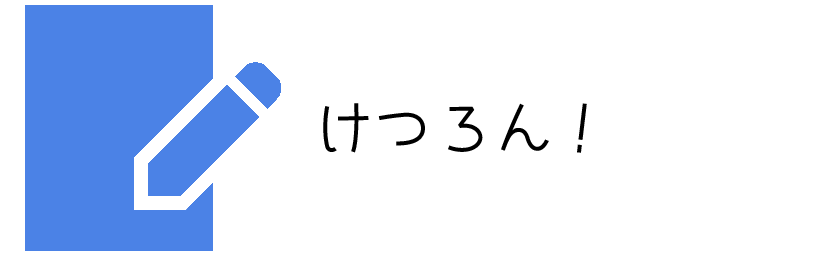
◇けつろん!
「顕微鏡でどこまで小さい物が見えますか?」という質問に対しては、
今や、原子1個レベルの構造が見えるだけでなく、そうした高い空間分解能で、さまざまな機能、例えば光照射をしたことによる、材料の中の電子の超高速ダイナミクスまで捉えることができます
というのが回答になるのです。
重川先生が取り組んでいらっしゃる最先端の顕微鏡は、大変に興味深く、かつ次世代の展開に欠かすことのできないものです。大学生読者の皆さんもぜひ後に続いてください。
◇こたえてくれたせんせい
重川秀実
Profile
『筑波大学』数理物質科学研究科 教授。
東京大学大学院工学研究科物理工学専攻博士課程中退、専門は、プローブ顕微鏡と量子光学を用いた極限計測とナノ科学。2019年(令和1年)紫綬褒章受賞など。
⇒『筑波大学 重川研究室』
https://dora.bk.tsukuba.ac.jp/ja/index.html
文:高橋モータース@dcp
編集:学生の窓口編集部