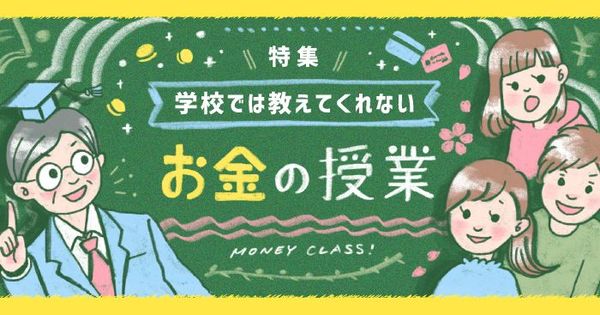債券の仕組みとは!?配当はどれくらいか知っておこう!|学校では教えてくれない「お金の授業」
今回は債権の仕組みや配当について詳しく解説をしていきます。資産運用を考える際に株式投資と並行して紹介されるのが債権です。株式投資は企業の株を購入するためイメージが湧きやすいですが、債権はイマイチイメージが湧きにくいかもしれません。
この記事では、これから投資を始める方を対象に、債権についてわかりやすく解説します。最後まで読んで、債権投資について理解を深めてみてください。

債券とは?
債券とは、国や企業が資金調達をする際に発行する証券のことです。ここでは、その仕組みと株式との違いについて解説します。
債券の仕組み
債券を購入するということは、その国や企業にお金を貸すということになります。
例えば国債を購入すると、その国にお金を貸したということになり、10年国債であれば10年後に国は投資家に利息をつけて元本を返却します。
この利息が投資家の利益の源泉になります。
また、満期を待たずに市場で売却することもできます。元本よりも高く売却できれば利益になりますが、逆に元本よりも低い値段でしか売れなかった場合は損失が発生します。
債券と株式は違う?
債券と株式は投資商品ではありますが、その特徴は全く異なります。
債券は、国や企業にお金を貸す借用証書です。
そのため、借りたお金は一定期間後に額面金額に利息を付けて返済をする必要があります。
一方、株式は企業が資金調達のために株券を発行して、それを購入することで株主となり、企業に資金を提供することができます。
企業はその資金を使い事業活動を行うことで、得た利益を出資額に応じて株主に配当します。株式は出資をしてもらうことを目的としているため、株主が投じた資金を返済する必要はありません。
債券の方が元本が返済されるため、投資家にとっては安全に思えるかも知れません。ただし、債券を発行した国や企業が元本や利息の返済をすることができないデフォルト(債務不履行)という状態になった場合、元本が一部、または全く返済されないリスクがあります。
債券も株式も需要に応じて金額が変動します。その値動きを利用して収益を得ることもできます。
債券や株式の売買差益で収益を得る方法を「キャピタルゲイン」といい、利息や株式の配当金の収益のことを「インカムゲイン」といいます。
| 株式 | 債券 | |
| 還元義務 | なし | あり |
| インカムゲイン | 配当 | 利息 |
| キャピタルゲイン | 株式価格の値差 | 償還前の途中売却による収益 |
| リスク | ハイリスクハイリターン | ローリスクローリターン または ミドルリスクミドルリターン |
債券にも種類がある
債券は発行体によって、さまざまな種類があります。
また、日本国内で発行されるとは限らず、海外で発行する債券や、国や企業が債券を発行することがあります。それぞれのケースについて詳しく解説します。
国内債券と外国債券
債券は国内の発行体以外のものを購入することも可能です。
日本国内において円建てで発行する債券を国内債と呼び、発行体、発行通貨、発行市場のいずれかが外国、または外国の通貨である債券を外国債券といいます。
外国債券は金利が高く、高い利息を得ることが期待できますが、為替リスクの影響を受けるため、国内債券よりもリスクが高くなります。為替リスクに関しては後述します。
公共債と民間債
債券の発行体には国や地方自治体、政府機関などがあり、これらを総称して公共債といいます。公共債のうち、国が発行するものは国債、地方自治体が発行するものを地方債、政府機関が発行するものを政府機関債といいます。
外国債券には、各国が発行する債券の他に、政府や政府機関が発行するソブリン債や、国単位ではなく世界の各地域の経済発展を目的として世界各国が協力して設立した開発金融機関の発行する国際機関債などがあります。
利息の有無
債券は利息の支払い方式でも分類することができます。ここでは、利付債と割引債をご紹介します。
【利付債】
債券の利息が定期的に支払われる、債券市場で一般的な利息の支払い方式です。定められた期間ごと(例えば、半年ごとや1年ごとなど)に、債券の額面に対する利息(クーポン)が投資家に支払われます。
【例:額面100万円、1年後に3万円の利息を受け取る利付債】
(3万円÷100万円 )×100 = 3%
【割引債】
保有期間中の利払いはなく、満期時に額面金額で償還されます。
【例:額面100万円、97万円発行された割引債】
償還時は額面100万円を受け取ることができるため、100-97万 = 3万円となります。
(3万円÷100万円)×100 = 3%
債券投資の配当はどれくらい?
債券投資は株式よりもリスクもリターンも少ない資産運用方法になりますが、債券投資はどれくらいの配当(利回り)になるのでしょうか。用語をまずは理解して、具体的な商品について紹介していきます。
利率と利回りの違い
利率とは、額面金額に対して毎年受け取ることができる利子の割合をいいます。
通常、利率というと表面利率のことを表します。
一方、利回りとは、投資金額と利息を合計した毎年の収益の割合のことをいいます。
【例:額面金額100万円、利率3%の債券を100万円で購入。5年間継続した場合】
(100万円×利率3%(※1))×5年間 = 15万円
(※1)額面に対する利子の割合は3%です
15万円÷5年間 = 3万円÷100万円(購入価格) = 利回り3%
この場合は、利率も利回りも3%。
【例:額面金額100万円、利率3%の債券を100万円で購入。5年後に105万円で売却】
(100万円×利率3%)×5年間 = 15万円
100万円で購入した債券が105万円で売れたので利息の他にさらに5万円プラス。
利益は15万円+5万円 = 20万円
20万円÷5年間 = 4万円÷100万円(購入価格) = 利回り4%
この場合は利率3%で、利回り4%となります。
実際の配当例
まず、個人でも購入できる「日本国債10年」を100万円で2024年2月14日に購入した場合、8月15日に2000円(適用金利0.40%)。年間で4000円の利息を受け取ることができます。
(参考:https://www.mof.go.jp/jgbs/individual/kojinmuke/main/outline/hendou/)
その他にも、米国債10年(4.304%*)、豪(オーストラリア)国債10年(4.267%*)など、金利が高くとても魅力的な商品があります。
※2024年2月14日現在の利回り
このように商品を見ると金利が高くとても魅力的な商品があります。
これはそれぐらいの利回りまたは金利で募集をしないと、買い手が見つからない、リスクの高い商品と考えることもできます。
債券投資のリスク
債券投資は一般的に株式投資よりもリスクが低い傾向があります。
どのようなことが発生すると債券にリスクが生じるのでしょうか。以下では、これらのリスクの要因について解説していきます。
価格変動リスク
債券は償還まで待たなくても、途中で売却をすることができます。購入時よりも債券価格が下がっている状態で売却をすれば損失が生じますが、逆に債権価格が上昇している場合は利益が発生します。
また、金利が上昇すると債券価格は下がり、金利が低下すると債券価格が上昇する傾向があります。金利は国の金利政策や経済状況によって影響を受けるため、その変動は債券価格にも影響を与えます。
| 債券価格 | 金利 |
| 債券価格は下がる | 上昇 |
| 債券価格は下がる | 低下 |
信用リスク
信用リスクとは、国債の場合は財政難。社債の場合は経営不振など、発行体が債務不履行(利息や元本の支払いを約束通り行えなくなること)に陥る可能性が高まるリスクのことです。
債券価格はこのような信用リスクに応じて変動します。一般的には、リスクが高まると債券価格は下がり、金利は上昇します。逆に、リスクが低下すると債券価格は上昇し、金利は下がる傾向があります。
為替変動リスク
外国債券を外貨で購入し、外貨で受け取る場合は、為替レートの変動によって受け取る日本円額が影響を受けることに留意する必要があります。以下はその事例です。
【1ドル100円の時に100万円分の外国債券を購入】
米国債に10,000ドル投資をして1年後2%の利益が出て、10,200ドルになりました。
10,200ドルを円に交換するときの為替レート
- ・1ドル100円の場合 10,200円×100 = 1,020,000円
- ・1ドル110円の場合 10,200円×110 = 1,122,000円
- ・1ドル 90円の場合 10,200円× 90 = 918,000円
このように外国債券は、運用している間に外貨建ての全額では利益が出ていたとしても、円に交換するときの為替レートによってはマイナスになってしまうことがあります。
したがって、外国債券を取引する場合には、為替リスクにも十分な注意を払う必要があります。
まとめ
債券は、国や企業が資金調達をする際に発行する証券です。
国債を購入すれば、その国にお金を貸したという扱いになり、社債を購入すればその企業にお金を貸したという扱いになります。また、満期まで持っていれば元本と利息を受け取ることができます。
債券はさまざまな発行体が発行しており、国が発行する国債、企業が発行する社債、その他政府債などがあります。
さらに、発行体、発行通貨、発行市場のいずれかが海外となっている外国債券もあり、それぞれのリスクに応じて利率、利回りも異なります。
債券も償還前に売買をすることができ、値動きをするために価格変動リスクがあります。その他、発行体の信用リスクによっても価格や金利は変動し、外国債券の場合は円に交換する際の為替リスクにも注意を払う必要があります。
債権への投資を始めるという方は、どのような債権を保有するかを検討し仕組みやリスクについて理解してから始めるようにしていきましょう。

文:金子 賢司
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。 以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、 年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。 <保有資格>CFP、住宅ローンアドバイザー、生命保険協会認定FP、損保プランナー 公式HP
制作:Media Beats
イラスト・編集:watasack(渡邊 桜)
他の“学校では教えてくれない「お金の授業」”もチェック!