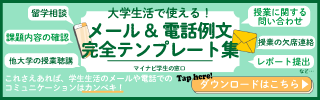意識が高くなりすぎる「大二病」……かかってしまう原因は? 心理学者に聞いてみた #もやもや解決ゼミ
日常に潜む「お悩み・ギモン」=「もやもや」を学術的に解決するもやもや解決ゼミ。
「中二病」という言葉がありますが、「大二病」という言葉は知っていますか? 大学二年生ぐらいの時期にやたらに意識が高くなり、言動が変化してしまうことを指します。
このような大二病はなぜ起こるのでしょうか?
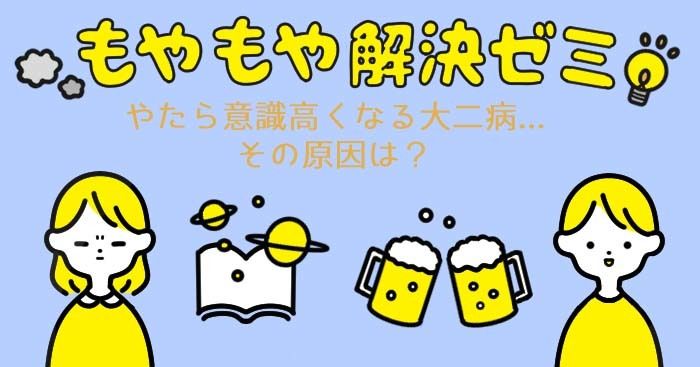
立教大学 現代心理学部映像身体学科の香山リカ教授に聞きました! 香山先生は精神科医としての活動も行っています。
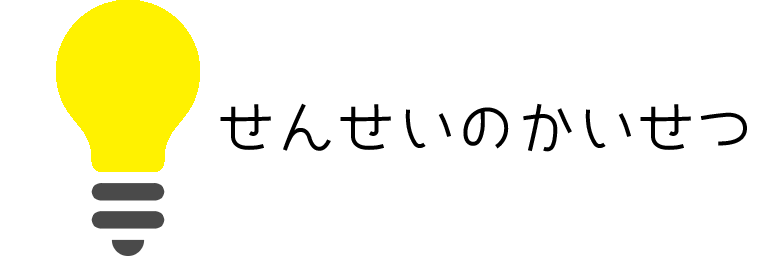
「意識が高くなる」のは大学生になってからの一つの生活パターン
大学に入り受験から解放されたときに待っているのが、「何のために勉強するの?」という悩みです。高校まではとにかく受験というはっきりした目標があったため、勉強のモチベーションも持ちやすかったと思います。
また、逆に家族の問題や恋愛についても、深入りしそうになったときには、「いやいや、今は受験に集中しなければ」と頭を切り替えることもできたはずです。
ところが、めでたく大学に受かったら、状況は一変。「なぜ勉強するの?」という問いにはっきりした答えはないし、家族や彼氏、彼女のことでも好きなだけ悩んだり考えたりする時間もできてしまいました。
そういう中で、頭や心をすっきり整理して、勉強や運動などにこれまでどおり専念できる人など、ほぼ皆無と言ってもよいでしょう。
それからどういう学生生活になるかには、大きく分けて2パターンあります。

一つは、「もう勉強する目標もなくなったし、とりあえず楽しくやろう!」と遊びやバイトなど、目の前のことにあれこれ手を出すタイプ。
もう一つは、時間ができて具体的な目標がなくなった分、思いきり抽象的なことや難しいこと、世の中のことなどに思考がシフトするタイプです。これが大二病といわれるものではないでしょうか。
悩む時期も大切なもの
「生きるって何?」「どうして世の中には格差があるの?」「時間に始まりと終わりはあるんだろうか?」などなど、哲学的な問いや本質的な問いにとらわれ、日常のことで一喜一憂している友達が幼稚で愚かに見えて、つい「キミはいつも幸せそうでいいよね……」などと冷笑してしまうこともあります。
私は、「こういう時期は人間の成長にとって必要なもので、大いに考えたり悩んだりしてほしい」と考えています。
ただ、頭の中でグルグル考えたり、SNSで誰かとケンカしたりしてもあまり発展性がないので、ちょっと年寄りくさいアドバイスですが、古典と呼ばれる本を読んだり映画を見たりしてほしいな、とも思うのです。
あと、いくら意識が高くなっても、人にはそれぞれ価値観や生活のスタイルがあるので、友達をバカにしたり冷笑したりするのはやめておきましょう。就活が始まり、意識を高くばかりしていられなくなったときには、またその友達と情報交換もしなければならなくなるかもしれません。
私は学生時代を過ごした後、「人生って何?」「人間って何のために生まれたの?」などと悩む人と向き合い、話し合う精神科医になったので、ある意味、一生意識高い系の世界で生きていると言ってもよいでしょう。
「いつまでも若くていいね」とまわりからは皮肉を言われることもありますが、悩み続ける人生も悪くないと思ってます。今「大二病」に陥ってる学生たちの中からも、将来の哲学者や精神科医が生まれてほしいな、と期待したい気持ちです。
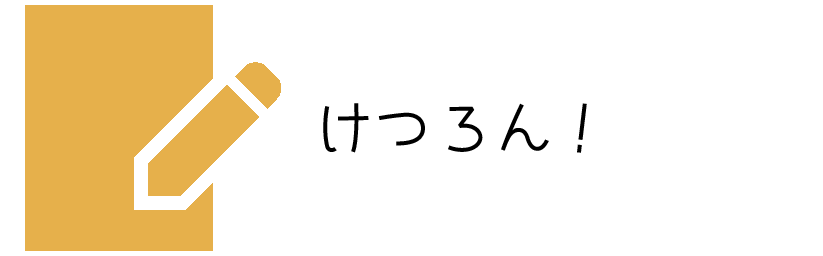
「大二病」といわれる、大学二年生ぐらいになると妙に意識が高くなってしまう状態は、香山先生によれば、これは人生にとって必要なものであるとのこと。二年生になると大学にも慣れ、時間にも余裕があるでしょう。香山先生のアドバイスにあるとおり、この時期に大いに考え、悩むのがよいのではないでしょうか。
イラスト:小駒冬
文:高橋モータース@dcp
教えてくれた先生

精神科医・立教大学現代心理学部映像身体学科教授。
1960年北海道生まれ。東京医科大卒。
豊富な臨床経験を生かして、現代人の心の問題を中心にさまざまなメディアで発言を続けている。専門は精神病理学。