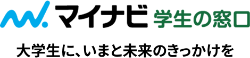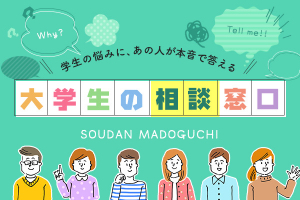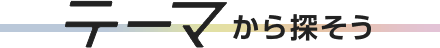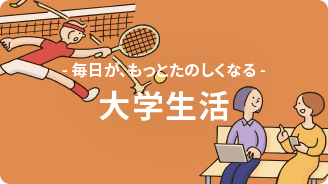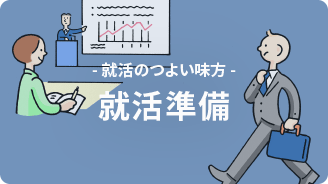22歳で世界を獲った映画監督が、広告会社に就職した理由
カンヌ・ベルリン・ベネチアに続いて権威のある国際映画祭とされるスペインのサンセバスチャン国際映画祭。そこで史上最年少・22歳で最優秀新人監督賞を受賞した、新鋭映画監督の奥山大史(おくやま・ひろし)さん。受賞作品『僕はイエス様が嫌い』が5月31日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほか、日本で公開となります。
本作の脚本は大学在学中に制作し、今後も映画を制作したいと意気込む奥山監督が選んだ就職先は「広告会社」。少し遠回りにも見える選択をしたのはなぜなのか。若き監督の就活と今後、そして本作の制作秘話について聞いてみました。
文:落合由希
写真:広ミノル
編集:学生の窓口編集部
誕生のきっかけは卒業制作
――本作は青山学院大学在学中に制作されたそうですが、昔から将来の夢は映画監督だったのでしょうか?
高校生の終わりごろから「映画を作りたいな」と思い始めました。その前は演劇が好きで、ずっと演劇を見てました。そこからだんだん映像にも手を出し始めたっていう感じですね。
――本作は大学の卒業制作として撮影されたんですよね?
そうなんですけど、作品として完成したのは会社に入ってからなんです。卒業制作としてこの作品を提出したわけではなくて、企画というか脚本を卒論として出しました。なので、作品自体は卒業制作と言い切れるものではないというか。でも、自分の中では「大学の集大成」として作った感じです。
「映画制作会社」はない。だから道に迷う。
――奥山監督の就職活動も、ごく一般的なものだったんですか?
そうですね。インターンもしていましたし、就活中も確実に受かるところをおさえとこうみたいな感じでした。でも、「映画を作れる会社」というのは意識してました。長編映画なんて大学時代には撮れないだろうから、会社に入ってから長編映画を撮らせてくれる機会をくれるようなところに行きたいなぁと思って。テレビの制作会社とか、広告の制作会社なんかを受けてました。
――仕事として映像制作ができる会社を探してたんですね。
でも結局、「映画制作会社」」ってちゃんと謳ってるところってほぼないに近くて。それは単純に、映画だけで会社としてお金を回していくのが厳しい現実があるからだと思うんです。だから「映画を作りたい!」と思う学生は、絶対1回道に迷うタイミングがあるだろうなって思います。
――奥山監督は現在、広告会社で会社員として働かれていて、映画制作とはまた違った仕事もされていると思います。
そうですね。今は広告を作る会社にいて、映画を作るのとは全然違います。僕からしたら何から何まで違うんですけど、でも唯一変わらないこととしては“モノを作る”ということ。そこは変わらないからこそ、それぞれから違うことを学べるので、結果的に映画を作る上でも、広告を作る上でも、いい効果があればなと考えてます。
――監督業と会社員の両立はかなり大変なのでは?
そうですね。大変……なんじゃないですかね。入社してからはまだ映画を作れていないので、なんとも言えないですけど。でも、本来なら会社で通常の業務をすべき時間に、こうして作品に関する取材をさせてもらえているので、そういう意味では理解してくださってるのかなぁと思います。
実体験からの「礼拝あるある」を散りばめた
――今作は奥山監督の実体験をモチーフに制作されたそうですが、実体験を映画にしようと思ったのはなぜですか?
「実体験を映画にしよう」というところからスタートしたというよりは、まずは会社に入る前に映画を作りたいな、というのが最初にありました。いくつか題材を考えていて、その題材のひとつに小さい頃の思い出を映画として残しておこうっていうのがあったんです。最終的にそれを選んだのは、あえて言うと「面白くなる」と思ったからです。
とはいえ、リスキーだなと思っていたテーマでもあったので、迷いもありました。一度プロットを書いたときは「やっぱこれじゃないんじゃないかな」とも思いましたし。あまりにも自分のことすぎて「自分が体験したことを見てください!」としか見えなくて……。それでどうやったら多くの人に楽しんでもらえるのかなぁって悩んでた時期もありました。そこから「ちっちゃいイエス様を出せばわかりやすくていいんじゃないかな」と思い始めてからは、結構トントン拍子に思いついて……っていう感じでしたね。
――イエス様は実体験というわけではないんですね。
そうですね、僕にはちっちゃいイエス様は見えてなかったです(笑)。でも僕も子どもの頃は毎日礼拝に行ってたんですけど、長いんですよ、牧師先生の話が。だから「ここで突然神様が降りてきて、先生に『君、なに言ってんの?』とか言ってくれないかなぁ」とか、そういう想像はよくしていましたね。なので“礼拝中に子どもが妄想する”というのは、描きたかったモチーフのひとつでした。
――子どもたちにとっては、きっとあるあるなんですね。
作中でも、お母さんに「お祈り中なんだからちゃんとしなさい」みたいなことを言われて「だってユラが目を開けてたんだもん」って言い返すと、「(ユラが)目を開けてたことがわかるってことは、あなたも目を開けてたってことでしょ?」っていうシーンがありますけど、あのくだりって、小学校の頃、先生に何百回言われたかわからないぐらいなんですよ(笑)。
他にも賛美歌の選び方とか、聖句の選び方なんかもある程度こだわったつもりなので、そのあたりは、礼拝などキリスト教に触れたことのある人だったら「あぁ、わかるなぁ」「懐かしいなぁ」って思ってくれると思います。
脚本~監督~編集まで担当するからこそのこだわり
――制作するにあたって、特にこだわった部分はありますか?
「音」にはすごくこだわったつもりです。静かな映画なので、小さい音が逆に目立つんですよ。たとえば、静かだからこそ、このぐらい足音は聞こえていいんじゃないかな? でもこんなに聞こえてたらさすがにおかしいかな? とか。どれくらい「足音」を足すかということについても、バランスをすごく気にしながら作っていきました。大きい音が鳴るシーンも中にはあったので、それをどのぐらい大きくして印象づけるかということも考えました。
――大きな音が鳴るシーンは、たしかにすごくビックリしました(笑)。
あと、やっぱり撮影にもこだわりました。なるべく絵コンテを作らずに撮影を行ったんです。撮影監督をしていた時期になんとなく学んだことなんですけど、コンテを書いていくと現場がそれに縛られちゃって、周りのスタッフもそのコンテの絵に近づけることに精一杯になってしまう。そうしないために、コンテもカット割も一切共有せず、その場で子どもがやってくれたお芝居を見て、どこから撮るのがいいのかなぁっていうのを考えていきました。「画」と「音」というのは作品の雰囲気を作る2大要素なので、そこはこだわったつもりです。
子役に対する演技指導法
――今作を作る中で、奥山監督がいちばん大切にしていたのはどんなところですか?
現場でいちばん大切にしたことは、演じてくれている子どもたちが楽しんでくれるようにすることです。やっぱり子どもがお芝居をしてくれる以上、彼らがすごく楽しんでやってくれないと映画を観てくれる人も楽しんでくれません。彼らに楽しんでもらえるように、どんなにイライラするようなことがあっても怒らず、常に笑顔を意識してました。
実際すごく優秀な子どもたちでやりやすかったんですけど、自然に楽しんでもらうためにも彼らには脚本を一切見せず、ストーリーもあまり伝えないようにしていました。サッカーをするシーンも、本当にサッカーをしてもらいました。
――ユラくん(佐藤結良)はとてもチャーミングな男の子ですが、彼を起用したいちばんの決め手は?
シンプルに言うと「いちばん撮りたくなった子」だったということになりますね。やはりある程度実体験からきた物語なので、自分にどこか通ずるものがあればいいなというのは考えていました。もちろんルックスとかではなく、おとなしいところだったり、でもテンションが上がるとすごい笑顔になってはしゃぐところだったり、大人に対して敬語でちょっと距離をとるところだったり……そういうところがすごく自分に似てる気がして、「やっぱ彼だな」ってなりました。
――撮影していて特に印象に残っているユラくんの演技は?
たくさんあるんですけど、ユラくんが初めて礼拝に行くシーンですかね。礼拝堂の中で最初はみんな立っていて、「座ってください」と言われたら全員座る、というだけのカット。撮影のときには気づかなかったのですが、編集のときに見返したら、初めて礼拝に参加したユラくんが、周りを見てから、ちょっとみんなより遅れて座っていたんです。すごい不慣れ感が出ていて、しかも浮いてて、転校生らしくて。「あぁ、上手だなぁ」って。そんな細かい演技ができることに感動しましたね。
小さいイエス様が、海外で受け入れられる理由
――特にお気に入りのシーンはありますか?
やっぱりイエス様が出てくるシーンは好きなところが多いですね。ワンカットワンカット、撮影していくのは大変と言えば大変なんですけど、チャド・マレーンさんがお芝居を上手にやってくださったので。
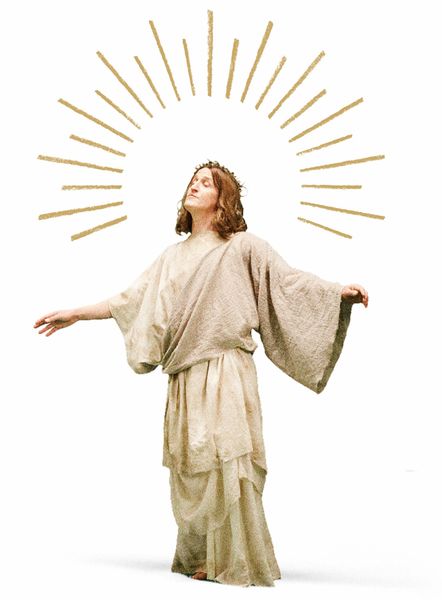 実は、何百回か見たらわかるかな? くらいの「隠れイエス様」が本編にはいるんですよ。
実は、何百回か見たらわかるかな? くらいの「隠れイエス様」が本編にはいるんですよ。
©2019 閉会宣言
――そうなんですか(笑)!?
予告編にも実はいるんですけど、全然見えないんです。探してくれたらうれしいです(笑)。「隠れイエス様を探せ!」やってほしいですね。
▲予告編動画
――チャドさんはすごくハマり役だと思ったのですが、演技面はいかがでしたか?
キャストは基本オーディションで選んだのですが、チャドさんはもう最初から「お願いします!」って頼みにいきました。チャドさん以外浮かばなかったんですよね。単純に見た目がイエス様っぽいなっていうのがあったので。アドリブもけっこうやってくださってます。
――セリフのない役でしたが、そのことについてチャドさんから何かツッコまれませんでしたか?
なかったですね。ただ、「僕オーストラリア人やけど、オーストラリア人がイエス様やることないと思うで」とは言われました。
――確かに(笑)。
海外の映画祭に行くと、やっぱりイエス様のシーンがいちばんウケるんです。サンセバスチャン映画祭で流したときも、そこがいちばんウケてましたし。「イエス様がよかった」ってよく言われましたね。
――キリスト教徒の方が見ると「不謹慎だ!」って感じる人もいるのかな? と思ったんですけど、みんな面白がってくれるんですね。
もしかすると心のどこかであまりよく思ってない人もいるかもしれないですけど、基本的にはすごく面白がってくれました。小さくなっていることや、周りに見えていないところなどからして、これは本当のイエス様ではなく、あくまでユラくんの「イマジネーションの産物」なんだということを理解してくださっているんだろうなと感じました。一定の評価もいただけたことを踏まえてもそう思います。
プレッシャーはない。むしろ、ここから
――若干22歳の若さで、しかも長編デビュー作でいきなり国際的に評価されて、今後へのプレッシャーなどはありますか?
作品が運よくたくさんの方々に届くものにできたんだなぁっていうだけで、それが次回作へのプレッシャーになる、というふうにはあまり考えてないですね。映画賞って、別に僕個人に対してのものじゃなくて、“作品”つまり関わってくれた人“みんな”に対しての賞だと思うので。
――不安を感じることもない?
そうですね。それよりも、ある程度評価された気がしたのに、国内の人はあんまり注目してないぞ? っていう不安のほうが……(笑)。公開が決まっていよいよだぞってなったときも、「サンセバスチャンって……?」みたいな人がやっぱり多いじゃないですか。だからむしろ「よし、これから頑張ろう!」という感じです。
学生時代のモヤモヤは、「形にする」
――では最後に、大学生読者に向けて一言メッセージをお願いします。
僕は、今作を作った今よりも、なんにも作ってなかった学生時代のほうが「オレは面白いものが作れる!」って思ってたんです。そのときは自信があるのに全然実行に移せてないみたいなモヤモヤがあって。今就職して、もちろん楽しいことだけではないですが、そう考えると学生時代がいちばん心がすさんでた気がしています。そういうモヤモヤを抱えている学生っていっぱいいる気がしていて。
だから、会社に入る前にこういう映画を作っといてよかったな、って思います。自分の実力もある程度わかりますし、形に残すことってすごく大事です。だからもしモヤモヤしてるんだったら、少しでも早く取り組んだほうがいいのかなって思いますね。なにかモノを作ることを目指すのであれば、とにかくぜひ早く行動にうつしてください!
文:落合由希
写真:広ミノル
編集:学生の窓口編集部
©2019 閉会宣言