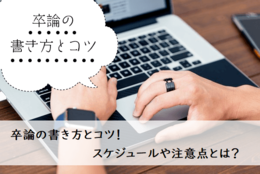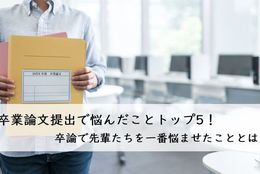卒論が終わらない! おすすめの卒業論文制作のコツ
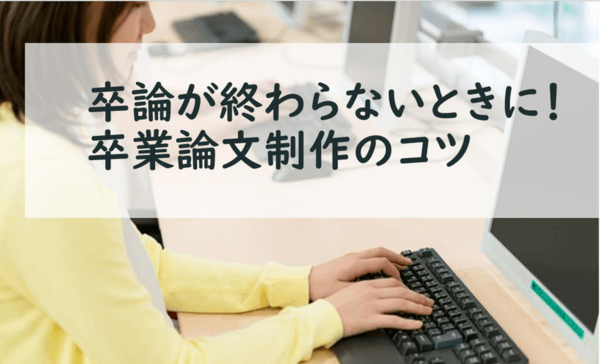
「卒論が終わらないと焦りに焦っている・・・」
もうすぐ卒業を控え、あとは卒論を提出するだけ。なのに、なかなか卒論が思うように進まない、という人もいるのではないでしょうか。
- 就職内定先から研修の連絡
- 単位認定試験
- サークルやアルバイト
など、4回生は意外と忙しいものですし、どれもおろそかにしたくないですよね。
そこで今回は、なかなか腰を据えて卒業論文を書く時間がない方、卒論が終わらないと悩んでいる方に対して、卒論を早く終わらせるためのコツを解説していきます。
この記事を読めば、つまずきがちなポイントやなるべく制作日数をかけないで卒論を制作していくことのできるコツが分かります。
▼こちらもチェック!
卒論執筆にかけた時間はどれぐらい? 今年卒業する大学生の卒論事情!
卒論の書き始めは何をすればいい? 早く終わらせるためのコツ

それでは早速、卒論の書き始めは何をすればいいのか、また卒論を早く終わらせるためのコツについてお伝えさせていただきます。
| 【卒論を早く終わらせるためのコツ】
|
卒業論文は、いうなれば推理小説のようなものです。
推理小説はたくさんの伏線があり、最後にその伏線を回収して「ああ、なるほど」と腑に落ちることが大事でしょう。探偵はこれが証拠というものを探さなくては始まりませんし、その証拠が今回の事件と関係があるというものでなければ読者からは納得されません。
同じように、卒業論文にとっての伏線は図表やデータ、グラフなど、そういうものが最後に論理的に結びついて、読者がなるほど腑に落ちれば卒業論文は完成します。
学術的になるため、
「卒論は難しい」
「終わらない!」
と感じる方も多いでしょう。
しかし、要領としては、推理小説を書くのと変わりがありません。気持ちを楽にして、まずは未完成の卒業論文を俯瞰してみてください。
その上で、最後の結末にたどり着くには何が足りなくて何を補えばいいのかを探していきましょう。
仮決めでいいので全体像を書く 目次だけでもOK

まず、卒論の書き始めは何をすればいいのかについて、よく勘違いしてしまいます。
卒論が終わらないと焦っている人は「とにかくなんとか文字数を埋めないと」と思うもの。そのためにも、思いついたところから書き始めたくなりますよね。
ですが、たとえば推理小説で言うと、犯行動機や凶器、犯人など主なものが決まらないまま、気分で書き出せば必ず後になって整合性が取れなくなります。
これは卒業論文も同じ。
卒論も筋が通るかどうかが大事で、筋さえしっかりと通ったら、文章にするのは時間さえかければなんとかなります。
まずは、じっくり筋が通るのかどうか、目次を眺めて検討してください。目次がちゃんと筋道通りになっていて、すとんと最後までつながっていれば大丈夫です。
仮決めでいいので何を書くか先に大枠を決めてしまいましょう。(あとで変更しても全然OKです)
| 卒論を早く終わらせるためのコツ(その1) 仮決めでいいので何を書くか先に大枠を決めよう |
しかし、目次の中にやや強引に感じる部分や、図表やデータの分析が結論の主張と違っている部分があるのは問題です。
そんな場合には
- もう少しデータを補ってみる
- 少し引用を増やしてみる
など、その主張が強引にならないような工夫しましょう。
あるいは、ほかに自分の主張にあう図表やデータなどを探して差し替えてみたり、最初から最後まで通しみたりして、無理がなく変なひっかかりのない目次になるように手直ししてください。
目次さえ完成すればあとは書くだけ。もうゴールはすぐそこですよ。
▼こちらもチェック!
卒論のテーマはもう決まった? なかなか決まらないときはどうすればいい?
イントロと概要は後回し データを先にまとめて形を作っておく
次に、2つ目の卒論を早く終わらせるためのコツとして「イントロと概要は後回し データを先にまとめて形を作っておく」というものがあります。
真面目な人ほど、最初から順番を追って仕上げないといけないと考えがちです。
学科や卒論の種類によって少し変わると思いますが、大体の場合は、
- 目次
- 緒言
- 方法
- 結果
- 総合考察
という順番で書いていきますが、実際は
- 目次
- 方法
- 結果
- 緒言+総合考察
の順番に書いた方が、効率的ですし、無駄な作業がありません。
イントロである「緒言」は、論文では大切なところ。
- なぜそのテーマを選んだのか?
- この卒論では何を主張したいのか?
- 今まで知られていることの何が世の中で知られていないのか?
- 今回の卒論によって何が期待できるのか?
こういう部分は卒論の全体像を掴んでいないと書けないものです。
最初から、緒言を書こうと頑張っても、意味のない文章を書いて、結局は他の部分を書き終わった後に書き直さないといけない場合が多いのです。
そのため最初は、卒論の材料を集めることに集中するべきです。
理系の場合ですと、日頃の研究や実験などを行っていき、データの可視化や考察など行ってください。あとで見返しても分かりやすいようにしておくとよいでしょう。
| 卒論を早く終わらせるためのコツ(その2)
|
目次を考えて、日頃のデータを蓄積していく中で、箇条書きでもいいので、自分の考えを論理的にまとめる癖をつけておきましょう。
もしデータがまだなくても結論を仮決めでいくつかのパターンで書いてしまう

「もしデータがまだなかったらどうしたらいいの・・・?」
こういう場合は、対処法が2つあります。
| 【データがまだないときの対処法】
|
1番目の仮決めする場合は、先行論文など、頼る資料がない場合に活かすことができます。
まだ取り扱っている学生が少ない状態なので、不安な気持ちになるかもしれませんが、かえって好都合です。
なぜならば、指導する側の教授も未知の部分があるからです。
まだ、未開の分野の論文を書いていく場合、担当の教授などに相談をしていくわけなのですが、上手く質問や会話をしていき、自分の書きやすい卒論にしていくと良いでしょう。
箇条書きでも良いので、いくつかパターンを書いて、教授に相談するのが、早く終わらせるためのコツです。
2番目の先行論文などを探す場合は、もちろんそういう論文や資料がないと実行できません。
しかし、もし探すことができたなら、論理的な考え方や論文自体の構成も自分の中で整理することができます。
もちろん、先行論文や資料を引用する場合があるかもしれませんので、どの部分から引用したか、あとから分かりやすいようにまとめておいてください。
卒論の書き始めでつまずきやすい対処法は「とりあえず書くこと」
目次やデータがそろってくるとあと、大切になってくることは、卒論の書き始めです。目次というプロットが整い、あとは文字に起こしていくだけ。なのに、なぜか文章がうまく書けない。
書いているうちに、
- 「書き出しはどうすればいいのか」
- 「“てにをは”は正しいのか」
と考えてしまったり、同じ表現ばかり目についたりするなど気になることが出てきて、なかなか文が書き進められないことがあるかもしれません。
そもそも、文章を書くことが得意でない人は、「どうやってこの目次を文字にしたらいいのかわからない」と思うことさえあるでしょう。
そんなときでも、とりあえずどんな文章でもいいので、まずは文字に起こすことが大切です。その際、人に伝えるつもりで書いてみましょう。
本来、論文には論文独特の書き方があるもの。しかしそれが難しいようなら、とりあえず会話するように書いてみるのも1つの方法です。誰かに話すかのように、まずは最初から最後までを通して書き上げてみてください。
小説でも、一番大事なのはプロットです。プロットが面白くなければ、全体を通じて面白くなりません。そしてこのプロットの部分は、筆者がもっとも力を入れて作るところであり、その人なりの個性が出るところでもあります。
こういった「プロット」は卒業論文でも非常に重要です。
筆者がひとつの考えを、卒論全体を通して貫いていれば、
- 卒論の整合性
- 主張に無理がないか
など、おのずとわかるでしょう。
また、それがどんな論文でどんな主張なのかが文章の流れからわかれば、文章を直すのはそれほど難しくありません。先輩や指導教授なども手直しすることができるはずです。
ここで気を付けたいのは、相手にわかるように書くということ。
文章の上手下手よりも、誰もが間違いなく同じ意味に受け取れる文章を目指して書いていきましょう。
卒論の文字数で注意するべきこと
文字数は各学部やゼミごとに規定があるため、それを目安に書いていきます。
しかし卒論を書く中で、字数が足りないという人もいるかもしれません。そんな時、ついやってしまうのが話を広げるということ。しかしこれは要注意です。
| 【卒論の文字数で注意すること】 文字数を稼ぎたいあまり話題をふくらましてしまう 逆に文字数オーバーしすぎてしまいます |
順番にこれらのことを解説していきます。
文字数を稼ぎたいあまり話題をふくらましてしまう
参考書やノートなどでも、なんでもかんでもたくさん書いてあるものより、ポイントをうまく整理したもののほうがわかりやすく理解しやすいものです。
また、卒業論文において話を広げるということは、それぞれが関係性を結び、ともに結論に向かっていかないとならないということにもなります。
その分、たくさんの複雑な伏線の絡み合いを考えないとなりません。卒論の文字数を稼ぎたいあまり話題がふくらましすぎてしまいます。
そうなれば、あらゆる方向に向けて細かいことを調べなくてはならなくないため、ひとつひとつの話題が膨らんで収拾がつかなくなる可能性もありえます。
その結果、規定枚数に超過してしまったり期日までに仕上げられなかったりするかもしれません。
| 【話題をふくらましてしまうときの対処法】 論理を強化することで文字数を膨らませてみましょう |
そんなときには話を広げて文字数を膨らませるのではなく、論理を強化することで文字数を膨らませてみましょう。
論理を強化するには、一にも二にも先行研究やグラフ、図表などのデータです。
そのためにも、日頃の実験や研究でのデータというものを日頃から分析して、自分なりの考え方をまとめることを心がけると良いでしょう。
卒論の文字数オーバーしすぎるデメリット
たくさん文字や情報があればあるほどいいと思うかもしれませんが、実は、多すぎるとノイズが増えてしまい、逆効果ということもあります。
時には、今まで一生懸命書いてきた卒論をバッサリ切らなければ良いものは生まれません。
もし話が広がりすぎてしまったときには、結論に向かうために潔く広がりすぎたものを切ることも大事。
書くうちに、
- これはどうなのだろう
- あれはどうなのだろう
という疑問も出てくるものです。そういう卒業論文も、広がった課題は今後の研究として締めくくりましょう。
まとめ
| 【卒論を早く終わらせるためのコツ】
|
卒業論文制作は大変な作業ですし、慣れないことばかりでなかなか終わらないとくじけそうになることもあるでしょう。
ですが、卒業論文は4年間の集大成でもあります。4年間がんばって学んできた証として、ぜひ残しておくことをおすすめします。
卒業したあと、きっといい思い出になるでしょう。また、長い論文を書き上げたという経験は、社会に出てからもきっと大きな自信になるはずですよ。
▼こちらもチェック!
大学4年生が卒論提出後にするべきこと38選! 学生生活最後の思い出作りをしよう