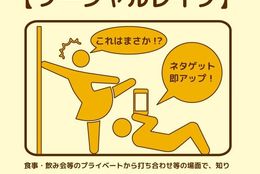「すみません」が口癖の人は要注意!それって“自己の喪失”かも?! 『発達性トラウマ 「生きづらさ」の正体』#Z世代pickブック
こんにちは! Z世代ブックピッカーのひっき(出版甲子園実行委員会所属)です。
普段、意識せずとも触れ合っている心理学の世界。ストレスやモチベーションなどさまざまな用語がありますが、「トラウマ」という言葉も一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
今回は「トラウマがもたらすこと」について、公認心理師・みき いちたろう氏の著書『発達性トラウマ 「生きづらさ」の正体』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)よりお届けします。
トラウマがもたらす“自己の喪失”と様々な症状
トラウマを負うとどのような症状になるのかについて解説します。特に現在もまさに生きづらさを抱えている方が自身の状況に気がつくきっかけになるように、なるべく手触り感を持ってご説明できればと思います。
トラウマの本質は「自己の喪失」
まず、大切なことは、トラウマによって様々な症状が引き起こされますが、その中でも核心となるものを踏まえる必要があるということです。核心を踏まえると個別の症状についても理解しやすくなります。
では、トラウマの核心は何か? と言えば、それは「自己の喪失(主体が奪われること、失われること)」です。トラウマを負うと、フラッシュバックや過覚醒といった問題のみならず、自分が自分のものであるという根本的な感覚が失われてしまうのです。特に発達性トラウマなど慢性的なトラウマではそうした感覚が顕著です。
ログインしていないスマートフォン
トラウマを負った人の多くは行動力があり、活発にいろいろなことに取り組んでいるために、まさか「自分がない」、などとは思いもしません。お読みのあなたも、「自分はそんなことはない」「自己の喪失なんていう実感はない」とか、「自分は自分で考えて行動もしてきたし、いろいろと取り組んできた。主体、自分がないなんてことはないだろう」と思われるかもしれません。
しかし、哲学や文学などのテーマにもなってきたように、本当に自分が自分そのものであるかはなかなか難しいものです。他者の期待や役割をこなすことが自分であると勘違いしたままということも珍しくありません。多くの場合、様々な症状や生きづらさに悩んだり、年齢が上がるにつれて環境の変化にも直面し、濃淡はありますが、よく考えれば自分がないことに気づくようになります。
私はそうした状況を「電器店にある見本のスマートフォンみたい」と表現します。物理的には動くけれども、自分のIDではログインしていない。自分の身体はあるし、行動はしているけれど、そこに自分がない、自分のものではない。本当の意味で自分によって動いていないし、自分で経験していない。そのために、何かを経験しても積み上がる感覚がない。自分の身になる感覚がないのです。それが一層、自信を失わせることにつながります。
トラウマが重いケースではこうしたことが顕著に現れます。これから見る個別の症状も自己喪失の結果、心身を統御できずに生じているとも考えられるのです。では、ここから具体的な症状を見ていきましょう。
症状1 過緊張
トラウマを負った場合に生じる、最も身近な症状が「過緊張」です。緊張する場面ではないところでもなぜか過剰に緊張してしまうのです。
頭で緊張を抑えようとしてもコントロールすることはできません。反対に、緊張しないでいようとすればするほど緊張は高まってしまいます。
本来、緊張とはストレスに際して、心身を活発にして対処するための便利な機能です。ただ、何を危機と認識するのか、どのタイミングで作動して、どのタイミングで収まるのかがうまく機能していない状態、これがトラウマから来る過緊張です。
特に、トラウマでは処理されない記憶が意識下に残っていて、扁桃体が過活動を起こしていると考えられます。内面では、常に危機が自分の隣にある状態です。それに対して身体は常に反応を続けています。危機に対応して身体はある意味正常に動いているともいえます。
リラクゼーションや呼吸法などを使っても緩和することは難しいです。緊張は、単に性格の問題や一時的なストレスによるものではありません。トラウマによる過緊張とは根深く、対症療法では太刀打ちできないものです。
症状2 過剰適応
過緊張と並んでトラウマによって生じる代表的な症状として「過剰適応」があります。過剰適応とは、簡単に言えば、「他人に気を遣いすぎてしまう、周りに合わせすぎてしまう」ということです。
トラウマを負った人は、いろいろなことを先回りして考えることが当たり前になっています。相手の感情や考えを過度に忖度してしまう。相手の雰囲気やちょっとした表情を読み取って、相手が怒らないか、気分を害さないか、と考えてしまうのです。多くの人が集まるような場面であれば、いろいろな段取りに過度に気を回したり、お世話しようとします。
しかし、本当の意味で相手の気持を汲めているわけではありません。むしろ、相手の意識下の不全感を忖度し、巻き込まれてしまうことも少なくありません。先回りして相手の気持を察しようと下手に出てしまい、相手に軽んじられたり、ハラスメントにさらされたり、といったこともしばしば生じます。
過剰適応の背景には、罪悪感や自信のなさが潜んでいます。別の記事で見た伊織さんがそうですが、「すみません」「ごめんなさい」が口癖になっていることもよくあります。そのような口癖があれば、過剰適応を疑ってみる必要があります。
また、怒りや叱責など他者の感情への恐れもあります。他者イメージのから来る対人恐怖も影響します。他者のイメージが実際以上に大きくなり、他者が得体の知れない理不尽な存在として捉えられています。そして、社会や人間関係のルール、メカニズムがよくわからない、という感覚もあります。そうした中で自分を守る手段が「過剰に気を遣う」ことなのです。
周りに合わせることを最優先するために、自分の気持ちや考えがわからなくなってしまいます。その結果、「自分(自己)」をしっかり保てなくなるのです。自分(自己)がないために、外部の基準に過剰に合わせるしか社会に適応するすべがなくなってしまうのです。
Z世代ブックピッカーのレビューコメント
人に気を遣いすぎてしまうことは、私もとても共感できます。相手に悪く思われたくないという感情からとってしまう行動だと思っていましたが、結局相手に良いように使われているだけなのではないかとも感じ、生きづらさに繋がってしまうのだと知ることができました。過緊張になってしまう人もそうですが、本当はすごく優しいから、自分の見え方や相手の反応を気にしてしまうのだと思います。私自身も自覚しつつ、そういった悩みを持つ周囲の方々を尊重し、受け入れることを大切にしたいです。
『発達性トラウマ 「生きづらさ」の正体』
著者:みき いちたろう 発売:2023年2月17日 定価:1,320円 (税込み)
発行:ディスカヴァー・トゥエンティワン
詳細ページ:https://d21.co.jp/book/detail/978-4-7993-2934-4
書籍レビュー:
読み終わる頃には、今までうまく言語化できなかった不安な感情が何だったのか気付けるようになると思います。「自分を大切にすること」は当たり前にすべきことなのに、意外とできていなかったことに気付かされました。また、人を尊重するためには、その人のことを受け入れることから始めますが、自分の想像の及ばない人に出会ったとき、「何かしらの生きづらさを感じているのではないか」と想像を働かせ、受け入れ、尊重できるようになれたら良いなと思いました。