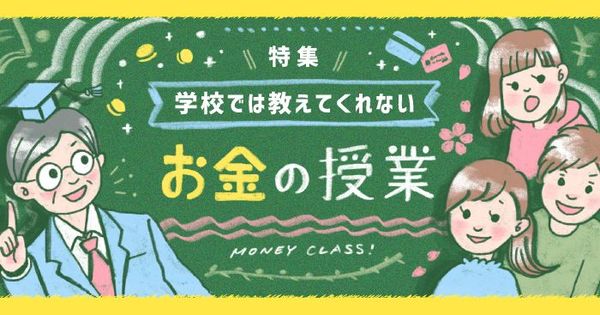仮想通貨の仕組みについてわかりやすく解説!|学校では教えてくれない「お金の授業」
この記事では最近話題の仮想通貨について詳しく解説をしていきます。
ブロックチェーンやビットコインに関する話題が最近増えていますが、その内容を理解している人はまだまだ少ないでしょう。
今回は仮想通貨業界に関して基礎から、なぜ注目されているのかまで解説していきますので、興味がある方は是非最後まで読んでみてください。
※本記事での仮想通貨は暗号資産を指します。

仮想通貨とは?
仮想通貨とは、電子データのみで取引される通貨のことで、インターネットで取引された物品やサービスの対価として利用することができます。
サトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto)と名乗る正体不明の人物(または集団)が発表した論文をもとに、2009年にビットコインの運用が開始されたのが仮想通貨の始まりです。
その後、アルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨の総称)が次々と生まれ、現在に至ります。
中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せず、ピア・トゥー・ピア(P2P)という方式が採用されており、仮想通貨を扱う者同士で取引情報が管理されます。
仮想通貨の種類
世界には約3,000種類の仮想通貨が存在しますが、日本で主要な扱いがある仮想通貨は以下の通りです。
仮想通貨の名称【読み方】(カッコ内は略号)
| 名称 | 特徴 |
| Bitcoin【ビットコイン】(BTC) | 正体不明のサトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto)という人物(または集団)が論文を公開。その論文によって運用が開始された仮想通貨です。2009年に運用が開始され、世界規模で普及している代表的な仮想通貨です。 |
| Ethereum【イーサリアム】(ETH) | さまざまな契約を自動化する「スマートコントラクト」を実行できる分散型プラットフォーム。契約内容がブロックチェーンに書き込まれているため、改ざんの心配がなく、契約を自動的に実行保存する機能があります。 |
| StellarLumens【ステラルーメン】(XLM) | 2014年7月に公開され、SDFという非営利団体によって開発・運営されています。個人間の送金や国際送金の問題を解決するために開発された独自通貨です。 |
| Litecoin【ライトコイン】(LTC) | 2011年にビットコインをベースに元グーグルのエンジニア、チャーリー・リー氏によって開発された仮想通貨です。ビットコインの課題であったトランザクション(取引処理速度)を解決する目的で開発されました。発行上限はビットコイン2,100万枚に対し、8,400万円と4倍に設定されています。 |
| BitcoinCash【ビットコインキャッシュ】(BCH) | 2017年8月1日にビットコインからハードフォーク(分裂)して誕生した仮想通貨です。ビットコインの取引拡大にともない、処理速度が低下するといった問題を解消しています。 |
仮想通貨の特徴
仮想通貨の特徴は、従来の法定通貨と異なり、「非中央集権」の仕組みとなっている点や、電子データのみで取引される通貨であるにも関わらず、現物の法定通貨と交換できること、発行数量に上限があるなどの特徴があげられます。
それぞれについて詳しく解説していきます。
非中央集権の仕組みとなっている
非中央主権の仕組みとは、政府や企業などの中央機関を持たず、P2P(個人間)でその仕組みを共同運営する仕組みのことです。
一方、円やドルといった法定通貨は国が発行・管理をしており、各国の金融政策によって発行量が決められているため、中央集権の仕組みを採用している通貨といえます。
中央集権は、中央に権力が集中し、非中央集権は個人の意思で自由な取引ができるという特徴があります。
法定通貨への交換が可能
仮想通貨は法定通貨(円やドルなど)に交換することが可能であり、仮想通貨を入手したり、法定通貨に交換したりするときは、一般的にはインターネットの「交換所」や「取引所」を利用します。
なお、平成29年4月1日以降から、これらの業態は「仮想通貨交換業」として資金決済法の規制対象となりました。
仮想通貨交換業とは…仮想通貨と法定通貨の交換、仮想通貨同士の交換、および利用者の仮想通貨と金銭の管理を行う業務を指します
発行上限が設定されている
法定通貨は、国が発行・管理をしており金融政策によってお金の価値をコントロールしています。一方、仮想通貨の多くは発行数量に上限が設定されています。なお、ビットコインの発行上限は2,100万枚です。
仮想通貨が市場に出回りすぎると価値がさがるため、一定のペースで上限に到達するように定められています。仮想通貨には、国のような発行母体が存在しないため、その発行ペースはプログラムによって自動的にコントロールされています。
例えば、ビットコインの場合、マイニングによって新しいビットコインが発行されますが、おおよそ4年に1度のペースで、マイニング報酬が半減する「半減期」が設けられており、新規発行数量が抑えられます。
このような仕組みによって仮想通貨は、発行量をコントロールされているのです。
仮想通貨の利用方法
ここまで解説してきた仮想通貨について、どのように活用していくことができるのでしょうか?仮想通貨そのものの活用と、ブロックチェーン技術の活用という側面から解説します。
決済手段として利用するため
仮想通貨は、暗号化されたデジタル通貨であり、現物が存在しないにも関わらず、インターネット取引の決済手段として利用されるなど、円やドルといった法定通貨と同様の役割を果たしています。
従来の中央集権の法定通貨と比べて、仮想通貨はネットワーク上の複数の利用者が分散してデータを管理するため、非常にセキュリティが強固であり、改ざんのリスクが低いとされています。
分散型プラットフォームを利用するため
仮想通貨は法定通貨のように国家が通貨供給量をコントロールするわけではありません。ネットワーク上で分散してデータが管理されることで、一部のデータが停止や故障をしてもシステム全体は稼働し続けることができます。
また、取引量が増えれば増えるほど、ネットワーク上で分散管理されるデータは大きくなり、セキュリティはより強固になり、改ざんのリスクも低減されます。
仮想通貨を支えるブロックチェーンとは
ブロックチェーンとは分散型台帳と定義されることもあります。これは分散型ネットワークを構成している多数のコンピューターの暗号技術を組み合わせ、取引データを記録する方法です。
仮想通貨の取引データは一定期間ごとにブロック単位でまとめられ、多数のコンピューター同士で検証しあいながら、ブロックを鎖のようにつなぎ合わせていきます。連結された各ブロックは、1つ前のハッシュ値(ハッシュ関数によって計算された値)を持っています。そのため仮に改ざんされても、1つ前のブロックのハッシュ値と異なれば、後続ブロックのハッシュ値も全て変更する必要があるため、実質的に改ざんは困難です。
また、一部のデータが改ざんされても、複数のコンピューターと整合性を確認し、正しい取引データを選別、保持し続けるため、改ざんのリスクは大きく低減されます。
さらに、ブロックチェーンは、複数のコンピューターが分散して構成されているため、大規模なインフラを必要としません。そのため、低コストで、特定の管理者が不在(非中央集権)でも信頼性を保つことが可能です。
仮想通貨のリスク
ブロックチェーン技術によってデータ改ざんの可能性は少なくなりましたが、仮想通貨には依然として、価格変動や、ハッキングのリスクが潜んでいます。
価格の急激な変動や不正アクセスによる損失は、どこでいつ発生するのかという、予測が難しいのです。
ここでは、主な仮想通貨に関するリスクの一部を紹介します。
価格変動が大きい
仮想通貨は価格変動幅(ボラティリティ)が非常に大きく、2021年3月時点でも1日で10%以上の価格上下を続く局面がある、非常にリスクの高い資産です。また、経済情勢や政治情勢、法令の変更など、さまざまな要因によって価格が大きく変動する可能性があります。価格の不安定さに留意した上で、リスクを最小限に抑えるためには、慎重な投資や取引が必要です。
ハッキングのリスク
電子データで取引される通貨である以上、ハッキングのリスクは付きまといます。2014年にはハッキングによって仮想通貨の価格操作が行われ、最終的には破産申請に追い込まれたマウントゴックス事件が発生しました。
また、記憶に新しいところで2018年の仮想通貨取引所のCoincheckがハッキング攻撃をうけ、580億円の仮想通貨が盗難された事件もあります。利益の大きいところには不正も集まりやすいのです。個人でいくら気を付けていても、取引所自体がハッキング攻撃をうけることもあります。
現在は改善の傾向が見られますが、未だにハッキング攻撃のリスクが存在することを認識しておくことが重要です。
まとめ
仮想通貨は電子データのみで取引される通貨であり、主な仮想通貨にはビットコイン、イーサリアム、ステラルーメン、ライトコイン、ビットコインキャッシュなどがあります。しかし世界には3,000種類もの仮想通貨があるといわれており、日本で扱えるものは今回紹介したものも含めてごく一部です。
仮想通貨の特徴として、非集権的な仕組みとなっていること、電子データのみの通貨でありながら法定通貨と交換できること、発行上限が半減期によって自動コントロールされていることなどが挙げられます。
仮想通貨は、一定期間ごとの取引記録をブロックにまとめ、つなぎ合わせることで改ざんを困難としています。また、複数のコンピュータでお互いに監視をし合い、整合性を保っていることから、非中央集権でもその取引の信頼性を保っています。
仮想通貨の技術により、取引記録の改ざんリスクは少ないものの、価格変動が大きいため、場合によっては大きな損失が発生してしまうことがあることもあります。また、ハッキングにもさらされやすい分野なので、セキュリティ対策への注目は必要です。
仮想通貨業界は、近年急激に成長しています。今後の動向を見逃さないようにも、是非最新の情報をチェックしてみてください。

文:金子 賢司
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。 以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、 年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。 <保有資格>CFP、住宅ローンアドバイザー、生命保険協会認定FP、損保プランナー 公式HP
制作:Media Beats
イラスト・編集:watasack(渡邊 桜)
他の“学校では教えてくれない「お金の授業」”もチェック!