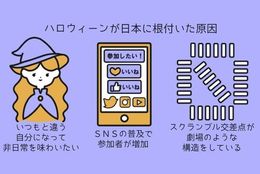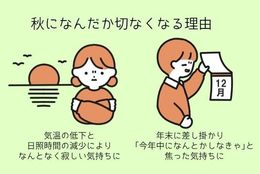コンセントの穴が左右で大きさが違うのはなぜ? #もやもや解決ゼミ
日常に潜む「お悩み・ギモン」=「もやもや」を学術的に解決するもやもや解決ゼミ。
皆さんは、コンセントの穴が「左右で大きさが違う」のはご存じでしょうか? 知らないという人は、近くにあるコンセントを確認してみてください。向かって左側の穴の方が若干ですが縦長になっていませんか? 実は一般的な家庭用コンセントの穴は左右の大きさが異なります。では、なぜ大きさが違うのでしょうか?

コンセントなどの配線器具を製造する『神保電器株式会社』にその理由を聞いてみました
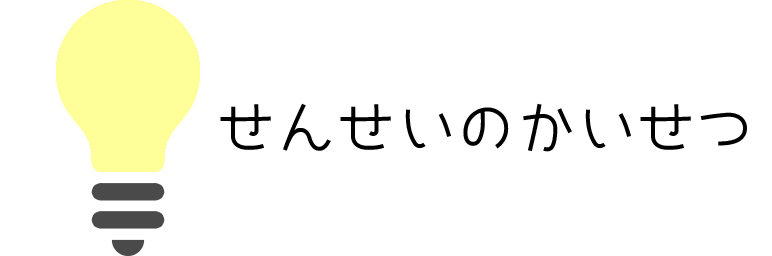
コンセントの穴は左が9mm、右が7mmとふぞろい
一般的な家庭用100Vのコンセントの差込口の幅は、左が9mm、右が7mmとふぞろいになっています。これは、コンセントに極性があることに由来しています。向かって左側の大きい穴が「接地側」、対して右側の小さい穴は「非接地側」といいます。
では、「接地側」とはどういうことでしょうか。一般の住宅に引き込まれている100Vの電源は、その電線路の片側をアース(接地)することになっています。アースすることで、漏電や電源ノイズ、なんらかの事故による異常電圧の混入などから、電源に接続されている機器や使用する人を守ります。左右で極性が異なるようにしているのは、電気を安全に使用するための大切な決まりなのです。
左右を間違えないように穴の大きさが変えてある

コンセントの穴は「接地側」「非接地側」と左右で役割が異なります。しかし、一般的な家電製品を見ると、プラグの大きさは左右で同じです。これは、左右どちらの向きにプラグを差し込んでも、電気が問題なく流れる仕組みだからです。
しかし、中には左右の極性を合わせる必要のある機器も存在します。その場合は「接地側」と「非接地側」が判別できないと、左右どちらの向きに差し込めばいいか分かりません。そのため、コンセント側は左右で大きさを変え、プラグ側も左右で幅を変えることで、逆さまに差し込めないようにしています。また、コンセントの裏側では、接地側の電線をつなぐ穴に「W」や「N」(接地側という意味の記号)などと表示して、工事をする人が間違えないように工夫をしています。
このように、コンセントの穴は、電気の通り道の交通整理をし、電気を安全に使用できるよう、左右で大きさが変えてあるのです。
海外では国によってコンセントの形状が異なる
海外ではその国の規格に基づいたコンセントになっているため、国によって形状に違いがあります。また、同じ国内であっても、地域によって形状が異なるケースや、複数の形状のコンセントが併用されているケースもあります。ドライヤーなどの家電製品を海外に持っていく場合は、その国、その地域の規格に合った変換器、変圧器を事前に準備するといいですね。
あなたのコンセントは大丈夫?
コンセントには、電気を安全に使うためのさまざまな工夫が施されています。例えば、コンセントの刃受けでプラグの刃をしっかり挟み込み、接触不良が起こりにくいようにしています。また、コンセント表面に凹凸を設けてトラッキング現象(コンセントとプラグの隙間にたまったホコリが原因で漏電し発火する現象)が、起こりにくいようにするといった工夫もあります。
そのほか、コンセントにも寿命があり、以下のような状況で利用している場合は寿命が短くなります。また、コンセントのひび割れや変色がある場合には、安全のためにお近くの電気店に相談してください。


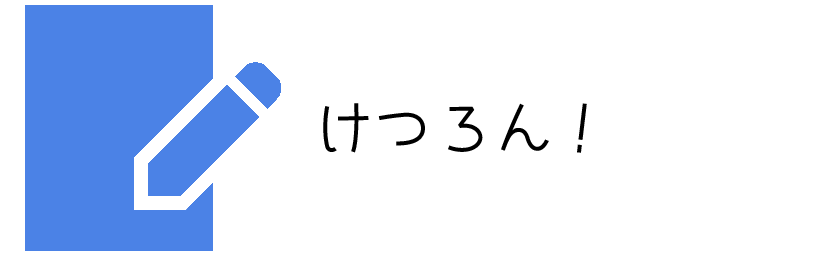
コンセントの穴が左右で大きさが異なるのは、役割を正しく機能させ、安全に利用するためとのことでした。普段の生活ではあまり意識しないかもしれませんが、私たちが安全に電気を使うためのとても重要な工夫なのです。
取材協力:神保電器株式会社 https://www.jimbodenki.co.jp/
イラスト:ここま まこ
文:高橋モータース@dcp