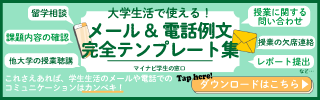学生でも確定申告は必要? 申告が必要な場合とは?
この記事では、学生でも確定申告が必要な場合について網羅的にご紹介します。
学生では、確定申告という言葉を聞いたことがないという人もいるかもしれませんが、学生であっても、アルバイト等である程度の収入がある場合は確定申告をしたうえで、必要に応じて「税金」を支払わなくてはなりません。
確定申告を知ることによって後々困らないだけでなく、大人になってからだけでなく副業に興味がある場合にも役立ちます。
確定申告とは?
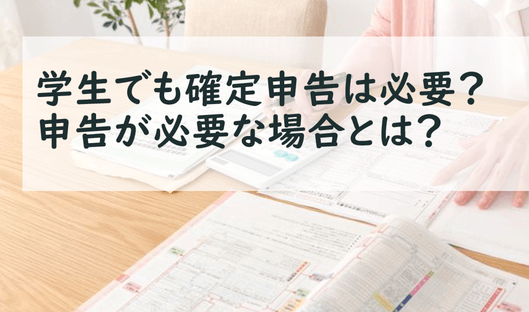
確定申告とは、一般的に1月1日から12月31日までの1年間に受け取った給料などといった所得を税務署に申告し、納めるべき所得税の額を決定する手続きのことです。
| 所得税 | 1年間で稼いだ給料所得について支払うべき税金のこと |
会社員の場合、会社が源泉徴収や年末調整などで給料に対して支払う必要のある税金をあなたに代わって計算し、天引きによって自動的に納められるように仕組み化されています。
税金に対して知識がなくとも勝手に納税してくれるため大変便利だと言えるでしょう。
源泉徴収とは?
給料や報酬など支払う事業者などに義務付けられている、税金を納める国の制度のことです。
正確な額を滞りなく納税してもらうために、従業員などの個人に代わって、ざっくりとした税金を給料から天引きし、預かる形で納付します。
大学を卒業し、会社に勤務すると会社があなたに代わって源泉徴収をしてくれるため、基本的に自分で確定申告をする必要はありません。
本来であれば、自分で税金を納める手続きをしなければなりませんが、源泉徴収によって自分で税金を納める側も手間が省けられます。
さらに、税務署の負担軽減や徴収漏れも実現できることから、双方によってメリットがあるのです。
年末調整とは?
源泉徴収と一緒に知ってほしいのが年末調整です。学生の場合も、アルバイトで「年度末調整」をお願いされることがあるでしょう。
年末調整は、所得税の過不足を調整する手続きのことを指します。
主に年末に行われ、保険や家族の有無など個人の税金にまつわる状況を会社などがとりまとめることで正確に把握し、支払うべき税金の金額を確定する手続きです。
確定申告し忘れたらどうなるの?

税金の入金不足があるのにもかかわらず確定申告を忘れた場合、延滞税や無申告加算税といった利息が発生します。
芸能人などによる脱税問題がニュースに取り上げられているのを観たことがあるという方もいることでしょう。
確定申告をしないまま放置していると、稼いだ金額によっては脱税疑惑を持たれてしまい、税務署があなたの家に立ち入り捜査をすることも考慮しなければなりません。
払いすぎた税金を戻してもらう(還付)場合は、その年の1月1日から数えて5年以内に手続きをすれば大きな問題になりません。
しかし、払いすぎた税金は自分で申告しないと戻ってこないという点からもアルバイトなどで働きすぎている傾向がある学生は、確定申告の重要性を知る必要があると言えるでしょう。
どんな場合に確定申告が必要?

アルバイトをしている学生であっても、一定の金額を給料として得た場合は確定申告が必要です。
現在では、学生をしながら投資や事業を起こすなどで自分で資産を形成できる時代にもなりました。
様々なケースにおいて確定申告が必要となる場面も多くなるため、一度一緒にチェックしてみましょう。
必要な場合その1:アルバイト先で年末調整が行われていない
年末調整は雇用先が代わりに手続きをしてくれるのが一般的ですが、アルバイト先によっては自分でアルバイト代に対する確定申告をしなければなりません。
1か所でアルバイトをしている場合は、毎月もらう給料から所得税分の金額が天引きされています。
これは、本来自分で支払うべき所得税を会社に一度預かってもらい、代わりに納めてもらっている状態です。
しかし、アルバイト代の年収103万円以下の場合など、本来は所得税を払わなくていい場合は前述の「年末調整」で金額を調整する必要があります。
確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)ので、忘れずに行いたいものです。
必要な場合その2:アルバイトの掛け持ちをしている
2か所以上でアルバイトの掛け持ちをしている場合もあるでしょう。
実は、アルバイトの給料から所得税分を天引きしてもらう源泉徴収の手続きは1か所のアルバイト先でしかできません。
そうすると、源泉徴収をしてもらっている会社以外の給料からは、源泉徴収がされていないことになります。
2か所以上でアルバイトをしていても、アルバイトによる年収が103万円以下なら問題ありません。
しかし、仮にアルバイトの年収が合計103万円を超えてしまった場合、所得税を納める義務が発生します。
源泉徴収をされていないアルバイト先の給料も考慮したうえで、本来納めるべき金額を確定申告で計算することで、実際に納めるべき所得税を計算しなくてはなりません。
必要な場合その3:年末前にアルバイトを辞めた場合
アルバイト先で行ってくれる年末調整は、12月31日時点でアルバイトをしている人に限られます。
年末調整が始まる前にアルバイト先を辞めていしまった場合は、年末調整を受けられません。
従って、年収の合計が103万円以上の場合かつ年末調整前に辞めてしまった場合は自分で確定申告をします。
必要な場合その4:株やFXなど投資やフリーランスの仕事をしているなど自分で資産を形成している場合
最近では学生の間に自分の事業を起こして、フリーランスとして活躍する方や株式投資やFXなど投資家学生も増えています。
この場合、アルバイトとは異なり個人で資産を増やすことからルールが変わり、親の扶養に入っているかどうかが重要です。
| 扶養とは | 養わなければいけない家族のこと |
さらに扶養には、税制上の扶養と社会保険上の扶養と2種類あることを覚えておかなければなりません。
|
税制上の扶養 |
・所得税(※1)や住民税(※2)の納税に関すること ・主婦の場合は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」に関すること |
社会保険上の扶養 |
・親が会社で加入している社会 保険(※3)に追加負担なしで加入できる。 |
※1所得税…お金を稼いだ人全員にかけられる税金で、国に納める義務がある
※2住民税…都道府県や市町村に住む人がサービスを受けるための経費を、税金として住んでいる地域に納める。住んでいる場所によって住民税の金額が異なる
※3社会保険…病気・ケガ・死亡・年金などの生活上の危険に対して国民全体でお金(保険料)を出し合って助け合う制度。お金は社会保険に集められ、助けが必要な人に充てられる
会社員の場合、定期的に自立して生活できるお給料をもらい、税金だけでなく社会保険費用も天引きされています。
しかし、扶養下にいる学生はその限りではなく、親にまだ養われている状態だと言えます。
そこで学生として親の扶養に入りながら株やFX・フリーランスとして自分で資産を増やしている場合、年間で以下の金額を稼いでしまうと扶養から外れ、自立したとみなされてしまいます。
税制上の扶養から外れる |
48万円以上稼いだ場合 |
社会保険上の扶養から外れる目安 |
130万円以上(月給換算で10万8,333円以上)稼いだ場合 |
なぜかというと、親の扶養に入れる条件が以下であるためです。
|
税制上の扶養 |
・その年12月31日現在の年齢が16歳以上であること ・親と日常生活をともにしている ・1月~12月までの報酬が48万円以下 ・納税者である親が自営業者の場合、親の会社で働いて給料を得ていないこと |
社会保険上の扶養目安 |
・親から見て3親等内の親族 ・親と日常生活をともにしている ・あなたの収入が130万円未満(月給換算10万8,333円未満)であること ・親と同居している場合、収入が親の収入の半分未満であること ・親と別居の場合、収入が親からの仕送り額未満であること |
アルバイトではなく投資やフリーランスなど自分で資産を形成する場合、親の扶養下にいるためには税務上の扶養範囲と社会保険上の扶養範囲を超えないように自分で収入の調整をしなければなりません。
ただし、条件ならびに収入形態によっては、後述する勤労学生控除という税負担を軽減できる制度が適用される場合もあるため、自分が対象かどうか一度チェックするのをおすすめします。
社会人から学生に戻った場合はどうなる?
最近では、社会人から大学に進学する方も増加しつつあります。
一般的に、学生に戻った最初の1年目は、社会人としてこれまで天引きされていた
・社会保険
・厚生年金
・所得税
・住民税
といった、税金を全て支払わなければなりません。
また、学生としてアルバイトなどを検討する場合は、
・アルバイトをしているか
・投資やフリーランスなど自分で資産形成をしているか
によって、確定申告の有無や方法が変化するため、前述の確定申告が必要な場合の項目を参照すると良いでしょう。
社会人から学生に戻った場合、健康保険や住民税・年金など税金の種類によっては親の扶養下に入ることで免除になる場合や、後述する勤労学生控除の対象になることもあるため、各種税金担当者または税務署・税理士などに確認することをおすすめします。
確定申告を行うには?

確定申告期間は、主に2月中旬から3月中旬の間が一般的です。
国税庁が定める期間内に申告をすることで、税金の未払いを防止できるだけでなく、払いすぎた税金を返金(還付)してくれます。
確定申告を行う方法は主に3つあるため、対象の場合はあなたのやりやすい方法で確定申告をしましょう。
1)税務署に行き、手続きをする
初めて確定申告をする場合は、税務署での手続きがおすすめです。
お住まいの地区ごとに最寄りとされる税務署があるため、担当者と話しながら書類作成ができるため良くある記入間違いを防げます。
また、確定申告の時期になると申告書の書き方も交えた無料説明会などを定期的に開催してくれることから、書類作成がひとりでは不安な方におすすめです。
ただし、確定申告の時期には多くの人が手続きの質問に殺到します。そのため、長時間待つこともあるかもしれません。
できれば早い段階で確定申告に関する疑問点を確認しに行くのも手段のひとつです。
2)国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」を使って申告書を作成し、必要な書類と一緒に送る
国税庁のホームページには、毎年確定申告の時期に無料で利用できる「確定申告書作成コーナー」というものが設置されます。
画面の指示に従い必要書類に記載されている数字を入力することで、自宅にいながらパソコンからも簡単に申告書が作成できます。
提出方法は主に以下の2通りです。
・申告書を印刷し、郵送または税務署に設置されているボックスへ投函
・e-taxと呼ばれる電子申請にてデータを送信する
税務署へ直接行く手間が省けるというメリットがあるものの、わからない項目は自分で税務署に問い合わせる必要があるため、初めての方は不安もあるかもしれません。
3)会計ソフトを利用し、確定申告書の書類を作成し、税務署へ送る
最近では、「確定申告書類作成コーナー」よりもわかりやすく簡単に確定申告ができる会計ソフトも続々登場しています。
無料である程度の機能を使えるだけでなく、「確定申告書類作成コーナー」よりも入力項目がわかりやすいため使い勝手が良いと言えます。
しかし、全ての機能をスムーズに使うためには有料会員にならなければなりません。
また、わからない項目を質問するにも有料サービスの場合もあるため、実際にある程度事業を展開していないと、かえって使い勝手が悪い可能性があるでしょう。
確定申告に必要な書類
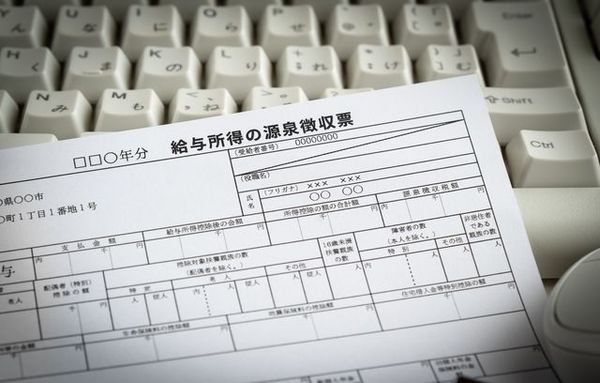
確定申告に必要な書類は、以下の通りです。
| 必ず用意したい書類や道具 |
| ・所定の確定申告用紙 ・アルバイト先からもらった源泉徴収票 ・印鑑(ゴム印NG) ・銀行口座情報 ・マイナンバーカード(ICチップ付き) ・ICカードリーダーライターまたはICチップ読み取り対応のスマートフォン(電子申請時) |
銀行口座情報は、年末調整をしていない状態で確定申告をする場合に必要です。
払いすぎた税金(還付金)を受け取るために、ゆうちょ銀行などの銀行口座の情報も求められます。
電子申請の場合、ICチップ付きのマイナンバーカードおよびICチップを読み取る器具を利用しますので、電子申請を検討している方は道具の準備も忘れてはなりません。
覚えておきたい「勤労学生控除」の制度

日本の税金システムには様々な控除制度がありますが、覚えておきたいのが「勤労学生控除」という制度です。
控除とは |
税金や社会保険の負担を軽くすること |
勤労学生控除とは、その年の1月1日〜12月31日までの間に一定の金額を稼ぎながら勉学に励む学生たちの税金負担を減額してくれる税制度です。
勤労学生控除とは |
働きながら勉学に励む学生たちの税金(所得税と住民税)の負担を軽くすること |
年度末調整や確定申告時に申請ができるため、覚えておくと役立ちます。
勤労学生控除は所得税と住民税が対象
勤労学生控除は、給料などの所得に対して以下の金額が控除されます。
| 勤労学生控除を受けられる税金(2020年以降) |
| ・所得税:27万円 |
お住まいの地方自治体ごとに課せられる住民税(県民税・市民税など)は地方自治体により差異があるため、住民票を置いている地方自治体によく確認しましょう。
勤労学生控除を受けられる条件
勤労学生控除は、学生で収入を得ている人が誰でも適用されるわけではありません。
所得税を管理する国税庁が定めるところによれば、勤労学生控除が適応するためには12月31日の時点で以下の条件であることが求められます。
| 勤労学生控除の対象(2020年度以降) |
| 1)給料など所得がある学生 ※勤労所得が学生である納税者本人の勤労による所得であること 2)1)による合計所得金額が75万円以下でかつ、1)における就労以外で収入が10万円以下であること ※例)給与だけの収入金額が130万円以下の場合、給与所得控除55万円を差し引くと、所得金額が75万円以下となります。 3)国税庁が定める特定の学校の学生・生徒であること ・学校教育法に規定する小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校など ・国・地方公共団体・私立学校法の第3条に規定する学校法人など ・職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で、一定の課程を履修させるもの |
勤労学生控除を利用する際の注意点
注意したいことは、
・給料などの所得に株やFXなど投資の配当金は所得に当てはまらない
・住民税と所得税では控除金額に差がある
・親の税負担が増えるまたは扶養に入れない場合がある
・学校によっては勤労学生控除を受けられない学校である場合がある
ということです。
自分の学校が勤労学生控除に当てはまる学校かどうかは教務課などで確認できますので、気になる方は確認してみましょう。
また、アルバイトやパートの場合は給与控除がありますが、フリーランスなど業務委託で自分で資産を形成している場合は給料ではなく「報酬」となることを考慮しなければなりません。
税金負担の控除を受ける場合は所得税はもちろん、住民税や親の扶養にも着目した計画的な働き方が必要でしょう。
いずれも自己判断が難しい場合も多いため、自分が対象かどうかは税務署または税理士と言ったプロの指示を仰ぐことが適切です。
まとめ

確定申告は、アルバイトなど稼いだ金額によっては必ずしも必要ではありません。
会社員になる場合は、会社が代わりに手続きしてくれることもあり、知らない人の方が多いかもしれません。
しかし、最近では様々な働き方があることからも、知識として覚えておくだけでも損はないでしょう。
税制は常に変化します。自己判断で誤りのある情報を申告した結果、適用されなかったり自分の税負担が増える可能性があったりなど、損害を被ることも覚えておかなければなりません。
学生だとしても、確定申告が必要なほど多額の収入を得て働いている場合は最寄り税務署や税理士への相談をおすすめします。