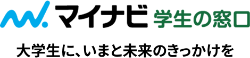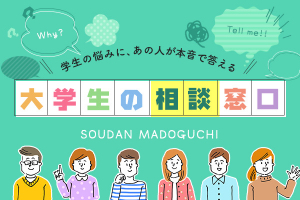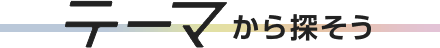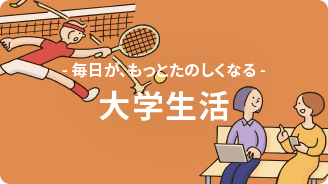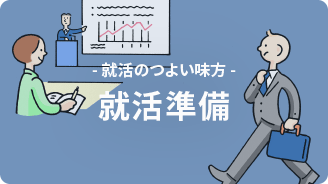【男性作家では史上最年少で直木賞を受賞!】作家・朝井リョウ「学生っていう肩書きでできることは、全部やらないともったいない」 #1 ~出版甲子園による独占インタビュー~
大学在学中のデビュー以来、その豊かな想像力で読者の心を掴んできた作家、朝井リョウさん。今回は、出版甲子園がこの夏発行したフリーペーパー「SHIORI」に掲載の朝井さん独占インタビューを3回連続で公開!「本」を通して、さまざまな面からその内面を掘り下げました。

大好きな本と自分が細い光で繋がった感覚
ーー幼い頃は、どのような本を読んでいましたか?
朝井:小学生くらいのころは、青い鳥文庫という講談社の文庫のシリーズが大好きで、はやみねかおるさんの夢水清志郎シリーズ、 松原秀行さんのパスワードシリーズ、令丈ヒロ子さんの料理少年のシリーズなどを読んでいました。3つ上に姉がいるのですが、姉が図書館で借りてきた本をそのまま読む、という感じでしたね。あとはとにかくさくらももこさんのエッセイシリーズ。実家にほとんどあったので何度も繰り返し読んでいました。
——中学生から大学生のころまで、学生時代の本の思い出はありますか?
朝井:それは沢山ありますよ〜。一番覚えているのは、読むほうより書くほうの思い出になってしまいますが、やっぱり高校時代に初めて小説の新人賞の一次選考を通過したときのことです。さくらももこさんの『ひとりずもう』というエッセイが大好きで、そこにはさくらさんの投稿時代のエピソードが収録されているんですね。あのさくらももこさんにも“自分の名前が雑誌に初めて掲載される”という時代があって、そのシーンの描写がすごく印象的だったんです。『もう一歩賞』みたいなところに自分の名前があるのを見て、腰を抜かして立てなくなる、みたいな。私が新人賞の一次選考を初めて通過したのは高校3年生のときだったのですが、学校の帰り道、駅の近くにある書店に駆け込んで、結果が掲載されている文芸誌を手に取ったとき、そのシーンを思い出したんです。もし名前が載っていたら自分はどんなふうになるんだろうって。そして、いざ一次選考通過者の中に自分の名前を見つけたとき、本当に震えて、手汗が湧き出てきて、立っていられなくなって。さくらさんが描写していたあのシーンが、ようやく本当の意味で自分の心の中に入ってきたような気がしました。自分の大好きな本と自分自身が細い光みたいなもので繋がれた感覚を抱いたんですね。 あれはこれからもずっと忘れないと思います。
あとは、大学受験に向けて国語の過去問を解いていたときのことも思い出深いです。試験って時間との勝負じゃないですか。とにかく急がなきゃいけないのに、題材になっている小説にしっとり浸ってしまったんです。それは堀江敏幸さんの「スタンス・ドット」という作品で、時間を忘れて読まされる何かがあったんですね。点数は散々だったんですけど、そのあと、その小説が収録されている本を探して読んでみたんです。『雪沼とその周辺』という短編集で、当時の自分は正直その内容を理解できてはいなかったと思います。でも、自分の知らない表現というか、この単語をこういうシーンで使うんだ、みたいな驚きが沢山あって、著者名を記憶していたんですね。その後いざどの大学を受験するか決めるために大学図鑑みたいなものを見ていたら、早稲田大学文化構想学部の教授一覧のところに堀江敏幸という名前があったんです。あの小説を書いた人だと気づいて、第一志望が決まりました。「スタンス・ドット」との出会いは、その後の自分の人生の方針を定めてくれたという意味で、すごく記憶に残っています。
——模試や過去問を通じて色々と文章は読まれたかと思いますが、読んでそこまで心に響いたのは「スタンス・ドット」が初めてだったんですね。
朝井:それまでは共感とか物語の起承転結とか、そういう部分で小説を面白がっていたのですが、「スタンス・ドット」は当時の自分には読み解けない巨大な何かを感じて、それが心に響いたんだと思います。今も読み解けてはいないと思いますが。
もっと直接的な読書の思い出でいうと、高校生のときに読んだ佐藤多佳子さんの『一瞬の風になれ』は、初めて“この本に書かれている時間は自分の人生には訪れないものなんだ”と強烈に意識させられた本で、とても印象深いです。この本がきっかけで、「学生っていう肩書きでできることは全部やらないともったいないな」と思うようになりました。このまま一生読み終わりたくない、と初めて痛感した本です。
あと、記憶が正しければ早稲田大学の中央図書館には古典の初版本が保管されていて、そこで谷崎潤一郎の『春琴抄』の初版本を借りたこともいい思い出です。たしか、真っ赤なケースに入っていて、それを持ち歩いているときは自分に不思議なパワーが宿っている気がしていました。大学の施設はもっと利用しておけばよかったですね。
面白い瞬間は、本気の中に眠っている
——大学時代には本を読む以外にどのように過ごしていましたか?
バイト、授業、サークルと、一般的な大学生っぽいことをしていました。私はダンスサークルに入っていて、特に1年生のときはそのコミュニティで多くの時間を過ごしましたね。
でも大学1年生が終わるタイミングでふと“このまま20歳になっちゃうのか”と思ったんです。私が中学生のときに綿矢りささんと金原ひとみさんが芥川賞を受賞されたのですが、当時のおふたりが19、20歳だったんですね。テレビでそのニュースを見たとき、金屏風の前で若いおふたりがピースしてるのがまあ衝撃的で。文壇と呼ばれる場所はとても遠いと思っていたけれど、そんなに年齢の変わらないふたりがその場所にいる姿を見て、「自分もあそこに行きたい、行けるのかも」と思っちゃったんですよね。
でもあっという間に大学1年生が終わろうとしていて、このままだとすぐにおふたりの年齢を超えてしまうと焦りました。それで、大学2年生になる前の春休みに、一念発起して書いた小説を新人賞に投稿しました。それが『桐島、部活やめるってよ』です。
だから、自分の大学生っぽい思い出っていうのは最初の1年間に凝縮されている感じですね。
——高校生・大学生の時はどんな学生でしたか?
やっぱり文章を書くのが好きだったので、「だったら材料を集めなきゃ」「学校っていう場所で経験できるものは全部コレクションしておかないと」みたいな学生でした。行事には何にでも手を出していたと思います。とにかく “学校”で経験できるものを収集してましたね。
——作家以外の場面で、そういった“収集”が生きた場面はありますか?
例えば友人の結婚式で本気の余興をやる、みたいなのは当時の名残りだと思います。色々やってみて思ったのは、結局一番思い出になるのって、何かを本気でやったときに起こる事故とか、滑稽と隣合わせの変な瞬間なんですよ。本気でやって成功しなくてもいいんです。本気でやったからこそ滲み出るおかしみみたいなものが、結局何年経っても面白いんですよね。今でも、こんなことしても無駄かな〜とか斜に構えかける瞬間ってあるんですけど、そういうときこそ“本気でやる、真剣にやるっていう中に一番面白い瞬間が眠っている"という教訓を思い出すようにしています。
朝井リョウ(あさい・りょう)/岐阜県生まれ。小説家。『桐島、部活やめるってよ』で第22回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。『何者』で第148回直木賞、『世界地図の下書き』で第29回坪田譲治文学賞、『正欲』で第34回柴田錬三郎賞を受賞。最新刊は10月発売予定の『生殖記』(小学館)。