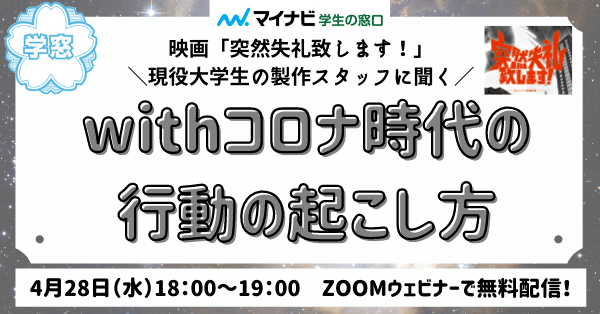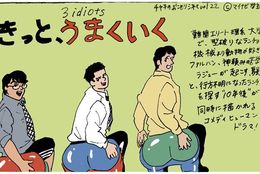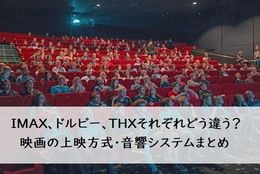全国120大学協力映画『突然失礼致します!』製作スタッフに聞く、withコロナ時代の行動の起こし方」後編 #学窓きっかけLIVE
4月28日(水)に開催したオンラインイベント「全国120大学協力映画『突然失礼致します!』製作スタッフに聞く、withコロナ時代の行動の起こし方」のログ記事【後編】をお届けします。
映画『突然失礼致します!』は、学生たちが「コロナ世代、映画で闘う」をキャッチコピーに掲げて製作したオムニバス映画で、1作品1分以内の短編180作品で構成されています。後編では、製作スタッフがイベントの視聴者からの質問に回答! イベントに参加した方はその振り返りとして、参加できなかった方は内容を参考に自分の仕事との向き合い方を考えてみてください。
登壇スタッフ紹介

登壇者:熊谷 宏彰さん
群馬大学社会情報学部4年。群馬大学映画部【MEMENTO】部長(創設者)。2020年4月よりSNS上で全国の大学生へ合同映画制作を呼びかけ、120以上の団体を繋げてコミュニティを形成した。『突然失礼致します!』では総監督・製作総指揮を担当し、劇中作『主よ、人の望みの喜びよ』の監督を務めた。 Twitter:https://twitter.com/hialloki
登壇者:森 孝史さん
埼玉大学教育学部4年。埼玉大学 映像制作サークルMaVie所属。前田柊監督の長編映画『情の時代』でプロデューサーを担当し、渋谷ユーロスペースでの劇場公開を実現した。『突然失礼致します!』では広報を担当し、クラウドファンディングにおいて約120万円の資金調達に貢献した。 Twitter:https://twitter.com/morinotakashi
登壇者:沼部一輝さん
福島大学人文社会学群4年。福島大学映画制作サークル元代表。1年次に監督した短編映画『ただいま』が東北電力主催「TOHOKU LOVE GAKUSEI MOVIE CONTEST」にて入選。『突然失礼致します!』では劇中作『また会う日まで』の監督を務めた。 Twitter:https://twitter.com/fumovietw1
登壇者:岡 愛摘さん
立命館大学映像学部3年。立命館大学メディアアートサークルREMに所属。京都市交通局主催のプログラムで四条駅・京都駅にデジタルサイネージを掲出した。『突然失礼致します!』では、人気投票第1位の劇中作『私のアオイトリ』の監督を務めた。 Twitter:https://Twitter.com/A_zuRitsuYuzu
登壇者:永田 日菜子さん
熊本県立大学総合管理学部4年。熊本県立大学映像研究部元代表。高校時代に所属していた放送部で動画編集と出会い、大学生になって本格的に映像制作を始める。撮影・編集だけでなく役者も経験している。『突然失礼致します!』では劇中作『模索』の監督を務めた。 Twitter:https://twitter.com/pukeikenコロナ禍に打ち勝つ方法は「正攻法“以外”のやり方で勝負」
――ここからは視聴者質問です。「人と共有できる趣味がなくて悩んでいるのですが、皆さんはどうされていますか?」
岡 趣味については、「今までこういうことを褒められた」「これは長続きしたな」ということがあれば、そこを突き詰めてみるといいと思います。私の場合は絵でした。趣味の共有は家族や友達、SNSでやってみるといいのではないでしょうか。身近なことから一歩ずつ始めることが大事だと思います。
――「映画サークルに所属していますが、コロナで先行きが見えません。皆さんはコロナ禍にどうやって打ち勝ちましたか?」
熊谷 打ち勝ったかはわかりませんが(笑)、コロナ禍でも映画の製作はできますから、そのやり方の勝負だと思います。正攻法ではなく、必要最少人数で行うなど撮影方法を工夫すれば、作れるものは作れます。でも、映画は楽しまれてなんぼの大衆娯楽ですから、作ったものをどう広げるのかも一緒に考えたほうがいいと思います。
――「夢を追うのではなく、安定した会社に就職しろと親に言われるのですが、私は役者になりたいと考えています。皆さんは親に何か言われましたか?」
永田 私も親に「安定した職に就きなさい」と言われ続けていますが、夢は諦めません。安定した職に就きながら、副業で絵を描きたいと考えています。ラランドのサーヤさんのように、普通の会社員として働きながら芸人をやっている人もいます。どうしても生活するうえでお金は必要になるので、安定した会社に務めながら、役者を目指す道もあるんじゃないかなと思います。
挫折しそうなときも、もうひと踏ん張りする方法
――「企画を打ち立てて、実行に移すまでのモチベーションの保ち方を教えてください」
沼部 「人を想うこと」だと思います。普段、僕はサークルで映像編集をしていますが、しんどいときもあります。でも、ここで投げ出したら脚本家や役者、カメラマンさんたちに迷惑かかるし、みんなの思いを踏みにじることになる。そうやって人を想うことがモチベーションに繋がると思います。
――「壁にぶつかったとき、どのような方法でアイデアを生み出したのでしょう?」
沼部 アイデアは基本、掛け算だと思っています。「コロナ禍で対面の撮影はできない」「では、自分たちは何ができるのか」「スマホ一個で映画は撮れる」「だったら家と家をつないで映画にしてしまおう」といった感じです。コロナ禍という状況を逆手にとって、むしろアイデアの種にする方法を僕はとります。
――森さんに質問です。「オンライン上で活動を進めるにあたって、連絡漏れなどをどう解決しましたか?」
森 重要な連絡は、常にZOOMを開きながら行っていました。例えばクラウドファウンディングのページを作るときも、ページ画面を誰かが共有しながら「この文章はこう変えたほうがいいんじゃない?」「この画像を今作ってください」といった具合に、オンラインでもその場に一緒にいるような空間を作ったことで、連絡漏れは減らせたと思います。
――熊谷さんに質問です。「このプロジェクトで挫折しそうになったタイミングはありましたか?」
熊谷 まずは企画段階です。前代未聞の取り組みだったので、どう実現すればいいのか苦心しましたし、途中で挫折しそうにもなりましたが、必死に考えて実行していきました。やればなんとかなりますね。
それと、学生映画というものは、作った作品を広げていくという文化があまりないんです。だから、作り終わったあとに、いざ広報をやるタイミングで、みなさんのモチベーションがだんだんと下がってしまいました。それを持ち直す方法がなかなか思い浮かばず、挫折しかけましたね。そこで「劇場公開しますよ!」と、皆さんがロマンを感じそうな共通目標を提供したことでモチベーションも保つことができ、高いチームワークを築けたと思います。
苦手なものにチャレンジすることの重要性
――「映画の続編はありますか?」
熊谷 具体的な言及はまだできませんが、強いて言えば、コロナ禍でこれだけいろんな大学と一本の映画を撮ったので、次はアフターコロナでいろんな大学と一本の映画を撮ってみたいと考えています。
――「おすすめの映画を一本挙げるなら?」
永田 『サーチ』です。全編がパソコンの画面上で繰り広げられる映画で、「こういう撮影のやり方もあるんだな」と、新しい発見にもなりました。
沼部 僕は『スクール・オブ・ロック』ですね。主人公が学校の先生になって生徒とバンドをやる話なのですが、その主人公がまぁだらしなくて(笑)。人の愚かさを描きつつも、いろんな人を巻き込んで面白い展開になるんです。これぞ人間のあり方だよな、っていう感じがして好きです。
――「コロナ禍で学校に行けないのですが、大学生活をどう充実させればいいでしょう?」
岡 できないことも多くて、不安になることも多いと思いますが、身近なことからでいいので、少し新しいことしてみるのがいいと思います。「コロナ禍だからできない」じゃなくて、「コロナだからこそ何ができるのか」と、逆転の発想でポジティブに物事を考えれば、気持ちも少し晴れると思います。
――まだサークルを探している最中なのですが、映画を作る楽しさって何ですか?
熊谷 作り手のイメージを「映像」という最もわかりやすい媒体で提示できることです。自分の思いを形にできることって、なかなかありませんから。例えば文章もそうですが、映像はもっと直接的に伝わるという意味で楽しいと思います。
――「あえて苦手なジャンルの映画を見たり、何か苦手なことにチャレンジしたりすることはありますか?」
森 私は人前で話すことや人をまとめて動かすことは大嫌いでした。もともと、教室の端っこに2〜3人で集まって話しているタイプの人間だったんです。でも、実際に苦手なことに挑戦してみると、ちょっとできただけでめちゃくちゃ嬉しいんです。こうしてZOOMで人前で話せたときとかも、「やってやったぜ!」って気持ちになるので、苦手なことへの挑戦は、自己肯定感を上げるうえでもおすすめです。
熊谷 好きなことにだけチャレンジしていても、身に付くものは少ないと思います。オールマイティに対応できるよう、いろんな物事にチャレンジしていくことは大切です。いろんな苦手なものにチャレンジして、トライ&エラーを繰り返すことには意味があると思うので、苦手なことにも積極的に関わってみてください。
――それでは最後に、視聴者にコメントをお願いします!
熊谷 とりあえず、思ったことは全部やってみましょう! そして皆さんに『きっとうまくいく』という映画を推薦します。あれを観ていると、多分なんかできるような気がしてきます。皆さんもぜひ、何か始めてみてください。