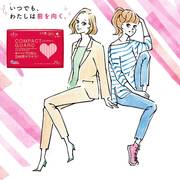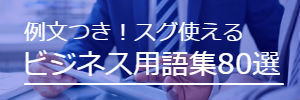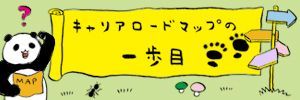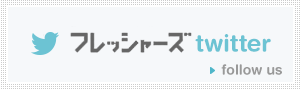- フレッシャーズトップ
- >ビジネスマナー
- >ビジネス用語
- >ビジネスで頻出! 「頂く」と「いただく」の正しい使い分けを解説【例文つき】
ビジネスで頻出! 「頂く」と「いただく」の正しい使い分けを解説【例文つき】
「先生からお手紙を頂いた。気にかけていただいたことがうれしかった」──こんな文章を読むと「あれ、同じ文書の中で「頂く」と「いただく」を使ってもいいの? 統一しなくちゃいけないはず」と思う人がいるかもしれません。
確かに、基本的に同一文書の中では漢字の表記を統一するというルールがあります。では、単純な間違いなのか、あるいは何か理由があるのか……答えは後者です。
個人的な手紙やメールではどちらでもかまいませんが、公文書やそれに準じるビジネス文書では、「頂く」と「いただく」を使い分けるのが基本。今回は、その使い分け方について解説します。
みなさん、「お読みいただけますか?」
▼こちらも合わせてチェック!
【人間力診断テスト19選】仕事、恋愛、お金…… あなたの社会人力は?
「頂く」「いただく」の意味
「頂く」「いただく」には次のような意味があります。
[他動詞]
1)頭の上に載せる。また頭上高くに位置させる。
2)敬意を表して、高くささげる。
3)上の者として敬い仕える。
4)(2)の意から「もらう」の謙譲語。Aからもらうという動作について、Aを高める。頂戴する。
5)「食べる」「飲む」の謙譲語。また「風呂に入る」意の謙譲語。
6)「食べる」「飲む」の丁重語。また「風呂に入る」意の丁重語。
*高めるべき人物が曖昧になり丁重語化したもので本来は誤り。
7)利益となるものを苦労もなく手に入れる。
II
[補助動詞]
1)「……ていただく」「お/ご……いただく」の形で)謙譲。「Aに……てもらう」という動作についてAを高める。
2)(「……(さ)せていただく」のかたちで)させていただく。
IIは、かな書きも多い。
(『明鏡国語辞典 第三版』大修館書店)*「戴く」は常用漢字外
このなかで、「頂く」は主に(4)(5)(6)(7)の「もらう」の謙譲語、「食べる」「飲む」の謙譲語という意味で使われます。ただし、「戴く」が常用漢字外であるため、(1)(2)(3)の意味でも使われることがあります。
また、「いただく」は主に補助動詞として使われ、他の動詞に「へりくだる意味」を加える働きがあります。
「頂く」「いただく」の正しい使い分けとは?
「もらう」「食べる」「飲む」「風呂に入る」の謙譲語として使う場合は、漢字の「頂く」を使います。本動詞(動詞として本来の意味を保持している自立した動詞のこと)としての用法です。ただし、食事の時の「いただきます」の挨拶はひらがなです。
また「書かせて+いただく」「お+送り+いただく」のように他の動詞を補助する場合は、補助動詞としての用法です。ひらがなの「いただく」を使います。
この使い分けは、『公用文作成の考え方』(文化庁)によるものです。「頂く」と「いただく」以外で、次の語でも同じように使い分けます。
例)
頂く → ……(し)ていただく
下さる → ……(し)てくださる
行く → ……(し)ていく
来る → ……(し)てくる
欲しい → ……(し)てほしい
良い → ……(し)てよい
(実際の動作・状態等を表す場合は「…街へ行く」「…賞状を頂く」「…贈物を下さる」「… 東から来る」「しっかり見る」「資格が欲しい」「声が良い」のように漢字を用いる)
(出典:『公用文作成の考え方』文化庁)
この使い分けは公用文やそれに準じるビジネス文書での場合です。ビジネス文書にもさまざまなタイプがあります。まず、企業であっても、自治体に提出する書類や公的・恒久的に使用する文書では、このルールに準じるとよいでしょう。いっぽう、広告などでやわらかいイメージにしたい場合は、「食べる」「飲む」「風呂に入る」のへりくだる意味をひらがなで書いてもかまいません。臨機応変に使い分けましょう。
▼こちらも合わせてチェック!
「下さい」と「ください」の違いって? ビジネスでの正しい使い分けを解説【例文つき】
「頂く」「いただく」を使う際の注意点
「頂く」「いただく」は、ビジネスでも日常生活でも非常によく使われますが、その分誤用も多い言葉です。特に次の点に気をつけて使いましょう。
丁重語はもともと誤用
意味の段でも述べたように、本来目上の人物が用意してくれたものを「食べる」「飲む」「風呂に入る」という意味で、謙譲語として使われていました。しかし、近年は単に「食べる」「飲む」「風呂に入る」の丁重語としても使う人が増えています。
ただし、あくまで慣用化の途上にあるというだけです。例えばSNSなどで「昨夜は日本酒を頂きました」という表現はさほど不自然ではなくても、「毎日、お風呂を頂かないと落ち着きません」という表現はやや違和感があります。もちろん、受け手の感じ方にも個人差はありますが、丁重語の用法はもともと誤用であるため、ビジネスや公的な場面では謙譲語の用法にとどめるのが無難です。
「いただく」は相手や第三者を主語にできない
補助動詞としての「いただく」は「(私は)先生にご指導いただいた」のように使います。この場合の主語は隠れていますが、恩恵を受けた「私」です。「先生がご指導いただいた」のように「先生」(恩恵を与えた人)を主語とすることはできないので気をつけましょう。
「頂く」を尊敬語としては使えない
「食べる」「飲む」「風呂に入る」を「どうぞ温かいうちに頂いてください」「お風呂が沸きましたので頂いてください」のように尊敬語として使うのは、完全な誤用です。また「どうぞ温かいうちに召し上がってください」「お風呂が沸きましたのでお入りください」が正しい言い方です。
「頂く・いただく」の使い方・例文
「頂く」と「いただく」は実際のビジネスシーンでどのように使えるでしょうか。場面や例文とともに見ていきましょう。
「頂く」の使い方と例文
打ち合わせや雑談、メールや文書など場面に合わせて謙譲語として「頂く」を使ってみましょう。
取引先や上司など目上の人物から物をもらった場合
取引先や上司などからお土産や贈り物などをもらい、お礼の言葉を対面・手紙・メール・メッセージで述べることがあります。そんな時は、「もらう」のへりくだった表現である「頂く」を使います。
・(取引先との会話で)先日はスタッフにお土産を頂き、誠にありがとうございました。
取引先や上司など目上の人物から形のないものをもらった場合
物だけでなく、言葉など形のないものについても「頂く」を使えます。上司からのアドバイスやお客様からの褒め言葉などをもらった場合に、使ってみましょう。
・(お客様に)うれしいお言葉を頂き、こちらこそ感謝申し上げます。
取引先や上司などに協力や助言をもらいたい場合
ビジネスでは得意先・お客様・仕入れ先に支援や協力を願ったり、上司など目上の相手に相談をもちかけたりすることがあります。例えば、メール・依頼状や会話で「頂く」を使ってみましょう。
・(先輩や上司に)明日の昼休みに、少しだけお時間を頂けないでしょうか。
「食べる・飲む」意味をへりくだる場合
目上の人物から食事や飲み物をごちそうになる場合に「頂く」を使えます。
「いただく」の使い方・例文
「(Aに)お/ご……いただく」は、「(Aに)……てもらう」という意味で、Aの動作についてAを高める謙譲語です。Aから受ける恩恵の意味も含まれます。「(Aに)お/ご……させていただく」は、「(Aに)……させてもらう」という意味で、Aの許可を得て行う動作についてAを高める謙譲語です。Aから受ける恩恵の意味も含まれます。
このことを踏まえて、目上の相手に何かをしてもらった場合や、許可を得て自分側が何かをさせてもらった場合に「いただく」を使ってみましょう。
来店や来場、日頃のお礼を伝える場合
イベントや発表会に来てもらったり、日頃お世話になったりしているお礼を伝える時に「……ていただく」「お/ご……いただく」の形で使えます。
・(上司に)いつも励ましていただき、感謝しております。
取引先や上司など目上の相手に何かを依頼したい場合
仕事で何かを頼みたい時に「……ていただく」「お/ご……いただく」の形で使えます。
・(上司に)実は部長にアドバイスしていただきたい件がございます。
許可を得て何かを行う場合
「……(さ)せていただく」は自分が何かを行うために相手の許可を得る場合、あるいは許可を得ると見立てた場合の表現です。許可が全く必要ない場面では、本来使いません。
逆は必ずしも真ならず
今回、本動詞は「頂く」、補助動詞は「いただく」が基本であると述べました。しかし、あくまで公用文の基本とされているという意味で、「逆は必ずしも真ならず」です。「頂く」と書かれていたら本動詞、ひらがなで書かれたものは補助動詞と機械的に判断できるわけではありません。
本動詞でもひらがなが使われていたたり、補助動詞でも漢字が使われていたりすることはいくらでもあります。同一文書の中で、同じルールで書かれていれば問題はありません。意味の違いを把握して、その場面でふさわしい使い分け方を判断するようにしましょう。
(前田めぐる)
※画像はイメージです
関連記事
新着記事
-
2025/10/21
-
2025/09/29
-
2025/09/13
-
2025/08/11
-
2025/08/09
【お盆に読みたい】家族問題の第一人者が綴る。あなたを責めつづける心の中の「お母さん」を手放すと起こる「人生の変化」とは?
HOT TOPIC話題のコンテンツ
-
PR
【診断】セルフプロデュース力を鍛える! “ジブン観”診断
-
PR
いつでもわたしは前を向く。「女の子の日」を前向きに♪社会人エリ・大学生リカの物語
-
PR
社会人デビューもこれで完璧! 印象アップのセルフプロデュース術
-
PR
あなたの“なりたい”社会人像は? お仕事バッグ選びから始める新生活
-
PR
視点を変えれば、世の中は変わる。「Rethink PROJECT」がつたえたいこと。
-
PR
ウワサの真実がここにある!? クレジットカードの都市伝説
-
PR
実はがんばりすぎ?新社会人『お疲れ度』診断
-
PR
忙しい新社会人にぴったり! 「朝リフレア」をはじめよう。しっかりニオイケアして24時間快適。