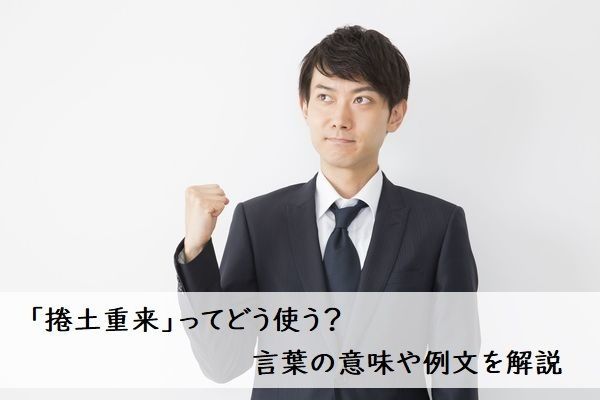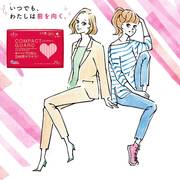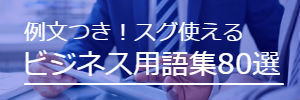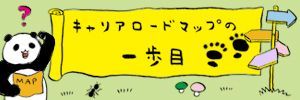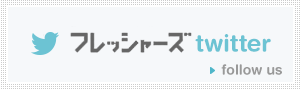- フレッシャーズトップ
- >ビジネスマナー
- >ビジネス用語
- >「捲土重来」とは? 意味、由来、使い方、類義語、対義語を解説【例文つき】
「捲土重来」とは? 意味、由来、使い方、類義語、対義語を解説【例文つき】
「捲土重来」とは、土煙が巻き上がるような勢いを取り戻して、巻き返していく様子を表した四字熟語です。読み方は「けんどちょうらい」、あるいは「けんどじゅうらい」。
難しい漢字を含む言葉ですが、最近では人気ゲーム「ウマ娘」のスキル名にも採用され「さあ、ここから捲土重来!」といったSNS投稿を目にするようになりました。
今回は、この「捲土重来」の意味や使い方、類義語や対義語をご紹介します。ビジネスシーンでも登場する言葉なので、覚えておくと便利ですよ。
▼目次
1.捲土重来の意味とは
2.捲土重来と臥薪嘗胆の違い
3.捲土重来の使い方を例文でチェック
4.捲土重来の類義語と言い換え表現
5.捲土重来の対義語
6.英語で言うと?
7.まとめ
▼こちらも合わせてチェック!
【人間力診断テスト19選】仕事、恋愛、お金…… あなたの社会人力をチェックしてみよう
捲土重来の意味とは
捲土重来(けんどちょうらい)とは、一度敗れたり失敗したりした者が、再び勢いを取り戻して巻き返すことを意味します。
捲土重来の「捲土」は「捲(まく)る」に「土」で土煙を巻き上げること。これは勢いが激しいことのたとえです。「重来」は「再びやって来る」こと。
このことから「土煙を巻き上げるような勢いをもって、今一度盛り返して攻めてくる」といったニュアンスを持っています。
捲土重来の由来
「捲土重来」は、唐の詩人・杜牧(とぼく)による詩「題烏江亭」の一節「捲土重来、未だ知る可(べ)からず」が基になってできた故事成語です。
この詩は「劉邦(りゅうほう)と天下を争うも、垓下(がいか)で戦いに敗れ自決した、秦末期の楚の人・項羽(こうう)」をしのび、杜牧が烏江亭を訪れたときに作ったものだといいます。
(意味)
負けた者(項羽)が土煙を巻き上げるような勢いで再び攻めてきていたならば、(勝敗は)どうなっていたかわからない。
このような杜牧の思いが詠われています。
現代では、そこから転じて、「一度敗れた(失敗した)者が、再び勢いを盛り返して巻き返す(再起をはかる)」意味の言葉として使われています。
捲土重来と臥薪嘗胆の違い
臥薪嘗胆(がしんしょうたん)も中国の故事にまつわる四字熟語です。漢字が難しいので分解すると、
「薪」→(固い)たきぎ
「嘗」→なめる
「胆」→(苦い)きも
となります。
固いたきぎの上で寝て、苦いきもをなめることであえて苦労を重ね、復讐心や悔しさを忘れずにいようとする様子をあらわしています。そこから「仇(あだ)を打つために苦しい状況に耐え忍ぶこと」という意味になっています。
この「臥薪嘗胆」も「捲土重来」も、ともに「一旦は敗れている」という点で共通していますが、そこから先が異なります。
捲土重来が「勢いよく反撃に出る」ニュアンスなのに対して、臥薪嘗胆の方は「苦しい状況であってもくさらず、地道に努力する」というニュアンス。捲土重来の方がよりアクティブなイメージであることが分かりますね。
▼こちらも合わせてチェック!
臥薪嘗胆ってどういう意味? 由来や使い方、類語を例文つきで解説
捲土重来の使い方を例文でチェック

「捲土重来」の例文を見てみましょう。
基本の例文
上記は、前回の大会では負けてしまったが、今大会ではまた盛り返して初戦を突破した、という意味になります。
「捲土重来を期す」の例文
非常によく使われているのが、「捲土重来を期す」というフレーズです。まずはこのフレーズから覚えることをおすすめします。
読み方は「けんどちょうらいを きす」となり、「これからの巻き返しを心に誓う」という意味合いです。
・昨シーズンが振るわなかったB選手にとって、今年は捲土重来を期す年である。
上記のいずれも、「これから勢いよく巻き返したい(そのために努力する)」というニュアンスで用いられています。同じように「捲土重来を期待する」と表現することもあります。
「捲土重来を果たす」の例文
さらに、「捲土重来を果たす」のフレーズでも使われます。
上記は「新製品の投入という戦略によって、見事に巻き返すことができた」の意です。例えば売上がV字回復したようなときにピッタリの表現でしょう。ライバル会社を追い抜いたときにも「捲土重来だ!」と言いたくなりますね。
このように、「捲土重来」はビジネスやスポーツや政治などで「満を持して挑んだ勝負ごとに敗れた人が、巻き返しを図る様子」をあらわす表現として使われます。
捲土重来の類義語と言い換え表現
捲土重来の類義語と言い換え表現には、次のようなものがあります。
⇒今にもダメになりそうな局面から復活すること
例)起死回生を図る。
●反転攻勢
⇒守りの情勢から翻って、攻めに転じること
例)反転攻勢に向けて〜
●リベンジ
⇒復讐・仇討ち・一度負けた相手に勝つこと
例)何とかリベンジしたい。
●名誉挽回
⇒失った名声をとり戻すこと
例)名誉挽回のチャンスだ。
そのほか、シンプルに捲土重来の意味である「巻き返す」「盛り返す」「反撃に出る」などと言い換えることもできます。
捲土重来の対義語
捲土重来と反対の意味を持つ対義語には、次のようなものがあります。
⇒失敗や挫折から元の状態に戻れないこと
●一蹶不振(いっけつふしん)
⇒一度の失敗で挫折し、二度と立ち直れないこと
英語で言うと?
もとは中国語に由来する「捲土重来」ですが、英語でも「make a comeback(盛り返す)(返り咲く)(復活する)」、「regain lost ground(失地回復する)」など、いずれも「捲土重来」に非常に近いニュアンスを持つ言葉があります。例を挙げてみましょう。
(その選手は見事な再起を果たした)
・The company should regain lost ground.
(その会社は失地回復を図るべきである)
まとめ
争いごとに負けても、大切なことに失敗しても、めげずに挽回を図るのが「捲土重来」。そんなハングリーな精神を忘れず、勉強やスポーツにも取り組みたいですね!
(マイナビ学生の窓口編集部)
▼こちらもチェック
・朝令暮改とは? 意味やビジネスでの使い方などを例文つきで解説・一生懸命とは? 一所懸命との違いや正しい意味、類語を解説【例文つき】
・初志貫徹ってどう使う? 意味と使い方を例文つきで解説!

学生の窓口編集部
「3度のご飯よりも学生にとっていいことを考える!」の精神で 大学生に一歩踏み出すきっかけコンテンツをたくさん企画しています。 学生生活に役立つハウツーから、毎日をより楽しくするエンタメ情報まで 幅広く紹介していますので、学窓(がくまど)をチェックしてみてください!
関連記事
新着記事
-
2025/10/21
-
2025/09/29
-
2025/09/13
-
2025/08/11
-
2025/08/09
【お盆に読みたい】家族問題の第一人者が綴る。あなたを責めつづける心の中の「お母さん」を手放すと起こる「人生の変化」とは?
HOT TOPIC話題のコンテンツ
-
PR
ウワサの真実がここにある!? クレジットカードの都市伝説
-
PR
実はがんばりすぎ?新社会人『お疲れ度』診断
-
PR
【診断】セルフプロデュース力を鍛える! “ジブン観”診断
-
PR
忙しい新社会人にぴったり! 「朝リフレア」をはじめよう。しっかりニオイケアして24時間快適。
-
PR
視点を変えれば、世の中は変わる。「Rethink PROJECT」がつたえたいこと。
-
PR
あなたの“なりたい”社会人像は? お仕事バッグ選びから始める新生活
-
PR
社会人デビューもこれで完璧! 印象アップのセルフプロデュース術
-
PR
いつでもわたしは前を向く。「女の子の日」を前向きに♪社会人エリ・大学生リカの物語