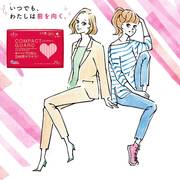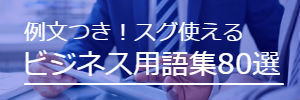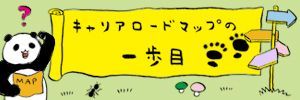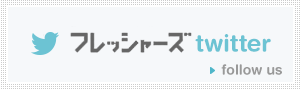- フレッシャーズトップ
- >お金の知識
- >投資・ローン
- >「インフレ」とは? 意味とメリット・デメリットを詳しく紹介!
「インフレ」とは? 意味とメリット・デメリットを詳しく紹介!
大学生のみなさんは、インフレとはどういう状況を指すのかきちんと説明できますか? 子どものころ、社会科の授業で習ったものの、いざ説明するとなると自信がないという人も多いでしょう。このインフレとは、いったいどういった現象なのか? 社会人になったら知っておきたい、「インフレとは?」について今回は説明していきます。
▼こちらの記事もチェック!
不景気とはいうけれど...。サラリーマンの生活は本当に厳しいの?
■インフレとは物価が上昇し続ける現象
インフレはインフレーション(Inflation)の略です。インフレーションの意味について『広辞苑 第六版』には、
・(通貨膨張の意)通貨の量が財貨の流通量に比して膨張し、物価水準が持続的に騰貴すること。その原因により需要インフレ・コストインフレなどに分類される(P.225より引用)
とあります。景気がよくなればお給料も増え、みんながどんどんお金を使ってたくさんモノを買うようになります。このとき需要が供給を上回ることで、モノ(供給)の価値が高まります。例えば100円で買えていたものが、需要が増えることで200円になったりする、ということ。ただ、景気がよければ給料もどんどん上がりますから、物価が上がっても変わらずモノを買えば、物価もさらに上昇していきます。これが継続するのがインフレです。
■インフレになる原因は?
広辞苑の説明には、インフレの原因として「需要インフレ」と「コストインフレ」が挙げられています。この2つはインフレの大きな原因となるものです。それぞれどういうものか見ていきましょう。まずは需要インフレからです。
需要インフレとは、その名のとおり需要が拡大することを原因とするインフレです。需要の拡大に合わせて供給も同じペースで増大すればいいのですが、需要が大きくなるにつれて「どうしてもその商品を買いたい」という人が増えるため、モノの価値は必然的に上がります。買い手が増えて起こる場合だけでなく、深刻な物資不足になることでもこの需要インフレが起こります。昨今問題になっている、任天堂のゲーム機『Nintendo Switch』の転売問題などは、まさにこの需要インフレのスモールバージョンといえますね。
次にコストインフレです。こちらはモノを作る際の生産費の上昇を原因とするインフレです。例えば人件費(賃金)や原材料費の高騰などが原因とされます。日本でも1970年代に起きた二度のオイルショックは、このコストインフレによるものです。他にも、世の中に出回る貨幣量が増えることで起こる「貨幣インフレ」もあります。
また、インフレはその速度によっていくつかに分類されており、例えば緩やかなインフレは「クリーピング(忍び寄るの意)・インフレーション」、年間10%程度の上昇率のものを「ギャロッピング(馬の駆け足という意味)・インフレーション」、3年間で累積100%(年率約26%)といった急激な物価上昇が起こることを「ハイパー・インフレーション」と呼びます。
関連記事
新着記事
-
2025/10/21
-
2025/09/29
-
2025/09/13
-
2025/08/11
-
2025/08/09
【お盆に読みたい】家族問題の第一人者が綴る。あなたを責めつづける心の中の「お母さん」を手放すと起こる「人生の変化」とは?
HOT TOPIC話題のコンテンツ
-
PR
社会人デビューもこれで完璧! 印象アップのセルフプロデュース術
-
PR
忙しい新社会人にぴったり! 「朝リフレア」をはじめよう。しっかりニオイケアして24時間快適。
-
PR
あなたの“なりたい”社会人像は? お仕事バッグ選びから始める新生活
-
PR
【診断】セルフプロデュース力を鍛える! “ジブン観”診断
-
PR
実はがんばりすぎ?新社会人『お疲れ度』診断
-
PR
視点を変えれば、世の中は変わる。「Rethink PROJECT」がつたえたいこと。
-
PR
ウワサの真実がここにある!? クレジットカードの都市伝説
-
PR
いつでもわたしは前を向く。「女の子の日」を前向きに♪社会人エリ・大学生リカの物語