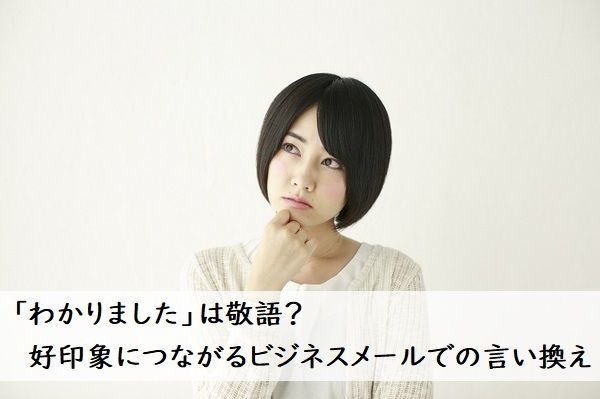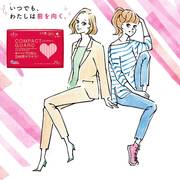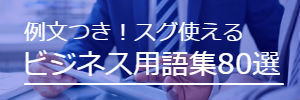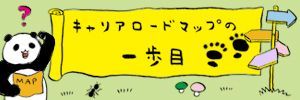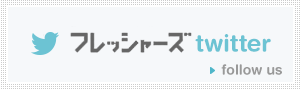- フレッシャーズトップ
- >ビジネスマナー
- >対人マナー
- >「わかりました」は敬語? 好印象につながるビジネスメールでの言い換え
「わかりました」は敬語? 好印象につながるビジネスメールでの言い換え
学生のうちは当たり前に使ってきた「わかりました」というフレーズ。たしかに明瞭かつ簡潔な言葉で、いつでもどんな場合でも、「わかりました」は誰にでも通じます。
しかし社会人の場合「わかりました」と返事をしてしまうと、「もう少し別の言い方できないの?」と思われてしまうかもしれません。特に目上の相手には、より丁寧な敬語を使うことで「ビジネスパーソンとしてキチンとしているな」と思ってもらうのも大切なことでしょう。
ここでは、「わかりました」というフレーズの敬語としての言い換え表現について解説。目上の人や上司に使う場合、大学で先生に使う場合、メールやLINEで使う場合などシーン別にご紹介します。つい言ってしまいがちなNGワードについてもあわせてチェック!
「わかりました」は敬語としてNG?
子どもから大人まで老若男女、対面やメール・電話で日常的に最も頻繁に使われるのが「わかりました」ではないでしょうか。
「わかる」
事の筋道がはっきりする。了解される。理解できる。
⇒「ました」をつけて丁寧な表現にしたもの。
「わかりました」は、丁寧語であるという意味では敬語だといえます。ですが、ビジネスマナーという観点で見ると、充分な敬語表現とは言えない面があることは事実です。
特に来客応対のようなかしこまったシーンや上司との会話で「わかりました」を使うと、やや未熟な印象となってしまいがち。そんな時は、より適切な敬語に言い換えることが大切です。ではどんな敬語表現にすると良いのでしょうか、次から見ていきましょう。
「わかりました」を適切な敬語に言い換えるなら
「じゃあ、“わかりました”は、それ以外どう言えばいいの?」
ここからは、「わかりました」の適切な言い換え表現をシーン別にご紹介していきます。
ビジネスシーンで目上の人や上司に使う場合
・かしこまりました
・承知いたしました
・承知しました
ビジネスシーンで真っ先に覚えていただきたいのは「かしこまりました」です。「かしこまる」とは、謹んで目上の人の言葉を承る、拝承する、承知するといった意味。例えばホテルやお店の受付、お客さまセンターへの問い合わせなどでは、必ずと言っていいほど耳にする言葉です。
「かしこまりました」を使うにはどこか抵抗があるという場合には「承知いたしました」というフレーズがおすすめ。先ほどの「かしこまりました」にも承知するという意味があり、ほぼ同じような意味合いで使うことができます。「いたす」は「する」の謙譲語となるため、敬語表現としても充分といえます。
似たようなフレーズで「承知しました」でもOK。こちらはもう少しくだけた表現となります。
仮にあなたが顧客や上司、取引先の立場だったとしましょう。相手に「わかりました」と返事をされるのと、「承知いたしました」と返事をされるのでは、どちらに好印象を持つでしょう。そう考えると、答えはおのずと出てくるのではないでしょうか。
もちろん「わかりました」も完全な間違いというわけではありませんが、この機会により丁寧な敬語表現「かしこまりました」「承知いたしました」をマスターしておきましょう。
大学で先生に使う場合
・承知しました
・わかりました
大学の先生(教授や講師など)も目上の人にあたりますね。ですが、あなたがまだ学生であることを考えると「かしこまりました」というのは丁寧すぎる感も(アルバイトなどで使い慣れている方はそれでも構いませんが)。
ビジネスマナーにそこまで忠実である必要はありませんが、目上の人に向けた適切な表現を心がける必要があります。この場合は「承知しました」か、あるいは「わかりました」でも問題ありません。
これまでも親しい先生に対しては「わかりました」と会話していた、という人も多いことでしょう。会話の中では「わかりました」で問題ない場合でも、メールなどの文面にした場合には表現をワンランク丁寧にした方がいいので、やはり「承知しました」がベターです。
アルバイトやパートで使う場合
・かしこまりました
・承知いたしました
・承知しました
アルバイトやパートの場合でも、仕事の現場であることに変わりありません。そのため「ビジネスシーンで目上の人や上司に使う場合」でお伝えした内容と同じ表現を使うことになります。特にお客様に対して使う場合、「アルバイトなのか社員なのか」は相手にとって関係ありませんから、きちんとした敬語表現を使うべきです。
ただし、学生アルバイト同士や歳が近いスタッフ同士の会話のときは別です。同じ職場内でかしこまりすぎても違和感があるため、「わかった」「わかりました」などを使って構いません。
ビジネスメールやLINEでの言い換え表現
・かしこまりました
・承知いたしました
・承知しました
ビジネスメールやLINEに絞ってみた場合でも、繰り返しになりますが上記3つが鉄板フレーズとなります。メールやLINEなどの文面においては相手の顔が見えない分、話し言葉よりも丁寧な言葉遣いを心がける必要があります。たとえ親しい先輩であっても上の立場の人に対しては「承知いたしました」などを使った方が無難です。
ですがこれらはあくまで敬語表現として考えた場合。同期や後輩とのやりとりなら敬語にしなくても構いませんので、これまで通り「了解!」といった表現でOKです。
「わかりました」の敬語で注意したいNGワード

「わかりました」を伝えるときに「何とか敬語にしなければ…!」という一心で、あまりふさわしくない表現をつい使ってしまうケースは多いようです。代表的な例を2つ挙げてみましょう。
了解しました
「わかりました」の代わりに「了解しました!」と出てしまうのは学生あるあるです。
物事の内容や事情を理解して承認すること。
このように「了解」には、ものごとを「理解」した上で「承認」するといった意味があります。承認という漢字から分かる通り、「認める」というニュアンスが含まれるのです。
そのため「了解しました」では、上から目線と受け取られてしまう恐れも。同僚や後輩とのやりとりなら「了解です」で問題ありませんが、目上の人に対する敬語表現としてはふさわしくありません。
了承しました
念の為「了承しました」も挙げておきます。了承(りょうしょう)も先の了解とほぼ同じ意味で用いられる言葉。ですが「承認する」の「承」という漢字が使われており、先ほどの「了解」よりもさらに「承認する」というニュアンスが強くなります。
通常、了承は目上の人から「了承を得る」といった使い方をします。反対に下の立場から「了承する」というのは不適切です。くれぐれも使わないように気をつけましょう。
「わかりました?」と確認したいときの敬語表現
続いては、「わかりましたか?」と相手に確認したいときの敬語表現をご紹介します。目上の人や上司に向けてそのまま「わかりましたか?」と聞いてしまうのはNG。先方としては内心カチンときてしまうかもしれません。
・ご理解いただけましたでしょうか。
・ではこの件はよろしいでしょうか。
・何かご不明な点はございますでしょうか。
ここでは「〜でしょうか」という表現をご紹介しています。「〜でしょうか」にすると、声に出したときに語尾を上げなくてもすみます。語尾を上げない方が、受け取る側にとってはソフトに聞こえますので、是非活用してみてください。
まとめ
人としてだけでなく、ビジネスパーソンとして他者とよりよいコミュニケーションを図るには「どんな言葉を使うか」がとても大切。何気ない一言で相手の気分を害してしまうのはもったいないですよね。
「わかりました」は間違いではありませんが、ビジネスシーンでは「かしこまりました」や「承知いたしました」に言い換えるのがマナーです。ただし親しい先輩には「承知しました」「わかりました」でもOK。取引先や上司など、使うべき時にはしっかりと敬語を使うように、メリハリをつけていくといいでしょう。
文:マイナビ学生の窓口編集部
関連記事
新着記事
-
2025/10/21
-
2025/09/29
-
2025/09/13
-
2025/08/11
-
2025/08/09
【お盆に読みたい】家族問題の第一人者が綴る。あなたを責めつづける心の中の「お母さん」を手放すと起こる「人生の変化」とは?
HOT TOPIC話題のコンテンツ
-
PR
実はがんばりすぎ?新社会人『お疲れ度』診断
-
PR
【診断】セルフプロデュース力を鍛える! “ジブン観”診断
-
PR
いつでもわたしは前を向く。「女の子の日」を前向きに♪社会人エリ・大学生リカの物語
-
PR
忙しい新社会人にぴったり! 「朝リフレア」をはじめよう。しっかりニオイケアして24時間快適。
-
PR
ウワサの真実がここにある!? クレジットカードの都市伝説
-
PR
社会人デビューもこれで完璧! 印象アップのセルフプロデュース術
-
PR
あなたの“なりたい”社会人像は? お仕事バッグ選びから始める新生活
-
PR
視点を変えれば、世の中は変わる。「Rethink PROJECT」がつたえたいこと。