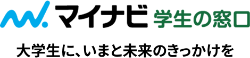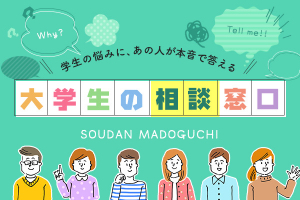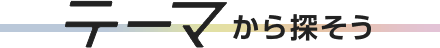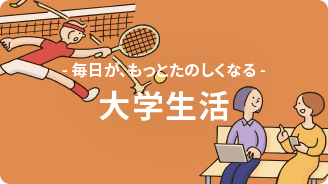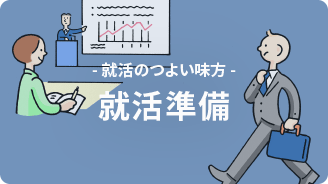「耳の聞こえない親と、耳が聞こえる子ども」コーダの宿命が未来とつながった日、迷うことなく広告代理店を辞めることに決めた。
「コーダ(Children of Deaf Adults)」とは、耳の聞こえない親を持ち、自身は耳が聞こえる子どものこと。Silent Voice(大阪市)代表の尾中友哉さんもその1人で、手話を第一言語に3兄妹の長男として育ちました。広告代理店で馬車馬のように働いていたある日の強烈な出来事を境に、自身の宿命を活かす仕事に就くことを決意。その理由や経緯を伺いました。
大阪市を拠点に活動するNPO法人。教育部門と就労部門の活動を通じてデフ*と聴者の関わりをアップデートし「共にできる」をふやし続けるNPO法人。事業拡大に伴い、新しい仲間を募集中。(*ここでは聞こえない・聞こえにくい人のこと)
1日8時間、手話通訳を担った幼少時代
―― 耳の聞こえないご両親の元、尾中さんはどんな幼少期を過ごしましたか。
3年前に僕自身が結婚し、妻の実家に行くようになって初めて、耳が聞こえる両親のいる家庭の様子を深く知りました。それは、自分の生い立ちを客観的に見る機会でもあったし、自分がどのような影響を受けて育ってきたのかを紐解く作業でもありました。 よく周囲からは「不幸」とか「不便」だと気遣いの眼差しを向けられますが、自分自身では他の家族と比べるわけでもないし、そんな風に感じることがなかったんです。
―― 不幸や不便だと思わなかったのは、ご両親の教育も影響しているのですか。
両親が相互の関係性をとても大事にしていた、というのは確かにあります。僕も両親のために何かをやることが嫌じゃなかったし、むしろ嬉しかったんですよね。
ただ、体力が尽きることはありました。今、手話通訳者を仕事にしてる人には「15分交代」のセオリーがありますが、僕は1日8時間、ぶっ通しで両親の通訳をしていたので。兄妹で年齢も1番上だったし、あらゆる役が回ってきましたね。それは今も続いていて、先日祖父が他界した時は葬儀や相続関係のことは全て僕が窓口になりました。
大手広告代理店に就職し、テレビ局担当に配属
―― 尾中さんが「Silent Voice」を起業するまでのキャリアを教えてください。
両親と僕には「聞こえる・聞こえない」の違いがあったため、何かと祖父が僕の教育やキャリアに厳しい人でした。「いい高校に入ったら近所の人が驚くぞ」と発破をかけられましたね。頑張って勉強して偏差値72の高校に行きましたが、僕は平成生まれのゆとり世代。祖父の価値観に半分は洗脳されつつも、半分は勉強アレルギーになり逃げたくて仕方ありませんでした。
そんな時に大学の授業で映像制作を体験したんです。気づいたら朝になっていたくらい熱中しました。小さい頃から僕にとってテレビは余興であり、言葉を教えてくれた日本語発信機でもあったので、自然と映像の世界に惹かれたんだと思います。競争や高収入を求める祖父の価値観と、自分のやりたいことをやろうという僕の考えをかけ合わせて、映像を扱う広告代理店に就職しました。
―― 現在からは想像できない異業種に勤めていたんですね。
入社して「局担」という部署に配属されました。ほぼ毎日、テレビ局の担当者との飲み会で、2日酔いっていう言葉じゃ足りないくらい“10日酔い”はしてました。馬車馬のように働いていたある日、どっちが地面でどっちが空なのかわからない瞬間があって、目を開けたら路上のゴミ箱に頭を突っ込んでいたんですよ。
「あれ?誰かが僕を起こしてくれている」と思ったら、相手はカラスでした(笑)。泥酔した状態でゴミ箱に頭を突っ込み、カラスの群れの中で目が覚める。働くためだけに滋賀の田舎から出てきて「僕はいったい何のために生きてるんだ…」って問いが否応なしに生まれましたね。
戸越銀座の団子屋で広告代理店の退職を決意
―― まるで漫画のようなひとコマですね…。
そんな状況のある日、当時住んでいた戸越銀座商店街でいつも行列ができていた「レモン団子」が食べたくて、店の前に並んだんです。途中で列が全く動かなくなり、客のストレスが溜まっていくのが伝わりました。前方を確認してみると最前列から聞き覚えのある呼吸音が聞こえたんです。あ、耳が聞こえないんだってすぐわかりました。呼吸が乱れると僕の父も同じ音を出していたので。
店員が聞きたかったのは、レモン団子にみたらし団子の餡がつかないようにラップで包みますか? ということ。僕がすぐに手話通訳をして事なきを得ましたが、列を見たら僕が立っていた場所は埋まっていて、戻ることができなかった。気を落として帰ろうとすると、さっきの人に肩を叩かれて「さっきはありがとう」ってお団子をもらったんです。
―― 良かったです。お団子を分けてもらえて。
もらったのはみたらし団子の方で、本当はレモン団子が欲しかった…(笑)。というのは冗談ですが、いまの僕にはこの団子を飲み込むことはできないなって思いました。それくらい、そこで起きたことは僕にとって激震が走る体験だったんです。
生きる意味を自問自答するくらい追い込まれている精神状態で、僕という個性で誰かの役に立つことができた。すごく感動したんです。それまでは、未来から逆算して現在を考えることの繰り返しでしたけど、その瞬間、自分の過去と現在と未来がつながったというか。
―― ご自身の過去、というのはどの時のお話ですか。
僕には耳の聞こえない両親がいて、日本語よりも先に手話を身につけたこと。そういう環境でずっと生きてきたこと。自分の宿命のような過去が、現在と未来とつながった。言葉で言い表すのは難しいですが、自分の情熱とかエネルギーの方向性が定まる衝撃的な体験だったんです。これからどう収入を得るかという手段の話は些末なことで、迷うことなく広告代理店を退職することに決めました。
とは言っても、そこから2年間は光回線の飛び込み営業をやったり、フリーランスデザイナーの仕事をやったりして食いつなぎました。人生の大きな目標に狙いを定めつつ、何をビジネスに起業しようか考えていましたね。
ネジを投げつけられた父。目指したのは“共創価値”
―― 起業にはどんな事業構想があったのですか。
まず、聴覚障害者と関わる仕事について調べていくと、「耳の聞こえない弱者を健常者が支援する」という構図がほとんどだと感じました。私の家族はそうした支援サービスにお世話になったので否定するスタンスではありませんが、僕自身は別の形で関わりたいなと。聞こえる人と聞こえない人の「共創価値」みたいなものをビジネスとして捉えられないかと考えたんです。
―― 聞こえる人と聞こえない人の共創価値とは何でしょう。
僕は家庭の中で両親の実力というものを常に感じて生きてきました。母は喫茶店を経営していて、大手のカフェチェーンが近くにできても客足が落ちない秀でた技を持っていました。家では僕が両親を支援するだけではなく、僕も両親に支援されてきた関係性があったから持続的だったし、貸し借りが成立していたから両親とは仲間の関係だったんだと思います。社会を見渡せば、多くの事業やサービスもそういう相互関係で成り立っていると思うんです。(もちろん無償の愛、親子関係の側面もあります)
聞こえる人と聞こえない人が共創する。それを社会で表現したらどういうムーブメントが生まれるのか、それをビジネスの軸に考えました。
―― 尾中さんが共創価値に目を向けられたのは、なぜだと思いますか。
父の場合は"聴覚障害者"というだけですごく苦労した過去があります。知識も豊富で野球もうまい実力のある父を僕は知っている。だけど、会社では名前を呼ばれる代わりに、耳が聞こえないからネジを投げつけられていたそうです。
家庭と社会に横たわるギャップは、僕の父親像に対しても葛藤を生みました。両親には社会に貢献する力があるのにって。父もかなり悔しい思いをしてきたはずです。共創価値を事業にできれば、聞こえない人の立ち位置が「かわいそう」とか「弱者」から別のものに変わる。変えたいと思ったんです。
聞こえない人の能力を聞こえる人が身につける研修プログラム
―― 現在、Silent Voiceで続けている「無言語コミュニケーション研修プログラム」が、当時尾中さんが立ち上げた事業ですよね。
そうです。うちの母が喫茶店の接客の中で発揮していた「観て気づいて行動する」というコミュニケーション能力を、聞こえる人にマスターしてもらう研修です。参加者は全員、耳栓をして音声を遮断し、言語の使用も一切禁止。その環境で、ジェスチャーや表情、仕草などから自分の伝えたいことを表現し、相手の伝えたいことを読みとるプログラムです。
この10年で接客意識向上やチームビルディングを目的に、約400社の企業研修に導入してもらいました。2017年には株式会社に加えてNPO法人も設立し、現在は14人の仲間がいる企業に成長しました。新たに教育事業も行っています。
DENSHIN(デンシン)- 無言語コミュニケーション研修プログラムについてhttps://denshin.silentvoice.co.jp/
―― Silent Voiceが今後、力を入れていきたいことを教えてください。

僕が目指しているのは、デフ(聴覚障害・ろう難聴者)が自分らしく生きられる社会です。最初は社会に出てからの仕事に焦点を当てていましたが、デフの人々から教えてもらったのは、教育の段階にこそ、孤立や「やりようのなさ」を感じやすいという苦しみでした。
生まれた地域や環境によっては、「聞こえないのは自分ひとり」という状況があります。調べてみると、デフの子どもたちに向けた企業活動や福祉サービスがほとんどなく、「儲からない」領域であるがゆえに支援が届いていないのです。私たちがそこに生活を懸けて取り組むのは勇気が要りますが、オンライン学習との併用も活用しながら、支援のない地域をなくしていきたいと考えています。
本当に必要なことに取り組めば、持続性は自ずと生まれる――。そのことを信じて、これからも活動を続けていきたいと思います。
取材・文:ぎぎまき
編集:マイナビ学生の窓口編集部
取材協力:サイレントボイス https://silentvoice.org/