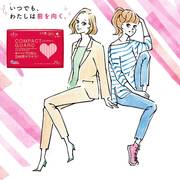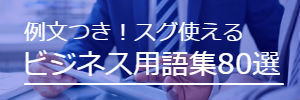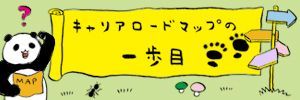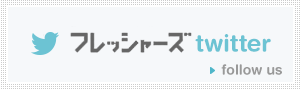- フレッシャーズトップ
- >ビジネスマナー
- >ビジネス用語
- >ナレッジとは? 意味や使い方、ノウハウとの違いを解説【例文つき】
ナレッジとは? 意味や使い方、ノウハウとの違いを解説【例文つき】
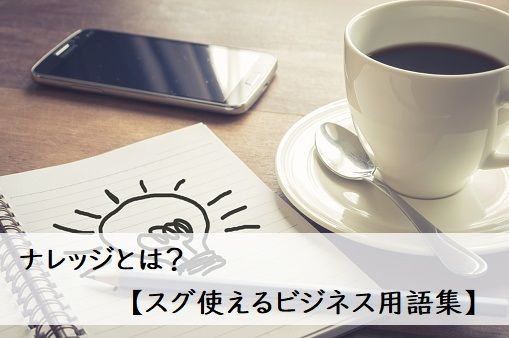
ナレッジとは英語の「knowledge」をカタカナ表記したもので「知識」という意味です。そしてビジネスシーンでのナレッジは、「有益な情報」という意味合いで用いられています。
ではナレッジとノウハウの違いは何でしょうか。
ビジネスシーンでよく使われる「ナレッジマネジメント」とはどんなものでしょう。
今回はちょっと難しいビジネス用語「ナレッジ」の意味や使い方を例文つきで解説。よく似た言葉「ノウハウ」「ハウツー」との違いについても見ていきます。
▼目次
1.ナレッジの意味
2.ナレッジのビジネスでの使い方
3.ナレッジの似た言葉と違い
4.ナレッジを使った例文
5.まとめ
▼こちらも合わせてチェック!
【理解力診断】 社会人の基礎的なスキルは足りてる?
ナレッジの意味

<意味>
・知識・情報・知見。
・企業などの組織にとって有益な知識やノウハウ。
ナレッジとは一般的には「知識」「情報」といった意味です。例えば本や新聞、資料のような形で文章化されていて、読むことで得られるような知識のことを指します。
ナレッジのビジネス用語としての意味
ビジネス用語としてのナレッジも基本的に同じですが、特に企業などの組織にとって「有益な情報」「付加価値のある経験や知識」を指すことが多いです。ビジネスシーンで「ナレッジ」を見たり聞いたりしたら、「有益な情報」と言い換えてみると分かりやすいでしょう。
例えばある企業において、1人の優秀な社員が自分の経験にもとづく有益なノウハウを持っているとしましょう。その社員さんが、せっかくのノウハウを自分の頭に持っているだけだとしたら、ちょっともったいないですよね。
そこで、その頭の中にあるノウハウを言語化し、見える化するとどうでしょう。他の人も「知識」として活用できるようになります。この「知識」こそがナレッジです。
「知識や情報=ナレッジ」を共有することは、企業にとって大きなメリットとなり、また個人にとってもスキルアップにつながることが期待されています。
「○○のプロ」と言われるような専門家や研究家がもつナレッジを1つの商品として、企業や組織に提供するビジネスも活発に行われています。
そもそも英語としてのナレッジはどんな意味?
そもそもナレッジとは英語の“knowledge”を由来とするカタカナ言葉です。英語の“knowledge”について辞書をひくと、
2.識別、理解、認識
3.(事実・事情を)わかっていること
といった意味があります。「知識として知っている」「よく理解している」といったニュアンスで用いられることが多いようです。
“a scholar of great knowledge”
(博学の学者)
といった具合に使われます。
ナレッジのビジネスでの使い方
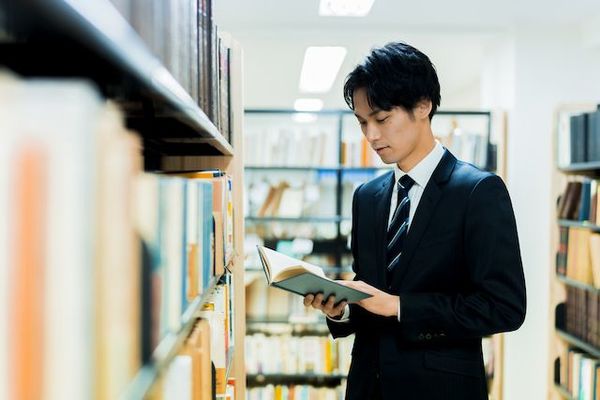
ビジネスシーンでのナレッジの使い方は、
・ナレッジを活用する
などが代表的です。
限られた人だけが持っていた知識を、関係者みんなで「共有」しようとするときや、ビジネスのために「活用」しようとするときにナレッジという言葉が登場するパターンが多いです。
さらに、ナレッジという言葉はそれ単独ではなく、他の言葉とくっついて使われることも多いです。ここでは、ビジネスシーンでの「ナレッジ+〇〇」のバリエーションを3つ紹介します。
ナレッジマネジメント
ナレッジマネジメントは、今までバラバラだった個々の知識やノウハウを企業として蓄積し、分かりやすく体系化して共有・活用していこうとする経営手法のことを指します。メリットとして、
・離れた拠点にもノウハウが伝わる
・若手の育成に役立つ
などが挙げられ、ナレッジマネジメントに注目する企業が増えています。
ナレッジベース
ナレッジベースは、先ほどのナレッジマネジメントの運用に際して必要となる、情報を一括管理できるデータベースのこと。
ナレッジベースに有益な情報を蓄積し、時代のニーズに合わせて更新を続けることで、企業にとっては大切な知的財産となっていくことでしょう。
ナレッジワーカー
ナレッジワーカーのワーカーとは「働く人」という意味。よってナレッジワーカーは「知的労働者」と訳されます。自身の体を動かして企業に貢献する労働者に対して、「知的労働者」は自身の「知識」を活用して企業に貢献する労働者です。
ナレッジワーカーは「マネジメントの父」と称された経営学者ピーター・ドラッカーが提唱した言葉とされています。
ナレッジの似た言葉と違い

ナレッジと意味が似ている類語としては「知識」が当てはまります。
それから次のようなカタカナ語も「似ているけどちょっと違う」言葉として挙げられます。「ハウツー」「ノウハウ」「スキル」それぞれの意味と、ナレッジとの違いを順番に見ていきます。
ハウツー
ハウツーは英語の”how to”からきており、「どのように〜するか」という意味を表します。つまり「やり方」や「手順」といった実務の基本レッスンのような意味合いです。ナレッジの方は手順的なものに限らずもっと幅広い知識のことを指します。
例えば身近なTVゲームで考えてみましょう。ゲームでいうハウツーとは、Aボタンで進む、Bボタンで戻る、攻撃するなどの基本的なやり方のことです。
ノウハウ
ノウハウは英語の“know-how”からくる言葉です。ハウツーのように「手順」のようなニュアンスもありますが、そのほかに「専門的なテクニック」や「技術的に優位となりうる情報や経験」「秘けつ」といった意味も持ちます。
専門的なテクニックというのは、簡単には自分のものにできないこともありますよね。
研究や経験を重ねてようやく得られるようなテクニックは、他の人が簡単に真似できない貴重なもの。つまりノウハウとは知識と経験に基づく独自の知恵のようなものです。
先ほどのTVゲームでいうと、基本操作ができたとしても攻略するのは難しいもの。「ここは武器を変えた方がいい」「このアイテムを10個持っていこう」「ここで必殺技を繰り出そう」など、工夫して編み出した攻略テクがノウハウです。
ナレッジとノウハウはとても似ている言葉で、そのまま言い換えができるケースも多々あります。ナレッジは「知識」のことなので、その中に誰かのノウハウが含まれることも。
例えば誰かのノウハウをうまく言語化してまとめることで、他の人に共有できることもあります。このとき誰かのノウハウはナレッジになっていくのです。
スキル
スキルとは「技能」のこと。先ほどのノウハウが「専門テクニック」なのでとても意味が似ているのですが、スキルは「能力」というニュアンスがより強くなります。つまり「テクニックを実践できる能力」という意味合いです。
TVゲームの例でいうと、「ここで必殺技だ」と思っていても実際に必殺技を繰り出せないと負けてしまいます。ジャストなタイミングで必殺技を出せる能力がスキル、というわけです。
それに対して、ナレッジは文章などで得られる「知識」のことなので、「実践」というニュアンスまでは含まれていません。
ナレッジを使った例文

ここからは、ナレッジを使った例文をご紹介していきます。
情報を共有するための環境づくりの場面で
「社内システムに、○○関連のナレッジをシェアするための「Q&A」を設けました」
ある分野における「有益な情報(ナレッジ)」を社内で共有するために、Q&Aとしてシステム化したという意味の例文です。
有益な情報を社内で共有したい場面で
「○○社との提携で得た情報やノウハウを、ナレッジとして共有するためにミーティングを行います」
「ノウハウ」と「ナレッジ」が両方使われている例文ですね。ノウハウを言語化して、ナレッジとして社内で共有しようとしています。
もう1点、こちらは実際にある医師・医学生専用Webプラットフォーム「MedPeer」での使用実例です。ナレッジが次のようなフレーズで使われていました。
MedPeerより引用
「全国の医師が経験やナレッジを『集合知』として共有し合う医師・医学生専用のドクタープラットフォームです」
まとめ

ナレッジとは「知識」「情報」という意味を持つ言葉。特にビジネスシーンでは「有益な情報」というニュアンスで用いられています。
企業にとっては有益な情報を皆で共有し、活用していくのはとても大切なこと。その重要性が再認識されるとともに、ナレッジという言葉も多く使われるようになってきているのです。
あなたも新社会人になったら「ナレッジの共有」を意識しながら仕事に取り組んでみてはいかがでしょうか。
(マイナビ学生の窓口編集部)

学生の窓口編集部
「3度のご飯よりも学生にとっていいことを考える!」の精神で 大学生に一歩踏み出すきっかけコンテンツをたくさん企画しています。 学生生活に役立つハウツーから、毎日をより楽しくするエンタメ情報まで 幅広く紹介していますので、学窓(がくまど)をチェックしてみてください!
関連キーワード:
関連記事
新着記事
-
2025/10/21
-
2025/09/29
-
2025/09/13
-
2025/08/11
-
2025/08/09
【お盆に読みたい】家族問題の第一人者が綴る。あなたを責めつづける心の中の「お母さん」を手放すと起こる「人生の変化」とは?
HOT TOPIC話題のコンテンツ
-
PR
【診断】セルフプロデュース力を鍛える! “ジブン観”診断
-
PR
いつでもわたしは前を向く。「女の子の日」を前向きに♪社会人エリ・大学生リカの物語
-
PR
あなたの“なりたい”社会人像は? お仕事バッグ選びから始める新生活
-
PR
社会人デビューもこれで完璧! 印象アップのセルフプロデュース術
-
PR
実はがんばりすぎ?新社会人『お疲れ度』診断
-
PR
視点を変えれば、世の中は変わる。「Rethink PROJECT」がつたえたいこと。
-
PR
ウワサの真実がここにある!? クレジットカードの都市伝説
-
PR
忙しい新社会人にぴったり! 「朝リフレア」をはじめよう。しっかりニオイケアして24時間快適。