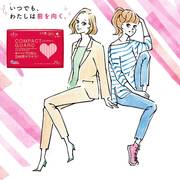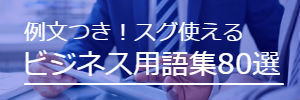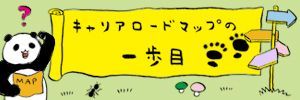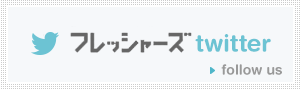- フレッシャーズトップ
- >社会人ライフ
- >社会人ライフ
- >教育の違いがそこにはあった! 日本人が欧州の人より「共同作業」が得意な理由
教育の違いがそこにはあった! 日本人が欧州の人より「共同作業」が得意な理由
日本人は空気を読むのが上手ですよね。場の空気を読むだけではなく、仕事や趣味などのコミュニティーにおいて欧州人よりも協調性がある気がします。欧州人の場合、コミュニティーにいながらもいわゆる「個人プレー」をしている人たちが目立ちますが、日本人は平均的に見てやはり「和」を大事にしている印象です。
▼こちらもチェック!
あなたの協調性診断! 仕事をする上で必要なチームワーク力を診断
これには色々な理由があるのかもしれませんが、もしかしたら「日本の学校」がひとつの理由かもしれません。
日本の小学校や中学校は「勉強以外」でも「同級生と一緒の共同作業」が多いです。みんなで一緒に教室の掃除をしたり、給食がある学校では給食当番があったり。中学校で部活動をしていれば、これもまた共同作業ですよね。
日本人は子どものときから学校でこのような「共同作業」が多いので、それが「協調性」につながっているのかもしれません。欧州人、または筆者も含む欧州育ちの人を見ていると、マイペースというか協調性がない(自己中ともいう)人がけっこうな数いたりします。そもそも「共同作業のやり方」がよくわからないのです。
欧州の学校、たとえば筆者の出身国ドイツの学校には「共同作業」の時間がほぼありません。たとえば掃除は業者の人がやるので、生徒たちがみんなで教室を掃除することはありません。そして学校はお昼の12時や1時に終わってしまうので、生徒はランチを家に帰って食べます。学校でお昼を食べようと思えば学生食堂はあるのですが、そこは大人の従業員がフライドポテトやホットドックなどを販売しているため日本でいう「給食」ではありませんし、当然生徒による給食当番もないわけです。
ドイツの学校には部活動もないため、たとえば生徒がサッカーをしたければ、学校ではなく、地元の(学校とは無関係の)市や国がやっているサッカークラブに入ってサッカーをします。逆にそういったクラブに入らなければ、学校を卒業するまでに一度もこれといった共同作業を経験しないまま卒業することになります。
ドイツを含む欧州の「学校」は「勉強を教えるところ」という要素が強く、「教育」の面、たとえば食事のような食育の面は、学校ではなく生徒の家庭に委ねられています。
関連記事
新着記事
-
2025/10/21
-
2025/09/29
-
2025/09/13
-
2025/08/11
-
2025/08/09
【お盆に読みたい】家族問題の第一人者が綴る。あなたを責めつづける心の中の「お母さん」を手放すと起こる「人生の変化」とは?
HOT TOPIC話題のコンテンツ
-
PR
忙しい新社会人にぴったり! 「朝リフレア」をはじめよう。しっかりニオイケアして24時間快適。
-
PR
【診断】セルフプロデュース力を鍛える! “ジブン観”診断
-
PR
視点を変えれば、世の中は変わる。「Rethink PROJECT」がつたえたいこと。
-
PR
社会人デビューもこれで完璧! 印象アップのセルフプロデュース術
-
PR
あなたの“なりたい”社会人像は? お仕事バッグ選びから始める新生活
-
PR
いつでもわたしは前を向く。「女の子の日」を前向きに♪社会人エリ・大学生リカの物語
-
PR
実はがんばりすぎ?新社会人『お疲れ度』診断
-
PR
ウワサの真実がここにある!? クレジットカードの都市伝説