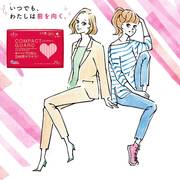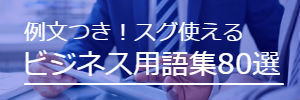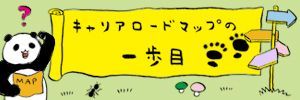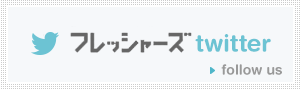- フレッシャーズトップ
- >ビジネスマナー
- >ビジネス用語
- >リテラシーとは? 意味や使い方をわかりやすく解説【例文つき】
リテラシーとは? 意味や使い方をわかりやすく解説【例文つき】

リテラシーという言葉は、ビジネスシーンのみならず日常会話でも耳にすることが増えてきました。「情報リテラシー」「ITリテラシー」といった言葉を聞いて「どんな意味?」と疑問に思われた方は多いのではないでしょうか。
今回はリテラシーの意味や種類、使い方を例文とともに解説。「◯◯リテラシー」といったリテラシーの種類も分かりやすく解説しますので、この機会にしっかりマスターしましょう。
▼目次
1.リテラシーの意味は
2.リテラシーの種類
3.リテラシーの使い方
4.リテラシーを使ったビジネス例文
5.まとめ
▼こちらも合わせてチェック!
【出世力診断】あなたは社長になれる?平社員のまま終わる?
リテラシーの意味は

リテラシーというカタカナ言葉は、「(ある分野に関する)知識や判断力、活用する能力」といった意味を持ちます。
リテラシーの意味で特にポイントとなるのは「活用する能力」の部分。正しい知識を身につけて活用する、あるいは使いこなす力、という意味合いが強いです。
簡潔に言うならば、たいていのリテラシーは「使いこなし力」と言い換えてみると分かりやすいかもしれません。
ちなみに、本来のリテラシー(literacy)の意味は「読み書きする能力」のことです。「読んで(知識を得て)」「書く(アウトプットする)」から転じて、現在のような「知識を活用する力」という使い方になったのかもしれません。
リテラシーの意味が分かりやすい代表例が「情報リテラシー」。
IT革命により、私たちは一昔前とは比べ物にならない位、たくさんの情報に囲まれて生きています。溢れている情報の中から、いかに「正しく取捨選択し」「上手に使いこなすか」といった能力の重要性が高まってきています。この能力こそが、まさに「リテラシー」です。
リテラシーの種類

リテラシーは単独で使われるよりも、先ほどの「情報リテラシー」のように関連する言葉を繋げて「○○リテラシー」と表現されることが多い言葉です。
以下にビジネスシーンでよく使われるリテラシーの種類を挙げますが、どれも基本的には「正しい知識を持ち」「活用する、使いこなす力」という意味合いを持っています。
情報リテラシー
情報リテラシーについては繰り返しになりますが、この情報社会の中で適切に情報収集を行い、正しい情報を取捨選択して使いこなす力を指します。
現代社会の情報の多くはマスメディアやwebメディア、SNSなどを通して伝えられるため、次に解説するメディアリテラシーとかなり意味が近くなります。
加えて、ビジネスシーンにおける一例として顧客情報を適切に収集し、安全に管理してマーケティングに活用する力なども情報リテラシーに当てはまります。
メディアリテラシー
テレビや新聞、インターネットやSNSといったあらゆるメディアから流れてくる情報を正しく取捨選択し、上手に活用する能力のことです。
メディアが扱うのは「情報」なので、先ほどの情報リテラシーと似ていますね。
メディアリテラシーが低ければ、フェイクニュースなど裏付けのない誤った情報を鵜呑みにしたり、不用意に広めてしまう危険性もあるため、特にメディア関連に携わる人に必要な能力です。
また、メディアの中には情報を受け取るだけでなく、SNSのように自分から発信できるものも。
SNSでは不適切な投稿を公開することで、他人を傷つけてしまったり、人間関係にヒビが入ってしまったりすることがあるため、メディアリテラシーが大切になってきます。
コンピューターリテラシー
PCやスマートフォンといったハードウェアから、ExcelやWordといったビジネスソフト、アプリなどを使いこなす能力を指します。
コンピューターは業務の効率に直結するため、現代のビジネスパーソンに欠かせない能力と言えるでしょう。
単にPCやソフトの技術的な操作方法だけでなく、例えば「自分にとって必要なソフトは?」など状況に応じた適切な情報収集力なども、コンピューターリテラシーに含まれます。
ITリテラシー
ITとは「情報技術」のこと。上記の情報リテラシーや、コンピューターリテラシーも内包した、IT関連の知識や使いこなし力のことを指します。今やIT業界はもちろん、全てのビジネスパーソンに必須ともいわれています。
さらに、IT関連の専門職なら、より高いITリテラシーが求められます。
例えばwebマーケターであれば、分析ツールや解析ツールの活用力。エンジニアであれば現場に応じたプログラミング言語やセキュリティツールの活用力などが当てはまるでしょう。
金融リテラシー
預金・債券・株式・外貨・ローンなど、金融商品についての知識を身につけ、適切に判断していく能力のことです。保険なども含まれるでしょう。
家のお金なら家計、ビジネスシーンなら会社の財務と金融商品をかけ合わせ、有効に管理・運用していく力を指しています。
例えば、家計のお金は全部タンス貯金しておくよりも、金融商品を活用することでもっと増やせる可能性がありますよね。しかし金融リテラシーが不足していると大損したり、投資詐欺に引っかかったりする危険性も。
マネーに関する正しい知識を持ち、リスクを回避しながらメリットを最大化する判断力こそが「金融リテラシー」ということです。
〇〇リテラシーはどの分野でも使える
現在のところ、リテラシーはITと関連する分野で使われることが多くなっていますが、他の分野で用いることももちろん可能です。
例えば製造業で「安全リテラシーが高い」というと、どんな意味になるでしょうか。この場合、安全対策(手順書の確認・安全装備など)の知識を正しく身につけ、それを業務の中できちんと実践できている、という意味だと捉えることができます。
リテラシーの使い方
リテラシーの基本的な使い方として、次のようなフレーズが挙げられます。
・リテラシーが低い
・リテラシーがない
・リテラシーを身につける など
例えば「私はITリテラシーが低すぎて……」という場合、単に「パソコンソフトの操作が苦手」というだけでなく、
「Wi-Fiってどうやって設定するの?」
「パソコンのスペックって?選び方が分からない」
など、ITツール全般に対する苦手意識を表す際に使うことができます。
また、ビジネスシーンでは前述のような「◯◯リテラシー」として使われるほか、応用力の高さを指し示す言葉として単独で使用されることもあります。具体例を次で見てみましょう。
リテラシーを使ったビジネス例文

リテラシーがどのような場面でどのように使われるのか、例文でご紹介します。単独での使用例(例文1)と、◯◯リテラシーの例(例文2)です。
例文1:単独での使用例
仕事での下調べが上手くいかずに、上司からアドバイスを受けている例文です。ここでは「いろいろ使いこなす、応用力」といったニュアンスで使われています。
例文2:〇〇リテラシーの例
金融機関に勤務した新入社員が、先輩から金融リテラシーの大切さについて教えられています。
自宅で業務をこなすリモートワークの導入を想定した例文です。会社全体のITリテラシーが低いとセキュリティが整わなかったり、自宅でのトラブルに対応できなかったりといった可能性が考えられます。
まとめ

リテラシーとは「(ある分野に関する)知識や判断力、活用する能力」を意味します。難しいと感じるときは、まず「使いこなし力」と端的に言い換えてみることをおすすめします。
また、国際化社会において、異文化を理解して対話していく力を「グローバルリテラシー」というように、新しいリテラシー用語も次々と生み出され、使用されるようになっています。これから個々のいろいろなリテラシーを培って、ビジネスシーンで活躍していきましょう。
(マイナビ学生の窓口編集部)

学生の窓口編集部
「3度のご飯よりも学生にとっていいことを考える!」の精神で 大学生に一歩踏み出すきっかけコンテンツをたくさん企画しています。 学生生活に役立つハウツーから、毎日をより楽しくするエンタメ情報まで 幅広く紹介していますので、学窓(がくまど)をチェックしてみてください!
関連キーワード:
関連記事
新着記事
-
2025/10/21
-
2025/09/29
-
2025/09/13
-
2025/08/11
-
2025/08/09
【お盆に読みたい】家族問題の第一人者が綴る。あなたを責めつづける心の中の「お母さん」を手放すと起こる「人生の変化」とは?
HOT TOPIC話題のコンテンツ
-
PR
いつでもわたしは前を向く。「女の子の日」を前向きに♪社会人エリ・大学生リカの物語
-
PR
忙しい新社会人にぴったり! 「朝リフレア」をはじめよう。しっかりニオイケアして24時間快適。
-
PR
【診断】セルフプロデュース力を鍛える! “ジブン観”診断
-
PR
社会人デビューもこれで完璧! 印象アップのセルフプロデュース術
-
PR
視点を変えれば、世の中は変わる。「Rethink PROJECT」がつたえたいこと。
-
PR
ウワサの真実がここにある!? クレジットカードの都市伝説
-
PR
あなたの“なりたい”社会人像は? お仕事バッグ選びから始める新生活
-
PR
実はがんばりすぎ?新社会人『お疲れ度』診断