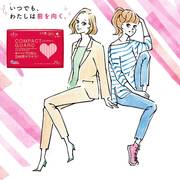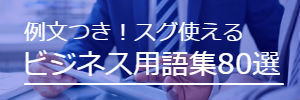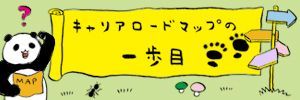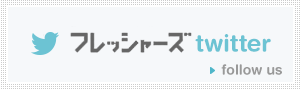- フレッシャーズトップ
- >ビジネスマナー
- >電話・メール
- >【拝啓・敬具は必要か不要か】ビジネスメールでの使い方と例文
【拝啓・敬具は必要か不要か】ビジネスメールでの使い方と例文
※記事全文を読むには会員登録(無料)が必要となります。
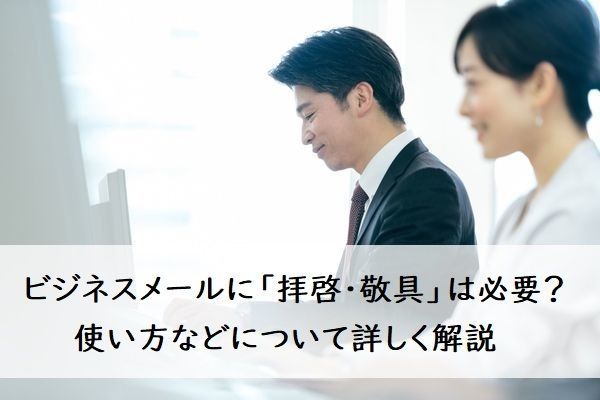
ビジネスメールに「拝啓・敬具」は必要なのでしょうか?
書面などで見かけたことがあったとしても、仕事中に取引先やお客様とのメールでやりとりで使っている人は、ほとんど見かけることがないという方もいるでしょう。
特に現代でのビジネスメールでは「拝啓」「敬具」を使うケースは稀だと言えますが、書面では見かけるため必要か不要か迷ってしまいますよね。
そこで今回は、拝啓の本来の意味や手紙での使い方からなぜメールでは不要なのかについて解説します。
ビジネスメールに必要?「拝啓・敬具」の意味とは
一般的なビジネスメールに「拝啓・敬具」が必要なのかを知る前に、書状や手紙で使われる「拝啓」と「敬具」の意味と「時候の挨拶」について知ることが大切です。
拝啓の意味
拝啓の意味は「あなたのことを尊敬しつつ、これから謹んで申し上げます」です。
「拝啓」の「拝」は「あなたのことを尊敬しつつ」という意味を持っています。
「啓」は「謹んで申し上げます」と言う意味があります。
古くは「拝啓仕候」(はいけいつかまつりそうろう)という4文字の複合形で用いられていました。
「拝啓仕候」から「拝啓」へ簡略化されたのは、明治時代の中頃だといわれています。
「拝啓」の後には一般的に時候の挨拶が来る
手紙や書状では「拝啓」のあと、二十四節にちなんだ季節の言葉を用いた本文の書き出しである「時候の挨拶」が続きます。
いきなり本題を切り出してしまうと、せっかちな印象を相手に与えてしまうので、時候の挨拶をクッションがわりにはさんでから本題へ移行するという仕組みです。
また「敬具」の前の末文としても使われます。
敬具の意味
「敬具」は、「これにて謹んで文章をしめくくります」という意味で使います。
「敬」は「謹んで」、「具」は「整える」という意味です。
実際に「敬具」が使われはじめたのは大正時代に入ってからだといわれており、それ以前までは「敬具」は使用されていなかったのだとか。
「敬具」は「拝啓」よりも後出なのが意外ですよね!
通常のビジネスメールに「拝啓・敬具」は原則不要!
以上を踏まえて「拝啓」と「敬具」の意味を把握したところで本題に戻りましょう。
結論から言うと、ビジネスメールで要件を先方に伝える際「拝啓」と「敬具」は原則不要です。
使うシーンが限られているだけでなく、「お世話になっております」から始めて、要件や結論を先に示すことが最優先だからです。
詳しく見てみましょう。
ビジネスメールは要件優先
ビジネスメールの場合は、要件を相手にわかりやすく伝えることが重要課題とされています。
そのため、一般的な「拝啓・敬具」の結びや時候の挨拶は省略して「お世話になっております」「お疲れ様です」程度の簡略化した挨拶にし、すぐ本題へ移行します。
ビジネスメールは「お世話になっております」「何卒よろしくお願いいたします」などを使おう
親しい相手の場合は「今日はよい天気ですね」くらいは入れてもいいかもしれませんが、前述の通り、ビジネスメールでは「拝啓」と時候の挨拶のかわりに「お世話になっております」「お疲れ様です」といった文言を入れます。
「敬具」の代わりとして「何卒よろしくお願いいたします」もしくは「よろしくお願い申し上げます」などの定型文が入ります。
前略もメールでは使わないほうが無難
手紙で挨拶を省略する際に使う「前略」もメールでは原則使用しません。
急ぐのだったら「お世話になっております」という挨拶だけで十分と判断されます。
そのため、ビジネスメールでは最低限の敬意を払いながら、スピードと効率化を重視することが重要です。
【例文でわかる】ビジネスメールの「拝啓・敬具」はマナー違反と思われる可能性がある
忙しいビジネスパーソンに向かって「拝啓」や長々とした時候の挨拶を挟むとかえって失礼にあたる可能性があるため、注意が必要です。
ビジネス上の要件を伝えるメールに、一般的な「拝啓」「時候の挨拶」を付け加えた例文を以下にご紹介します。
この記事は会員限定です。ログインをすると続きをお読みいただけます。
関連記事
新着記事
-
2025/10/21
-
2025/09/29
-
2025/09/13
-
2025/08/11
-
2025/08/09
【お盆に読みたい】家族問題の第一人者が綴る。あなたを責めつづける心の中の「お母さん」を手放すと起こる「人生の変化」とは?
HOT TOPIC話題のコンテンツ
-
PR
社会人デビューもこれで完璧! 印象アップのセルフプロデュース術
-
PR
視点を変えれば、世の中は変わる。「Rethink PROJECT」がつたえたいこと。
-
PR
いつでもわたしは前を向く。「女の子の日」を前向きに♪社会人エリ・大学生リカの物語
-
PR
ウワサの真実がここにある!? クレジットカードの都市伝説
-
PR
あなたの“なりたい”社会人像は? お仕事バッグ選びから始める新生活
-
PR
忙しい新社会人にぴったり! 「朝リフレア」をはじめよう。しっかりニオイケアして24時間快適。
-
PR
【診断】セルフプロデュース力を鍛える! “ジブン観”診断
-
PR
実はがんばりすぎ?新社会人『お疲れ度』診断