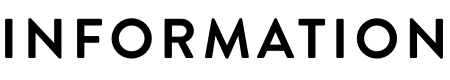ITジャーナリスト・成蹊大学客員教授
高橋 暁子
SNSや情報リテラシー教育が専門。スマホやインターネット関連の事件やトラブル、ICT教育事情に詳しい。
https://time-coaching.net/profile/
SNS上で発信・交流するときに気をつけたいこと

投稿やコメント、DMのやりとり、LINEのオープンチャットなど、さまざまな人との関わりが持てるのがSNSの魅力。友達以外にも多くの人が目にするからこそ、正しいマナーが必要です。
他人が見て不快に感じそうな内容は投稿しない
SNSは基本的に、不特定多数の人が見るものです。いろんな価値観や考え方を持った人がいますので、誹謗中傷はもちろん、差別的な発言や、人によって意見が分かれるような発言は避けるようにしましょう。
カンニングを思わせるような内容など、世間で禁じられていることを発信するのもNG。他人にその部分だけ切り取られ、炎上させられる可能性もあります。
気分が興奮状態のときは投稿をしない
人は興奮状態だと視野が狭まり、判断力が乏しくなります。特に何かにムカついてカーッとなっていたり、恋愛で舞い上がっているときなどは、つい悪口や恥ずかしいことを投稿してしまいがち。そんなときは少し時間をおき、冷静になってから、後で後悔する内容でないか考えてみましょう。
写真や動画を投稿するときに気をつけたいこと

特に若い世代に人気のInstagramやTikTok。写真や動画をアップしたことがある人も多いのではないでしょうか? 気軽に投稿してしまうと、トラブルや事件に巻き込まれる可能性もあるので要注意です。
一度顔出しをしたら一生消えないと心得ておく
顔出しをすると最初のうちは「いいね」をたくさんもらえて気分がよくなりますが、一度顔を出してしまうとスクショや保存をされ、たとえ自分で削除してもネット上では消せません。なかには、収益目的でYouTubeなどに転載されてしまう人もいます。
例えば歌で活躍したい、ダンスのプロになりたいなど、明確な目的がある人はいいですが、「ちょっとちやほやされたい」「みんなやってるから」という軽い気持ちあれば、よく考えてみることが大切です。
個人情報が特定できるものの写り込みに注意する
制服や校章、掲示物など、校内には高校を特定できる要素が多いため、特に学校での撮影は背景の写り込みに注意しましょう。家の間取りや外観、窓から風景など、ちょっとした情報でも自宅が特定されてしまい、待ち伏せやストーカー被害に遭う人もいます。
また、自宅や学校付近の公園、行きつけのお店など、ローカルスポットでの撮影は、簡単に居住地区が特定できてしまうので注意してください。
一緒に写っている人の許可を得る
高校生でも、自分の写真を公開してほしくない人は一定数は必ずいます。どんなに仲のいい友達でも、公開する前に必ず「アップしていい?」と確認するようにしましょう。NGであれば公開しないか、スタンプなどで顔を隠して公開する場合でも本人に確認してください。
勝手にアップすると、人間関係にヒビが入ったり、相手に何かあったときに責任を問われることもあります。
通りがかりの人や、クラスメイトなどの映り込みにも配慮しましょう。自分以外の人の公開は基本的にNGと考えておくといいですね。
「高校生」というだけでネットの標的になりやすい

「高校生」はネットの大好物! それだけでブランドになり、注目されて面白がられ、ネタにすることでPV数が稼げます。「女子高生」は自撮り写真や動画を拡散されやすく、ポルノサイトなどに転用されることも。
男子の場合は女子に比べて「いいね」や再生数が伸びないため、投稿が過激化する傾向があります。ちょっとでも行動に問題があると、それを晒され、炎上動画として世の中に広まり、停学や退学、内定取消し処分となるケースもあります。
「鍵アカ」や24時間で消える「ストーリーズ」だからといって軽々しく投稿してしまうのも危険です。収録機能やスクショで保存され、悪意を持った人に拡散されると、本名や住所、学校が特定され、デジタルタトゥーとして一生残り続けます。たったひとつの投稿が、今後の人生に大きな影響を及ぼすことを自覚しておきましょう。
「ただ見ているだけ」でも注意が必要!

SNSを利用している人なかには、投稿はせず、閲覧用にアカウントを持っている人もいるはずです。ただ眺めているだけなら安心と思ったら大間違い! デメリットもしっかり理解しておきましょう。
メンタルヘルスに悪影響を及ぼす
さまざまな調査機関の研究により、特にInstagramやTikTokは10代のメンタルヘルス(こころの健康状態)に悪影響があると報告されています。
今では自撮り写真をアップするときは、加工するのが当たり前。そういった、ものすごくキレイに整った人ばかりを見ていると、加工したものが真実に見えてきて、「美しくなければいけない」「ヤセてなくてはいけない」という強いメッセージを受け取ってしまいます。そうなると自信がなくなり、鬱や摂食障害になったり、自分は生きている価値がないと思うようになるのです。
誤情報やデマほどのめり込みやすい
いざダイエットをしようとSNSで調べると、間違った情報もたくさん流れてきます。なかには、健康被害につながるようなとんでもないデマなのに、何十万回も再生されている動画も多いです。
また、SNSはAIがそのユーザーが好みそうな情報を優先的に出してくるので、どんどん偏った情報や間違った情報にのめり込むという悪循環が。
自分の好み以外の情報もフラットに取り入れられるよう、SNSだけでなく、日頃からニュースサイトやTVなどをチェックすることが大切です。
自分で制限する!という強い意志を持つ
短時間で楽しめ、自分好みの投稿が次々に流れてくるTikTokなどの「ショート動画」は、特に10代にとって中毒性が高いことが指摘されています。
仮に1日に2時間ショート動画を見ているとしたら、1日の12分の1、つまり1年間のうちの1ヶ月間を丸々費やしている計算になるんです。せっかくの貴重な高校生活、それではもったいないと思いませんか?
SNSの「利用時間制限機能」を設定したり、スマホの「スクリーンタイム」や「Digital Wellbeing」機能で利用時間を確認し、アラームをかけるなどして、上手にコントロールできるようにしましょう。
しかし、実践できる人は少なく、SNSで高校生活を無駄にしてしまったと後悔している先輩たちをたくさん見てきました。SNSに依存せず、今しかできないことを楽しめるといいですね。
闇バイトに巻き込まれないようにするには?

最近世間で話題の「闇バイト」。特殊詐欺で逮捕される未成年の数は年々増え、その3割が中高生と言われています。正しい知識や情報を知って、自分自身が加害者にならないよう心がけましょう。
アルバイトは必ず求人サイトで探す
中高生が闇バイトに手を出す根本的な原因は、「何でもSNSで検索する」ことにあります。SNSには危ない情報も多く存在するため、アルバイトを探す際は求人サイトなどを活用したほうが安心です。
求人サイトでも、その企業が信頼できるのか、仕事内容は明確か、時給や勤務時間が明記されているかをよく確認しましょう。例えば「物を運ぶ」や「電話をかける」などといった曖昧な仕事内容であれば、避けたほうがいいでしょう。
うまい話やおいしい話はない
SNSで「高額バイト」「即日即金高収入」などで検索すると、それらはすべて闇バイトで使われているハッシュタグで、どんどん似たような情報が流れてくるため、犯罪に巻き込まれるリスクが高まります。
今の日本の平均時給から考えると、1日フルで働いても報酬はせいぜい1万円ほど。それを遥かに上回る5万、10万の仕事は、犯罪を疑うようにしてください。判断が難しい場合は、保護者に相談するのがおすすめです。
世間のニュースや出来事を知っておく
逮捕された中高生の中には、最後までまったく犯罪だと気づかなかったという人も少数ながらいます。それでも犯罪は犯罪。社会経験や知識が乏しいと、怪しいかもと疑いを持つこともできません。
1つでも毎日見るニュースサイトを決め、自分の興味がない情報にも目を通すようにしましょう。今どんな犯罪や被害が増えているのか、何を気をつけなくてはいけないかを学んでおけば、加害者にも被害者にもなるリスクを避けることができます。
SNSは高校生活を盛り上げてくれる一方で、炎上、デジタルタトゥー、犯罪被害、さらには自身が犯罪者になるなど、多くの危険性も潜んでいます。投稿する際は後々後悔をしない内容を心がけ、のめり込みすぎてSNSの世界がすべてにならないようにしていきましょう。上手に活用できれば、きっと今度の人生の役に立つはずです!