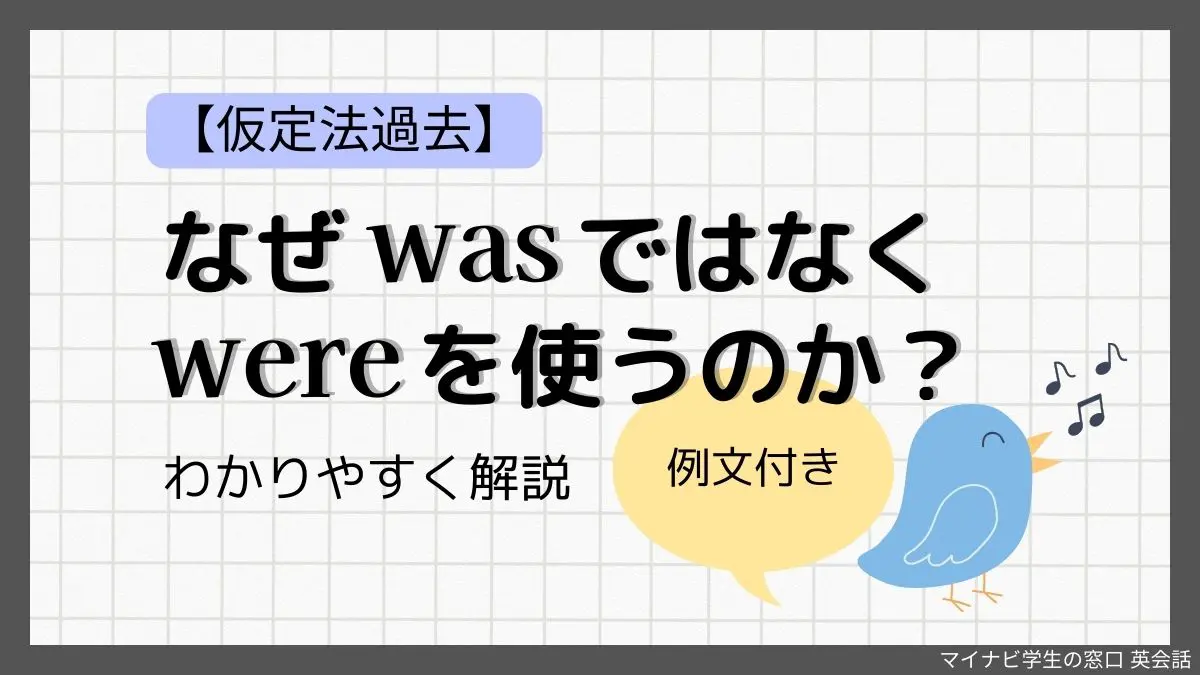英語の仮定法とは、現実とは違う状況を仮想して「〜だったらいいのにな」と言う表現です。非現実的な感覚を示すため、現在形ではなく過去形を使い、「仮定法過去」として表します。
ルールが複雑なため、苦手意識を持つ方も多いのではないでしょうか?
ここで、仮定法を学ぶと一度は目にするであろう、有名な例文をご紹介しましょう。
I wish I were a bird.(もし私が鳥だったらなあ。)
例文を読んでみて、違和感を抱いた人も多いかもしれませんね。
なぜなら仮定法を習ったとき、“I” “He” “She”などの単数形の主語に続くbe動詞の過去形は、“was” と勉強したはずだからです。
“I” は単数形だから過去形のbe動詞は“was” になる。じゃあ、どうして “I was” じゃなくて “I were” なの?
本記事では、仮定法過去について、なぜ“was” ではなく“were” を使うのか、英語初心者にもわかりやすく解説していきます!
結論:仮定法では“were” を使うことで「現実との乖離」を表している
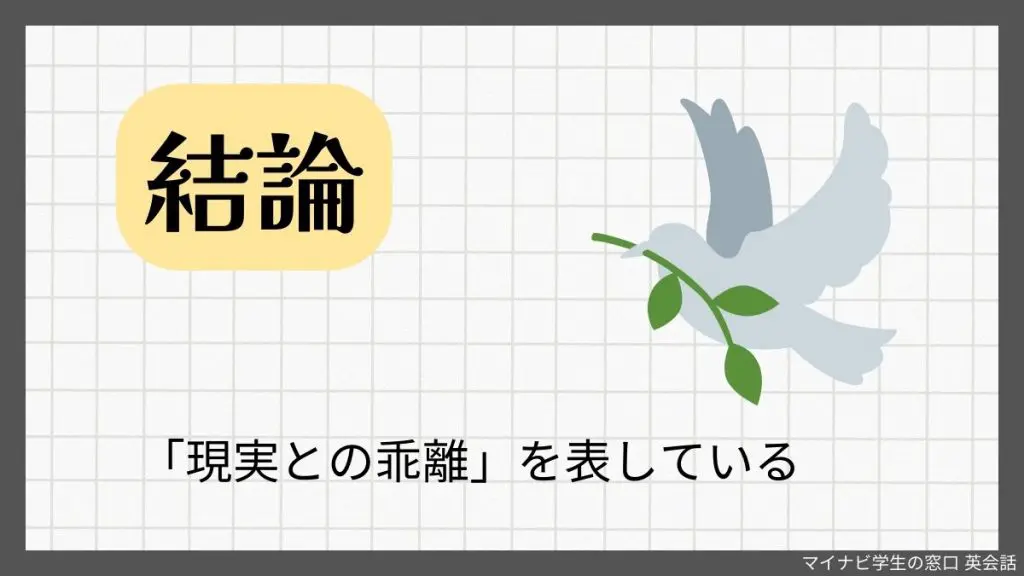
仮定法過去で “was” ではなく “were” を使う理由は、「現実との乖離」のニュアンスを強く表現しているからです。
冒頭の例文 “I wish I were a bird.” では、「もし私が鳥だったら」という、現実では絶対にあり得ないことを仮想していますね。
通常、“I” のあとに続く be動詞の過去形は “was” です。「“was” が来るのでは?」と考えていた人の認識は誤っていませんので、安心してください!
しかし英語の世界では、あえて “were” という「通常ではない形」を取ることで、「現実から離れている状態(=ありえない感じ)」を出すんです。
もし“I was a bird” になると、自分が鳥になって飛べる可能性がある前提で、仮定しているニュアンスが出てしまいます。
人間が、

今から鳥になろうと思えばなれるから、やってみようかな。
と考えている状態は、不自然ですよね。
そのため「現実とは異なる形」を表現するために、“I were a bird” という形になるんです。
この形式は文学や芸術作品でも多く使われています。
例えば名作ミュージカル『屋根の上のバイオリン弾き』には、“If I were a rich man” というフレーズが登場します。
使われているのは、主人公が「もし俺が金持ちだったら」と、非現実的な仮定をしながら歌うシーンです。
貧しい主人公にとって、金持ちになることは絶対に不可能という状況が伝わってくる例ですね。
このように非現実的な空想をする場合に、“I were” を使うことで、「不可能だ」というニュアンスを強調できるんです。
背景:英語の古い歴史の影響が関係している!「be動詞の過去形」は、すべて “were” を使っていた
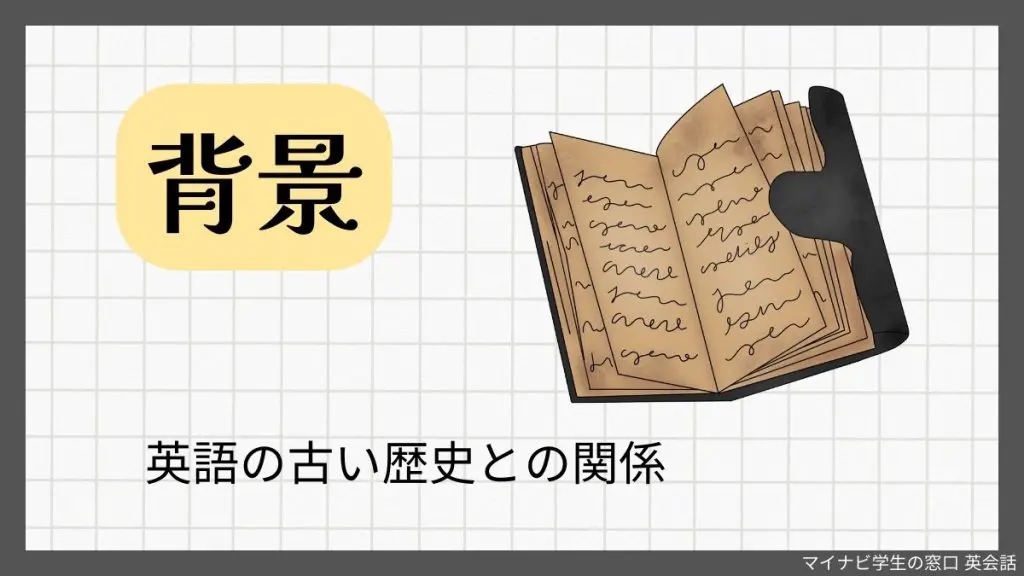
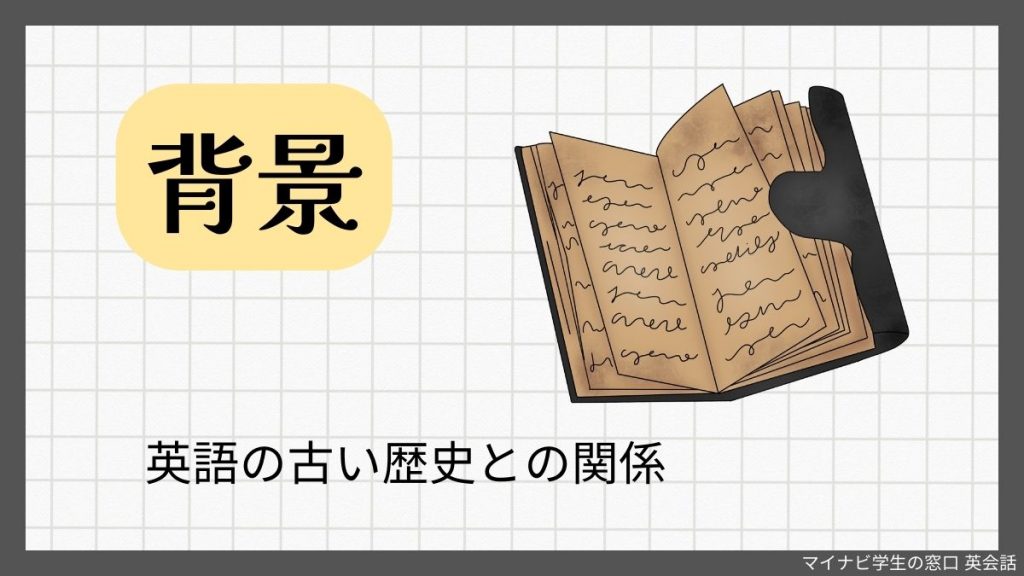
英語の歴史をさかのぼると、古くは「be動詞の過去形」は、すべて “were” を使っていたそうです。
例えば “I were” や “She were” といった具合に、そもそも “was” というbe動詞自体が存在しなかったんですね。
とくに、“She were” “He were” のように三人称単数に“were” が付く形式は学校で習わないため、現代人の感覚ではかなり違和感があるのではないでしょうか。
実際は、最初にbe動詞の過去形“were” があり、別の形として “was” が生まれました。その後、徐々に一人称でのbe動詞は “I was” や “She was” と、現在の形へ移り変わっていきます。
しかし1つだけ、 “I were” を使うケースが残りました。
「仮定法過去」です。
仮定法は「もし〜だったらなあ」という、現実ではあり得ないことを仮想する特殊な文法です。
“I were” という、今ではもう使われない表現をあえて使うことで、「現実じゃない感じ」「あり得ない感じ」を強調しているんですね。
高校までの一般的な英語教育では、なかなか教えてもらえない背景事情ですが、マメ知識として頭の隅に置いておくと、理解の助けになるはずです。
京都女子大学の論文でも触れられている通り、仮定法は日本人の英語学習者にとっては、難しい文法項目とされてきました。
しかし歴史的な背景をざっと理解し、「仮定法」=「現実じゃない感じ」のイメージさえ頭に浮かべられれば大丈夫です。複雑に考えなくても、「“I were” は非現実的なんだな」と、使い方をスッキリ理解できますよ。
仮定法“I were”について例文で考えてみよう〜 口語ではwasを使うケースも! ~
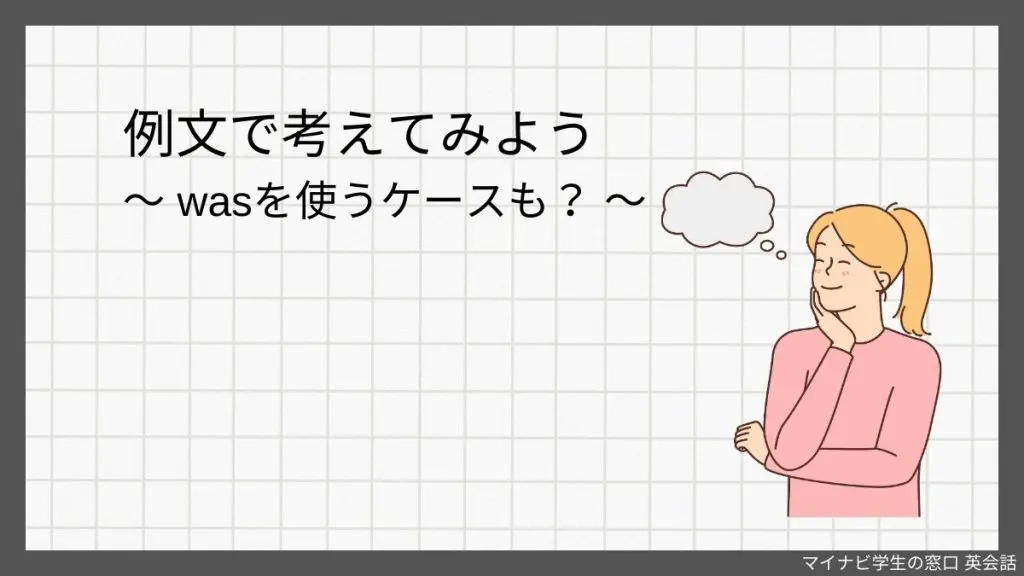
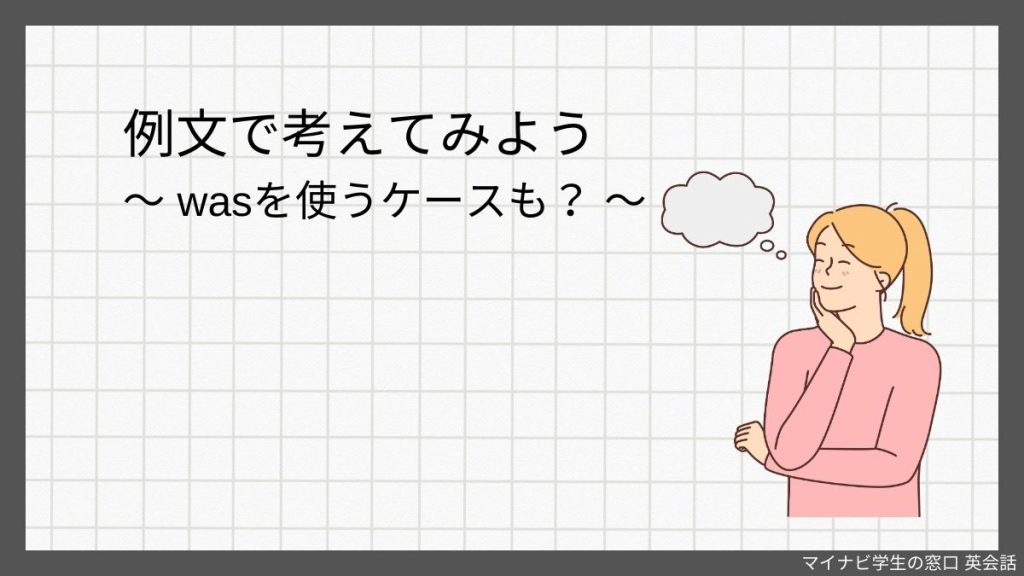
実際に仮定法過去の例文をいくつかチェックしながら、“I were” の使い方をマスターしていきましょう。
If I were a cat, I would sleep all day.
(もし私が猫だったら、一日中寝てるだろうな。)
If I were an American, I would throw a party every weekend.
(もし私がアメリカ人だったら、毎週末パーティーを開くよ。)
If I were the Prime Minister, I would work hard to improve the country’s education system.(もし私が総理大臣だったら、国の教育制度を改善するために尽力するだろう。)
上記の例文は、いずれも話し手が、ごく普通の日本人である前提です。その自分が、猫 / アメリカ人 / 総理大臣になることは、現実ではありえない状況ですよね。
このように、現実ではないことを仮想するときに “I were” と仮定法を使うことで「現実との乖離」「あり得ない感じ」を出しているんです。
少しだけなら実現の可能性がある場合“If I was ~” という表現でもOK
以上で見てきた例文は、いずれも極端なシチュエーションを想像している典型的な仮定法過去の文章です。しかし、より微妙なニュアンスの場合、少し表現が異なってきます。
If I was slimmer, I could pull off various outfits.
(もし私がもっと痩せていたら、いろんな洋服が着こなせるのにな。)
「あれ? 話が違うよ!」
「今度は “I was” になっているけど、どっちが正しいの?」
……と混乱してしまいますよね。
実は、仮定法でも “I was” を使うケースは一部存在するんです。
非公式で口語的な言い回しですが、ネイティブの日常会話では主に、
「場合によっては、将来起きても不思議ではないこと」
を表現するとき、“I was” が使われることもあります。
“If I was slimmer” は、「もし私がもっと痩せていたら」という仮定が「現実に起こる可能性がある」という微妙なニュアンスを含んでいます。
体質的にどうしても痩せられない人の場合、「痩せること」は非現実的ですが、技術の進歩で痩せる方法が見つかる日が来るかもしれません。
このような「現実的ではないけれども、少しなら実現可能性がある」と感じられる場合に “I was” を使うことがあるんです。
I wish I were a bird.
(もし私が鳥だったらなあ。)
⇒ 実現可能性0%
「現実との距離」がもっとも遠い = “I were”
If I was slimmer, I could pull off various outfits.
(もし私がもっと痩せていたら、いろんな洋服が着こなせるのにな。)
⇒ 実現可能性20%
「現実との距離」がちょっと縮まる = “I was”
“I was” は正式な形ではありませんが、口語表現としては使用されることがあるので、便利な英会話フレーズとして押さえておきましょう。
仮定法 “I were” について理解を深められる質問と回答
仮定法 “I were” は難しい文法事項で、混乱してしまう人は多いですよね。より理解を深めるために、役立つ情報がまとまったQ&Aを紹介するので、ぜひ参考にして、マスターしてみてください。
仮定法過去と仮定法現在の違いは何ですか?
仮定法現在は、現実になっていない事柄について「そうなって欲しい」と願い、要求や提案をするときに使われます。仮定法過去との違いとしては、過去の出来事や三人称の主語だとしても、that以下は必ず動詞の原形になることです。
仮定法過去の例文:“If I were rich, I would※ buy a house.” (私がお金持ちなら、家を買うのに。)
※“were” に時制を合わせて“would” を使う
仮定法現在の例文:“I suggested that he go※ to the gym.”(私は彼にジムに行くよう勧めた。)
※“went” ではなく常に現在形“go” を使う
仮定法過去と仮定法過去完了の違いは何ですか?
現時点での仮定を表す仮定法過去と異なり、昔の話をしているのが仮定法過去完了の特徴です。
仮定法過去完了は、過去のある時点で「~だったら、~だったかもしれない」と、過去の時点での仮定を表します。基本の形は「If+主語+had+過去分詞, 主語+助動詞の過去形+have+過去分詞」。
現在の出来事について仮定するなら仮定法過去
例文:“If I were rich, I would buy a house.” (私がお金持ちなら、家を買うのに。)
基本の形:If+主語+動詞の過去形, 主語+助動詞の過去形+動詞の原形
過去の出来事について仮定するなら仮定法過去完了
例文:“If I had been rich, I would have bought a house.”(私がお金持ちだったら、家を買っていたのに。)
基本の形:If+主語+had+過去分詞, 主語+助動詞の過去形+have+過去分詞
仮定法過去ではHeやSheなどの三人称単数でも“were” を使いますか?
“If he were rich~” “If she were here~” のように三人称単数で使われることもあります。しかしあまり見慣れない形ですよね。最近は日常会話では“was” を使うケースも増えてきているので、どちらを使ってもいいかもしれません。ただ、本来は三人称単数でも“were” を使うため、正しい表現としてこちらを覚えておくのがおすすめです。
仮定法“I were” に関する理解度チェックテストに挑戦!
最後に、理解度をチェックテストで確認しましょう!
① 以下から、仮定法過去の使い方が正しいものを1つ選んでください。
A) If I were a bird, I will fly anywhere I want.
B) If I were a bird, I would fly anywhere I want.
C) If I was a bird, I would fly anywhere I want.
D) If I was a bird, I will fly anywhere I want.
② 次の文を完成させるのに最も適した語句を選んでください。
If I _ rich, I would travel the world.
A) am
B) was
C) were
D) be
③ 以下から1つだけ、仮定法過去が使われていないものを選んでください。
A) If I were you, I would apologize.
B) If I were taller, I could reach the top shelf.
C) If I was at the party last night, I didn’t see her.
D) If he were here, he would help us.
④ 次の文章を英訳してください。
もし私があなただったら、その仕事を辞めるだろう。
解答
① B) If I were a bird, I would fly anywhere I want.
② C) were
③ C) If I was at the party last night, I didn’t see her.
④ If I were you, I would quit the job.
~④について~
よくある誤用例は“If I were you, I will quit the job.” 。
仮定法過去では、未来を表す助動詞“will” も、時制を一致させて過去形“would” にしましょう。
違いまとめ:仮定法で “I were” を使うのは「現実との乖離感」を表すため
あらためて、今回のテーマ「仮定法の “I were”」について、記事の内容をまとめました。
- 仮定法で “I were” を使うのは「現実との乖離感」を表すため
- “I were” の形は英語の歴史が関係している
- 非公式な口語表現では “I was” も使うことがある
“was” も“were” も最初は「be動詞の過去形」として習うため、とても紛らわしいですよね。しかし仮定法の役割は、過去の出来事を表現することではありません。
参考:沢田照徹『現代アメリカ語の用法』(中京大学教養論叢, 1968)
あくまでも「現実に起きていないこと」を、仮の状況として説明するときに使われると覚えておきましょう。
仮定法は苦手意識を持つ人も多いと思いますが、しっかりマスターすることで、日常会話での表現の幅もぐっと広がるはず。つまずいたときは本記事を読み返したり、今回の例文を音読して感覚的に使い方を覚えたりして、理解を深めてみてくださいね!