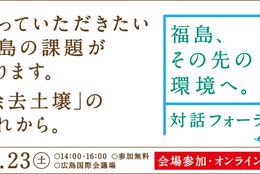「あの日から12年。福島の新たな課題とは。」大学生記者の「『福島、その先の環境へ。』対話フォーラム(仙台開催)」潜入レポート
学窓ラボ、学生ライターの梅田慶太です。
2011年3月11日といわれて何が思い浮かぶでしょうか。
私はこの日が来るといつも東日本大震災の光景が思い浮かびます。私はこの当時京都にいて小学3年生でした。
学校から帰ってくるといきなりテレビに映し出される津波で住んでいた家が流される映像や東京電力福島第一原子力発電所の水素爆発(以下原発事故と記載)の映像など今でも強烈に印象があります。
原発事故によって多くの人の人生が変わり、当たり前の日常が失われるというものでした。あれから12年経ち一つひとつ復興に向けて歩んでいっていますが新たな課題が生まれてきています。
今回は2023年3月18日に行われた、『福島、その先の環境へ』についてレポートしていきます。
『福島、その先の環境へ。』対話フォーラムとは。
環境省が行っている、東日本大震災及び原発事故からの今後の福島の復興・再生に向けた取組のうちの一つである、「福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた全国での理解醸成」を目的としたフォーラムになります。今回は、8回目の仙台開催にオンラインで参加しました。
ちなみに、以前学窓ラボのメンバーが別の活動に参加しましたので、是非そちらのレポートもチェックしてみてください!
⇒ 【学生記者】あなたは「これまでの福島」と「これからの福島」がわかりますか? 「『福島、その先の環境へ。』対話フォーラム」潜入レポート
↑登壇者の方々。
左から、東京大学大学院情報学環 准教授 開沼博氏、環境省 環境再生・資源循環局長 土居健太郎氏、環境大臣 西村明宏氏、フリーアナウンサー 政井マヤ氏、一般社団法人 HAMADOORI13代表理事 吉田学氏、北海道大学大学院工学研究院 環境循環システム部門 資源循環材料学研究室 教授 佐藤努氏、長崎大学原爆後障害医療研究所教授 東日本大震災・原子力災害伝承館館長 高村昇氏。
↑このフォーラムでは参加者の皆さんの意見や質問を対話ボードとして集約していました。
今回のフォーラムの内容については動画で見ることができるのでぜひ1度みてください。https://www.youtube.com/watch?v=pW9UVpfx12M
ここからは今回のフォーラムの印象的な部分についてレポートしていきます。
まず、このフォーラムのテーマである「除去土壌」について環境省 環境再生・資源循環局 馬場康弘氏より説明がありました。
除去土壌とは、原発事故について漏洩した放射線によって土壌が汚染され、その汚染された土壌を取り除き除染をする際にできた土壌のことです。
私はこの説明を聞いた時に、放射線のことを勉強していたので土壌汚染についてのことは知っていましたが、今まさに中間貯蔵施設に貯蔵されていること、またこの除去土壌は再生利用などを行い全国で分担して処理していくという事を知りませんでした。
またこの説明の中では実際に中間貯蔵施設になっている福島県双葉町・大熊町の町長からのメッセージを聞き、様々な思いを背負いながらこの中間貯蔵施設ができたという事も知ることが出来ました。
次にこの説明を踏まえたうえで、対話ボードに意見を集約し、これを基に対話セッションに移りました。
まず、そもそも再生利用するのかという質問がされました。それに対しての答えは以下の通りです。
放射線を取り除くという事はそう簡単にはいかないため、処分場も普通のごみ処理場のような処分場ではなく特別な処分場を1から作る必要があるためたくさん作ることもできないことや埋め立てる場所がないため再利用できるものは再利用しようというのが再生利用する理由です。
では、この目的を知ったうえで皆さんが思うのが「本当に安全なのか」「何となく不安」という気持ちが芽生えると思います。
会場でもこの不安という質問が多かった印象があります。
まず、国は除去土壌を再生利用する際の基準として以下のように定義しています。
この定義を見て真っ先に思うのが、追加被ばく線量が1mSv/年を越えないという部分です。そこで、皆さんは放射線についてどういうイメージを抱いているでしょうか。
漠然と「危険なもの。」「できれば浴びたくない。」などのマイナスイメージが先行すると思います。実は、日常生活の中でも皆さん知らず知らずのうちに放射線を浴びています。
この上の図を見てみると、人間が生活していく中で年間に2.1mSv浴びています。また、皆さんが一度は経験したことがある胸部X線検査については1回0.01mSvとなっています。
では、放射線というのはどのくらい浴びると危険といわれる量になるのかという事ですが、この図にもあるように、ガン死亡のリスクが徐々に増えることが証明できる量が100mSvとなっています。
また放射線を浴びることや、体内に入ったとしても単純に体内に蓄積されていくというものでもありません。
この指標を踏まえたうえで皆さんもこの国の定義、1mSv/年が高いのか低いのか考えてみてもらえればと思います。
実際再生利用する場合は、除去土壌の上に50cmほどの盛り土をするため放射線の量は少なくなると言われています。
放射線は発しているもの(線源)から距離が離れれば離れるほど影響が小さくなるという性質を持っているからです。
また、質問として、除去土壌を用いている中でその土壌で育った作物や生き物などを人間が食べても害がないのかという質問もありました。
回答としては、極めて可能性が低いという回答でした。この理由としては、今回の除去土壌に含まれているのはセシウムであり、セシウムは体の一部分に蓄積するという性質はないため、全身を循環するが、尿などとして外に排出されるためという事でした。
↑今回のフォーラムのまとめであるグラフィックボードです。「不安」というものがキーワードになっていました。
最後に。
今回のフォーラムを聞いていて共通して出てきたキーワードとして「不安」という言葉でした。私は、この不安には2種類あると思います。
正しい情報を知ったうえで不安、なんとなく怖いから不安という2種類です。
この後者のほうはしっかり自分から情報を調べて正しい情報を選別しながら、知ることで不安な気持ちが解消されることも多いはずです。
放射線は目に見えないためとても怖いものというイメージがついていますが、実際に病気の診断や建物の鉄筋などの歪みや中身を解体せずに見ることが出来ることなどメリットもあります。
しかし、デメリットのみが先行してなんとなく怖いという理由で、この除去土壌の問題について意見を述べてしまうのはとても危険なことです。
このような姿勢が風評被害につながり、新たに苦しむ人を作ってしまうのではと思います。
震災から12年がたった今、もう一度福島の放射線による問題に向き合ってみて、放射線について理解を深めてもらえればと思います。
また理解を深めたうえで身近な人などとぜひ意見を交流してみてください。これが福島のこの問題を多くの人に知ってもらうための第一歩だと思います。
ぜひこの記事をきっかけにもう一度東日本大震災を思い出してもらえると嬉しいです。
文:梅田慶太(学窓ラボ)
編集:学生の窓口編集部
福島、その先の環境へ。|環境省
福島再生・未来志向プロジェクト https://fukushima-mirai.env.go.jp/